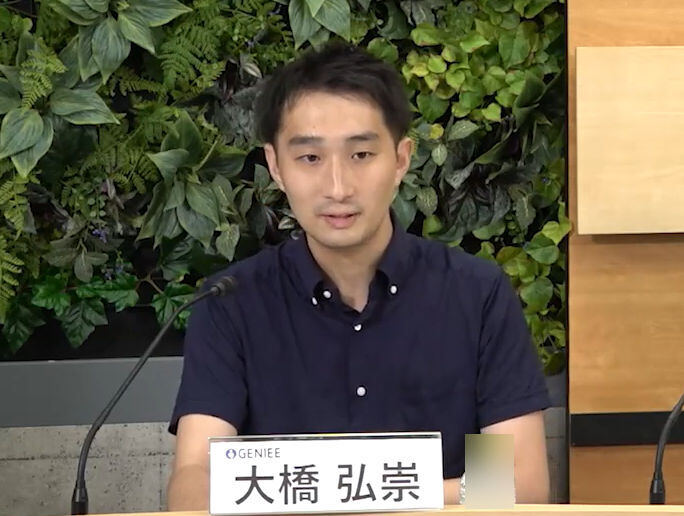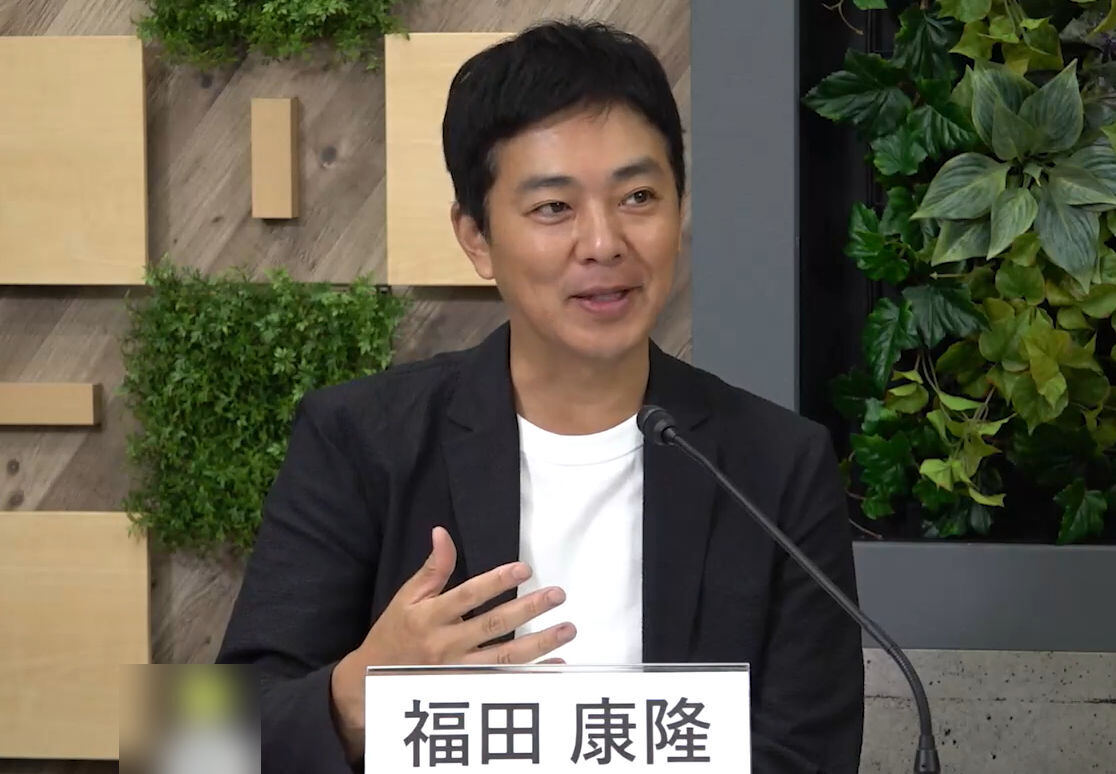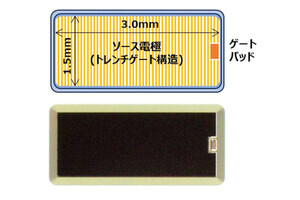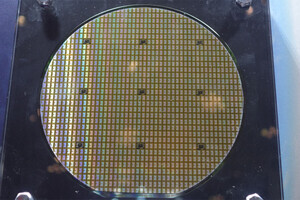8月21日と22日の2日間、マーケティングのサービス・ソリューションの導入を検討するにあたり、利用者に向けて成功イメージと解決策を提供する「TECH+セミナー Marketing Days 専門家とベンダーの対話 トップマーケターが語り合うBtoBマーケティング最前線」を開催した。
2日目の8月22日には、パネルディスカッション「顧客起点でデータを活用! 売上の上がる組織モデルとは?」が行われ、マーケティング領域で多くの知見と成功体験を持つ4人の専門家が、消費者中心のマーケティグの全体最適について、これまでの経験を基に意見を交わした。
参加したのは、クー・マーケティング・カンパニー 代表取締役 音部大輔氏、ジャパン・クラウド・コンサルティング 代表取締役社長 福田康隆氏、ジーニー 上級執行役員 SFA/CRM事業本部 事業CEO 大橋弘崇氏、HAPPY ANALYTICS 代表取締役 小川卓氏の4人で、音部氏がモデレーターを務めた。
消費者中心の全体最適とは
音部氏:消費者中心の全体最適と言うと、BtoCの話だと思われがちですが、皆さんは、どのように考えていますか?
小川氏:顧客視点とビジネス視点は、最終的には一致するはずですが、その間のプロセスや見ているデータについては、ビジネス用語で語られてしまいます。例えば、購入や会員登録のような言い方をしますが、ユーザーからすると単純に1つのハードルでしかなく、顧客視点でのデータの出し方、見方みたいなところができていないと思います。
福田氏:特にBtoBでは、営業フェーズに入ると自社都合でステージ設計してしまうケースがあります。提案書や見積り提出、デモなど、顧客の態度変容とあまり関係ないステージ設計をするケースが多く、やはり、顧客視点でつくり変えることが大事だと思います。
もう1つ、BtoBの場合は企業体で見ないといけない中で、組織の責任者と担当者が見ているものが違うことがあります。現場は二重入力や集計が大変という課題がありますが、責任者は売上増やコスト削減、リスク低減ということを考えているので、それぞれをどう合わせていくのかという、縦横のつなぎ合わせの部分が重要なポイントだと思っています。
大橋氏:実際にツールを導入しているお客さまの場合、データがいろいろなところに分散していて、経営が見たいデータが見られないといった課題や、現場は二重入力が面倒なので止めたいとか、Excelを使っているという課題があり、これをどうやって両方とも解決するのか悩まれている会社さんが多いです。そんな中、我々は顧客管理システムを提供していて、そこにデータを貯めることで、顧客の社内のデータを1つにまとめ、同じデータを見ながら意思決定できるように支援していくケースが多いです。
小川氏:現場は自分たちがやっている取り組みの評価や成果を日々の論論するのですが、経営側から見ると、それらはいろいろな中の1つであって、知りたいのは、どのレバーを押せば売上が上がるのかとか、コスト削減ができるのかみたいなところだと思います。
音部氏:経営者向けと現場向けは、分けて設計したり考えたりするのですか?
大橋氏:そうですね。実際に分けて設計するケースが多いですが、入力元は現場が入れるデータなので、経営はそれを見ながら意思決定していくかたちになります。実際に経営の方がどういうデータを見たいのかという点は、我々のほうでヒアリングしながら、どういったデータを入れていくのか、逆にデータを入れすぎると現場が疲弊してしまうので、別の仕組みで解決しましょうといった提案をしながら、全体設計して進めていきます。データを1カ所に貯めるといろいろな部署でデータを資産として活用できるので、そのデータのパイプラインも含めて設計をしていくのが重要だと思っています。
現場が求めるツールとマネジメントが求めるツール
音部氏:現場が入れるツールとマネジメントが欲しいツールには、どういった違いがありますか?
大橋氏:経営が求めているツールはすごくシンプルで、意思決定に役立つツールです。我々はBIツールを提供していますが、BIツールを入れたからといって、見たいデータがパッと出てくることはなく、今、見ているExcelのデータをBIにもっていくといったところに価値を感じていただく人が多くいらっしゃいます。一方で現場の方は、目前にある営業活動やどんなお客さんにどうアプローチしたらいいのかという細かな課題を解消してくれるものが好まれる傾向があります。
福田氏:「意思決定=リソース配分」だと思います。そこから逆算して、何を見るのかということから考えないといけません。BtoBでありがちなのは、マーケティングはリードを追って、インサイドセールスが案件をつくりますが、この数字が良くても、実際に売上が伸びないみたいなことがよく起きます。そのときに、単純に営業が悪いのか、その前の段階に問題があるのかもっと細分化して、どこに人を投入すべきか、もしくはどこを効率化すべきかという判断ができるようなものが必要になります。そのあたりの知見とセットで提案することが大事だと思います。
小川氏:経営は、効率良く売上を上げたいという中で、どこに手をつければいいのというところを知りたいと思っています。それが、いわゆる現場のKPIと経営者のKPIの違いだと思います。現場のKPIは、自分たちがやっている取り組みに対して重要な指標がありますが、それが各部署を合わせると10個とか20個になります。経営は、この中のどこが一番大事なのかというのがKPIだと思っています。
成功事例をどう活かすのか
音部氏:うちの業界は特別なので、個別最適してほしいというリクエストが出ることがよくあると思いますが、この部分はどう説明されていますか?
福田氏:事例は典型ですが、事例を要求する割に、持っていくと「うちと違う」と言われることがあります。違いに目を向けるとキリがありません。上手くいっているお客さんは、業種や規模が違っても、共通点を見出せる人です。20%の違いにフォーカスしても、生む生産性はすごく低いので、80%に注目していきましょうと言いたいです。
小川氏:事例の話で言えば、その事例自体は役立たないと思いますが、上手くいった背景を説明してあげることが重要だと思っています。それは組織の話だったり、データの見方の話だったり、こういうミーティングをしたからだといった話です。こちらの方がすごく大事ですね。
まず全体設計ありき
音部氏:マネジメントも現場もハッピーという仕組みをつくろうと思ったときに、どんなところに注意していますか?
小川氏:全体設計自体は最初にやる必要はあると思いますが、すべて一度に入れようとするとコストや時間かかり、途中で頓挫する例もたくさん見てきました。やるべきことは2つあって、1つ目は、今あるデータでもまだできていないこともあるはずなので、ツール単体でできることを見つけるパターンです。2つ目は、アクセス解析とメール配信という1つの組み合わせでもいいので、つなげる事例をつくってみることです。小さいながらも一度このプロセスを回すと、その意味が見えて、「さらにつなぐと、こんなことできる」というのがイメージしやすくなります。
福田氏:提案する側からの視点で言うと、よくやりがちなのがスモールスタートです。全体設計がないままスモールスタートするケースが結構あって、これは絶対に上手くいかないと思います。「スモールスタートで早く結果を出しましょう」と言いますが、それだけやっても結果は出てこないことがすごくよくあります。データがないという会社さんも結構ありますが、データがないことは基本的にないので、まず、データを活かして実行系から回していくのがいいと思います。
大橋氏:小さく始めるというのは、全体設計があって初めて有効な手段だと思っています。現場でもExcelからいろいろなデータを引っ張ってきて、データ統合することをやっています。そういったものを自動化してみるとか、すでにあるものをより簡単にできるようにして、ステップバイステップで進めていくことをやっていくと、全体設計の中でしっかり進んでいけるでしょう。
全体最適に向くリーダーとは?
音部氏:どんな人がリーダーになると、全体最適が進みますか?
小川氏:あまり空気読まないタイプと、自分の成果をアピールしたいタイプです。あと、忖度しない人ですね。仕方なくやっているとか、KPIを達成するためにやっているというよりは、これが本当に会社のためになるとか、顧客のためになるという思いがあれば、スキルは付いてくると思います。どちらにしても、自転車レースの先導者のような人が必要です。
福田氏:忖度しないというのは、すごく大事だと思います。もう1つ、トップの支持がある人です。各部門といろいろな調整をしないといけないのですが、そのときにその人の力量に任せると上手くいかないので、最後は上の人がきちんとその人を支援してくれることが欠かせないと思います。
大橋氏:データが分散していることに苛立ちを覚えている人やモチベーションが高い人が引っ張っていくと成功しやすいと思っています。当然、トップのサポートや周りの人のサポートを得られるような人間性が必要ですが。会社として、その人が言っている主張を肯定してあげて、そこに対してこれは事業のためになるというところを認識してあげられる組織をつくれば、その人を中心にプロジェクトが回っていくケースが多いのではないでしょうか。
音部氏:今日は、顧客視点でデータを活用し全体最適にどう誘導を促していくかといったテーマで、識者3人の方から話を伺いました。皆さん、ありがとうございました。