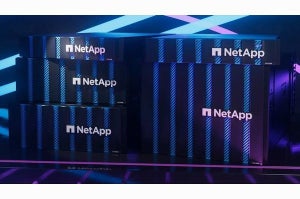ネットアップは7月27日、都内で2024年度の事業戦略に関する記者説明会を開催した。説明会にはネットアップ 代表執行役員社長の中島シハブ・ドゥグラ氏と、同 チーフテクノロジーエバンジェリストの神原豊彦氏が出席した。
4つの“S”で複雑性から解放
まず、中島氏は「日本法人は設立から25周年を迎えた。当社はエンタープライズデータストレージの初期から存在しており、NetApp=イノベーションはわれわれのDNAだ。設立当時は、新しいストレージアーキテクチャとしてNAS(Network Attached Storage)を提供し、ストレージの認識を大きく変えることになった」と述べた。
また、同氏は「これまでに多くの技術分野でイノベーションを達成し、サーバの仮想化技術に合わせたストレージ仮想化技術の実現や、複数のパブリッククラウドにまたがるデータファブリックの実現をはじめ、業界でもユニークな価値あるソリューションを提供し続けている。NASだけでにとどまらず、SAN(Storage Area Network)やオブジェクトストレージ、暗号化技術など、継続的に開発に取り組み、業界における標準仕様策定にも貢献してきた」と、日本法人設立から今までを振り返った。
同氏によると現在、エンタープライズITは「データ」「クラウド」「AI」が交わる大きな交差点にいると述べており、次世代のビジネスにはデータ駆動型のデジタルビジネスが必須ではあるものの、ハイブリッド/マルチクラウド環境におけるデータの断片化が進んでいるという。また、データは増加し続けるとともに多様化が進み、AIをはじめとした新しいワークロードのためリソースの管理が困難になると指摘。
こうした状況に対して、組織のDX(デジタルトランスフォーメーション)をけん引するテクノロジーとして、オールフラッシュ、ストレージサービス、クラウド、コンテナ、ハイブリッド/マルチクラウドを挙げている。一方で、企業・組織は予算の縮小やランサムウェアの脅威、持続可能性、複雑化するシステムへの対応、スキルギャップの解消などに取り組まなければならないという。
NetAppがグローバルで行った調査では、オンプレミスやクラウドに分散したデータの複雑性が上昇し、DXによるビジネス推進に大きな影響と与えていると回答した技術担当上級管理職の割合が98%に達しているという。
中島氏は「アプリケーション、データ、オンプレミス、クラウドなど、カスタムメイドのインフラとデータのサイロ化で複雑化したITシステムに対して、企業はシンプルさを求めている」と話す。
そこで、同社は「Savings(コスト削減)」「Simplicity(シンプリシティ)」「Security(セキュリティ)」「Sustainability(サステナビリティ)」の4つの“S”でデータ、クラウド、AIのテクノロジーをけん引するという。同氏は「4つのSでお客さまを支援し、次の25年に向けて“NetApp体験”を向上させていく」と力を込める。
4つのSを実現するネットアップの「データファブリックプラットフォーム」
これら4つのSを実現するものがネットアップが従来から提唱している「データファブリックプラットフォーム」というわけだ。同プラットフォームは「ストレージとデータファブリック」と、コスト最適化と自動運用が可能な「Spot」などを含む「クラウドオペレーション」の2つの領域でそれぞれ製品・サービスを展開している。
そして、続いて登壇した神原氏がストレージとデータファブリック領域について重点的に説明した。同氏はSAN特化型のフラッシュストレージ「ASAシリーズ」、ライセンスモデルを見直したストレージOSの「ONTAP One」、統合データ管理コンソール「NetApp BlueXP」、ストレージ保証プログラム「NetApp Advance」、AIの取り組みを紹介。
ASAシリーズは6月に発表しており、VMWareやミッションクリティカル用途に適した新しいストレージ。耐障害性を備えたアクティブ/アクティブ構成であり、NVMe/FC、NVMe/TCP、FC、iSCSIプロトコルに対応し、99.9999%の可用性を保証。
ランサムウェアから迅速なリカバリを実現するセキュリティと保護、他社のオールフラッシュストレージと比較して、CO2排出量を最大70%抑制するサステナビリティにも対応している。
ASAについて神原氏は「AIなどの技術進化により、プログラミングがシステムにアクセスするという時代になると当社では想定しており、トランザクション数は膨大なものになるだろう。そのため、業務システムにつながるストレージに関しても性能と信頼性の強化が重要になることから、ASAを提供する」と説く。
ONTAP Oneはライセンスモデルを見直し、同社ストレージの「FAS」「AFF Cシリーズ」「同 Aシリーズ」、ASAシリーズの全モデルを対象としている。ONTAP Oneによるシングルアーキテクチャで、すべて同じ操作で利用することを可能だ。
これまではONTAPの各機能をユーザーが選択して購入していたが、すべての機能を利用できる。同氏は「ストレージに求められるすべての機能を包含した、単一のライセンスモデルとして提供する。新しく販売する機種を対象にするだけでなく、お客さまが利用している既存製品でもONTAPをバージョンアップするだけで利用可能だ」と強調した。
BlueXPは昨年11月に発表し、同社の最大の特徴であるデータファブリックを具現化する統合データ管理コンソール。
ハイブリッド/マルチクラウド環境に対応し、クラウドごとの操作の違いやバックグランドのアーキテクチャの違いなどを抽象化し、バックアップ、セキュリティ、コンプライアンスといった企業のITポリシーにもとづいたデータ管理を可能としている。
NVIDIAとのAIに関する協業を強化
NeApp Advanceは、新たに「ストレージライフサイクルプログラム」(保守サポートオプション)、「ランサムウェアリカバリ保障プログラム」(AFA/ASAのオプション)、「99.9999%データ可用性保証プログラム」(ASAのオプション)の3つのオプションプログラムを追加。
ストレージライフプログラムは追加料金を支払えば、AFFとFASに搭載するコントローラを3年に1度無償提供する。3年後にオンプレミスを継続して利用するか不明でクラウドに移行する場合は、差額分をクラウドのクレジットとして利用してもらう。
ランサムウェアリカバリ保障プログラムは、ランサムウェア攻撃によるデータ損失を回避し、バックアップからの確実な普及を保証し、99.9999%データ可用性保証プログラムはストレージの継続的な稼働を保証するというものだ。シーにもとづいたデータ管理を統合的かつ容易に行うためのツールと位置付けている。
一方、AIの取り組みについて同氏は「AI活用の場面が広がる中で、これまで以上に精度を高めるとともにビジネスを支えるプラットフォームとしての信頼性が求められる。AIの精度を高めるためのフィードバックループをスムーズに行うためにエッジ、コア、クラウドにまたがるデータの流れに着目したAIプラットフォームリファレンスアーキテクチャとして『NetApp Data Pipeline』がある」と説明した。
同アーキテクチャは、ハードウェアに加えAI開発に必要となるさまざまなソフトウェアツールセットを提供することで、データの自由な移動をシンプル・セキュアに実現するという。
NVIDIAとは同アーキテクチャにもとづき協業しており、その最初の成果として「NetApp ONTAP AI」などがある。今回、同社との協業を加速するため、AIを商用環境で利用できるように堅牢性、セキュリティ、信頼性を担保する「NVIDIA AI Enterprise」への参画を表明している。
神原氏は「当社のアーキテクチャが信頼性を持ち、AIのプラットフォームを支えていく」と、意気込みを語っていた。