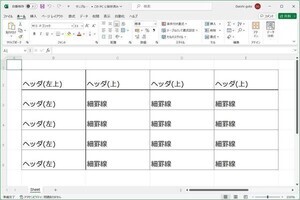「成長の牽引役としての役割を果たす」─みずほ証券社長の浜本吉郎氏はこう話す。米国では債券引受でベスト10に入るなど存在感を高める。強みは銀行と証券の連携。例えば法人ビジネスでは銀行が資金を提供し、証券がアドバイスをするという形。また、足元の株価を受けて、日本の個人投資家が株式市場に参入、この受け皿としての役割をどう果たすのかも問われる。浜本氏が目指すものとは。
【あわせて読みたい】みずほFG社長・木原正裕「2年目の課題」、社員との対話を続けて1年
欧米の現状はどう見えたのか?
「世界経済全体はリスクを抱えながら、高値警戒を強めながらも徐々に推移していくと見ている」と話すのは、みずほ証券社長の浜本吉郎氏。
浜本氏は今年6月、米国と英国に足を運んだ。現地のオペレーションの視察、投資家との対話、そして後述する買収案件があったからだ。
米国の現状を浜本氏は「引き続き低い失業率で、高いインフレ率。期待インフレ率よりも、やや警戒的、予防的な高い金利が前提になっている」と話す。
欧米、特に米国では2022年3月以降、急速な金利引き上げが進んできた。23年6月のFOMC(米連邦市場公開委員会)では一旦停止したものの、FRB(米連邦準備制度理事会)議長のジェローム・パウエル氏は年内にあと2回の利上げを示唆している。米国はインフレに対する警戒感が引き続き強い。
欧米を見てきた目から、日本市場はどう見えているのか?
「引き続き、金利が低位に抑えられている。そして日本企業の株価はバリュエーション(企業価値評価)的に安いなという感覚はある。また、中国を巡る地政学リスクなどもあり、バリューチェーンが日本と欧米という大きなグループに回帰している」
日本の株価は上下動を繰り返しながら比較的高い水準を保っているが、それは中国に向かっていた海外投資家の資金が「消去法」的に日本に投じられているからという見方が強い。「英国のヘッジファンドの人と話していたら『30年ぶりに日本で調達して日本株を買っている』と言っていた」と浜本氏。
今後もこの流れが続くかは、日本銀行の金融政策や、東京証券取引所が上場企業に要請しているPBR(株価純資産倍率)の改善などの施策がプラスに作用するかどうかにかかる。
また、海外投資家が日本買いを進める一方で、国内投資家の日本売りが続いている。ただ、足元で国内投資家は「含み益が戻って、投資余力が出てきている」(浜本氏)。
その意味で日経平均の今後については、3万3000円近辺で揉み合って日柄調整をした後、「今年度の後半には3万5000円もあり得る」と見る。
米国は金利の急激な引き上げで、シリコンバレーバンク(SVB)始め中堅銀行が破綻するなど、一時先行き不透明だと見られたが、引き続き未公開株に投資するプライベート・キャピタルの勢いなど現地の感触を得て「大きなクラッシュの要因はない。ただ、上値を突き抜ける材料も足元ではない」と浜本氏。こうした状況を、証券ビジネスとしてどう捉えるかが問われる。
FGの中期経営計画を牽引する役割
2023年5月18日、みずほフィナンシャルグループは新たな中期経営計画を発表した。19年度から「5カ年計画」を進めてきたが、システム障害や足元の経営環境の大きな変化を受けて1年前倒しで策定。
業績目標は、25年度に連結業務純益で1兆円から1兆1000億円を目指す(23年3月期は8052億円、19年3月期は3933億円)。
この目標達成に向けて特に、資産形成・運用ビジネスで500億円、国内法人ビジネスで700億円、グローバルCIB(Corporate and Investment Bank、銀行、証券の一体化)ビジネスで600億円を積み上げる見通し。
浜本氏は、この中計におけるみずほ証券の役割を「成長の牽引役」だとし、「証券ビジネスで、国内でナンバーワンを取りたい」と意気込む。
事業の成長に向けたドライバーとなるのが、前述のグローバルCIB。このビジネスモデルを特に実践しているのが、米国みずほ証券。そもそも、オフィス自体が銀行、信託、証券という枠組みにとらわれていない。看板には「Mizuho」とあるが、中では各事業の担当者が入り乱れて仕事をしている。
「日本では法律の壁はあるが、この姿の実現は私が目指しているものであり、先輩方から引き継いだ目標でもある」
その結果、投資適格(IG債)のDCM(債券資本市場)で、過去10年間、米国でトップ10以内につけている。また、非投資適格のDCMでも10位程度、ECM(株式資本市場)でもトップ10入りが視野に入る(いずれもディールロジック調べ)。
浜本氏は「CIBは、プロダクトそれぞれが強くなるのではなく、全体のバリューチェーンが強くなることが大事」と話す。
例えば、企業が自社を見直して事業を売る、あるいは成長を目指して他社を買うという時、必要になる機能としてM&A(企業の合併・買収)、ファイナンス、ECM・DCM、シンジケーション(協調融資)、デリバティブ(金融派生商品)、セールス&トレーディングなどがある。
浜本氏は、その起点として重要なのが、各産業に通じた専門家「インダストリアルカバレッジ」だとする。そうした専門家が企業の経営陣と戦略について話し合える関係を築くことが大事だという。そしてもう一つ重要になるのがアドバイザリー(助言)業務。
ただ、この2つの業務はみずほにとって「長い間、ミッシングピース(足りない部分)だった」と浜本氏。これまでは基本的には自前で強化しようと取り組んできたが、この数年は提携・買収も視野に検討を進めていた。
折しもコロナ禍によって業界全体でM&Aが停滞。ブティック的にM&Aアドバイザリーを手掛ける企業は、業績が厳しくなるところが増えた。そのため、彼ら自身も生き残りに向けたパートナーを探していた。
そんな中、みずほも複数の候補と議論を重ね、23年5月に米投資銀行のグリーンヒルを約760億円で買収することを決めた。経営陣やブランドは存続させるが、米国みずほ証券と一体運営する。
「ミッシングピースが埋まり、フル装備に一歩近づいた。欧州はもちろん、日本のメンバーとのコラボレーション次第で、日本企業をお手伝いする機会が大きく広がる。今までは米系大手の独壇場だったが、より日本企業に近い我々が寄り添いながら仕事させていただける」
この中計期間中も、米国事業が牽引することになるが、一方で「米国一本足」でも危うい。そこで欧州やアジアにも投資をし、事業を強化していく。
ネット証券との連携をどう進めるか?
23年3月期はコロナ禍の影響が残る中、個人の取引は低調で、証券各社は苦しんだ。だが今期は前述の海外投資家の日本買いなどもあり株価は上昇。岸田政権が打ち出した「資産所得倍増プラン」もあって、かつてないほど個人の投資への関心は高まる。この波をどう捉えるか。
「我々は制度に乗るだけでなく、これまで『貯蓄から投資へ』が進んでこなかったボトルネックに真剣に取り組まなければならない」
みずほ証券は22年10月、楽天証券ホールディングスの議決権比率19.99%分、約800億円を出資した。いわばパートナーになったわけだが、浜本氏は楽天証券HD社長の楠雄治氏とほぼ毎週のように議論している。
その場では例えば、「従来型の総合証券のビジネスモデルは今後、持続しないのではないか」といったテーマも話し合われた。
従来は株式や投資信託などの商品が顧客の「前」に並んでいて、営業担当者は売りたい商品に誘うようなスタイルだった。
今後はそうではなく、営業担当者は顧客の「横」で、同じ目線で商品を見て、一緒に投資戦略を立てていく。その助言は商品から独立し、顧客にとって最適なものを選ぶ必要があるのだ。
こうした流れから、みずほ証券では支店での個人向け営業において収益目標、つまりノルマを外した。「今は、どれだけ収益を上げているか、どの商品をどのくらい売っているかといったことを評価の対象としていない。この流れはもう後戻りしない」
その意味で、今後の対面営業は顧客の数を増やすだけでなく、コンサルティングに特化して、顧客を深掘りしていく。
そして深掘りした結果として導き出した、例えば事業承継、相続といった課題に対してはグループの銀行、信託と連携して解決していく。
一方、ネットに親和性の高い世代などはコンサルを必要としないケースも多い。そうしたネット証券による取引を求める顧客は、楽天証券やPayPay証券(PayPay35.0%、ソフトバンク30.6%、みずほ証券34.0%を出資)に送客していく。
「全てのチャネルを自立させて駆動していくことで、1億2000万人は無理でも、多くのお客様にアクセスしていく」
この国内証券戦略はグローバルCIBと並ぶ、みずほ証券にとっての大きな柱となっている。
楽天証券、PayPay証券に対しては出資をしているため、両社が強く成長すれば、みずほ証券にとってのリターンも大きくなる。そこに向けては、みずほ証券から両社への商品供給も行っている。例えば、IPO(新規株式公開)銘柄や、個人向けの社債を供給すると「しっかり売れていく」(浜本氏)。
一方、楽天証券の顧客の中からも、今後資産が増加していく中で、中には対面のアドバイスを求める人も出てくる可能性がある。さらに、そうした顧客はプロ投資家レベルのリサーチを求める動きが出てくるかもしれない。そのニーズをみずほ証券が捉えるということも、今後考えられる。
日本の「金融リテラシー」を高めるために
多くの人が投資の世界に入ってくるとなるとリテラシー、金融教育の重要性が増す。政府も、金融経済教育を国家戦略として進めるべく、24年中に「金融経済教育推進機構(仮称)」を設立する方針。
みずほ証券もこれまで、地道な取り組みを進めてきた。全国の支店の支店長や管理職だけでなく、若手の担当者も含め、地元の小・中・高校で授業を行ったり、教材を提供している。
また、大学では慶應義塾大学、京都大学・大学院、一橋大学・大学院、東京大学大学院、國學院大学で寄付講義・寄付講座を行っている他、早稲田大学と共同で高校生向けのネットでの教育プログラムを提供している。
楽天証券とも金融教育における連携を進めていく考え。
「お客様のリテラシーが上がり、リスクとリターンのバランスがわかるようになることで、今の資産所得倍増プランが目指しているように、自分の力で自分の将来をつくり、自分の身を自分で守ることにつながる」
いくら素晴らしい商品を並べても、それを買う人のリテラシーが高くなければいけないということ。
米国や英国では教育の中に金融投資教育が組み込まれており、中学生くらいまでに学び終えるという。日本は高校生くらいから学び始めるが、どうしても投資についてはプラス面で捉えられてこなかった。
そのため、これまでは投資教育がないままに定年を迎え、退職金をどう運用したらいいのかわからないというケースが多かった。「これまでは、泳ぎを知らないままで2メートルのプールに投げ込まれるようなものだった。そうではなく、小学生のうちに50センチのプールから始め、溺れる危険性や小さな成功体験を知りながら、リテラシーを高めていくことが大事」
今はかつてと違い、楽天証券やPayPay証券などのネット証券では1円から投資できる他、ポイントでの投資も可能。若いうちから資産形成に慣れるための装置は整っている。
「楽天証券、PayPay証券などの提携先を含め、グループを上げて取り組む。さらに、これを社員自身が取り組むことでエンゲージメント(愛着心)にもつながる」
昨年、みずほ証券では延べ63カ店が自主的に金融教育に取り組んできた。浜本氏が指示を出すのではなく、例えばイントラネットなどに各支店の取り組みが掲載されると、それを見た他の支店が呼応して取り組むといった形で「草の根」的に広がっていった。「今年は昨年の倍のペースで取り組みが進んでいる」
前述の、収益目標を外した上での顧客目線でのアドバイザリーと、この金融経済教育は「両輪」。すぐに数字に表れるものではないが、確実に将来に向けた「種」となる。
みずほFG全体の収益力向上と、日本全体の金融リテラシーの引き上げは、一見距離があるように見えるが「顧客本位」という意味で強い連関がある。顧客に何かを買ってもらうという発想ではなく、顧客のニーズを満たすことで収益を高めるという循環を築くことができるかが、みずほ証券に問われている。