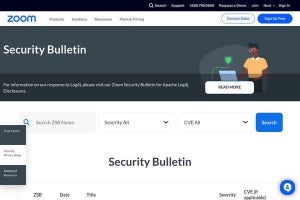ZVC JAPANは6 月28日、オンライン記者勉強会「Zoom Phoneとかなえるハイブリッドな未来の働き方」を開催した。
勉強会には、ZVC Japan UCaas戦略担当の吉田馨一氏が登壇し、「クラウド電話であるZoom Phoneとは何か」「音声ビジネスコミニュケーションの中核をなす電話をらZoom Phoneに置き換えることで、どのような利点があるのか」などについて紹介した。
本稿では、その一部始終を紹介する。
Zoom One
導入工程が簡潔な「Zoom Phone」
コロナ禍を経て、社会的なコミニュケーションインフラとして広く活用されているZoomだが、ビデオミーティングだけではなく、「ZoomPhone」というクラウド電話の機能も提供している。あわせて、会議やチャット、電話、ホワイトボードなどをまとめたサービス「Zoom One」の提供する機能を活用することにより、働く場所や使用デバイスを選ばない働き方を実現することができるという。
「従来のオンプレミス型の電話システムとZoom Phoneの違いとしては、『工程の簡潔さ』が挙げられます。従来のオンプレミス型の電話システムは、ライセンスに加えて、電話機、サーバなどのハードウェア、メーカー保障、保守サービス、通信費用などさまざまな複雑な工程が敷かれています。しかしZoom Phoneは、これらを1つのクラウドにまとめています。そのため、お客さまは、パソコンやスマートフォンを用意するだけで電話を使えるというシンプルな構造になっております」(吉田氏)
吉田氏はZoom Phoneの特徴として、「常に最先端の機能を備えている」という面も挙げた。
上述したように、Zoom Phoneはクラウド型のサービスであるため、導入した時が最も「古い」状態で、日を追うごとに機能がアップデートされていくという。そのため、顧客は常に最先端の機能を享受できることになる。
「『信頼性』もZoom Phoneの特徴です。データはもちろん暗号化されていますし、弊社は世界中にデータ管理センターを持っているので、これらを連携して、信頼性の高いシステムを提供しております」(吉田氏)
「電話から会議への昇格」も実現
Zoom Phoneは、機能の面でもさまざまな特色を持っている。
「先程、Zoom Phoneは『最先端の電話ソリューション』と説明しましたが、それは機能面でも言えることです。さまざまな機能から、特に紹介したいのは『電話から会議への昇格』を実現した機能です。Zoomミーティングとのシームレスな連携を行うことで、電話を掛けている最中も内容によってはミーティングに切り替えることが簡単に行えます」(吉田氏)
このような特徴を兼ね備えたZoom Phoneは3つのプランを提供している。「Zoom Phone Pro」は、自動応答・コールキュー・通話録音などを行うことができ、Cloud PBXフル機能を提供するライセンスだ。「Zoom Phone Japan Regional Plan」は050番号とZoom Phone Proライセンスがバンドルされており、「Zoom Phone Global Select Plan」は0ABJ番号とZoom Phone Proライセンスがバンドルされている。
料金体系は以下の通りとなっている。
日本企業の事例から知る「Zoom Phone」の活用方法
説明会の後半では、日本企業におけるZoom Phoneの導入事例が紹介された。
最初に紹介された千代田化工建設では、「単純なシステムリプレースが高額なため、次世代の音声環境を探していた」「コロナ禍においてニューノーマルな働き方が求められる中、オフィス・在宅などのロケーションに依存することなく利用可能な音声環境の要望が高まった」が、導入前の課題だった。
それに対して、Zoom phoneを導入したことによって、電話をするためにオフィスに出社する必要がなくなったため、ユーザー部門が求める多様な働き方を実現できるようになったほか、PCやモバイルなどの複数のデバイスで利用できることでユーザー満足度が向上しているという。
また、2つ目の事例として紹介された大町自動車学校は、2019年と2023年の2回にわたって大規模豪雨に被災。事務所内のPCや固定電話、書類などがほぼすべて水没するという被害に遭ったという。加えて、数日にわたって停電が続き、生徒と連絡が取れないという状況も経験しており、これらの体験から災害時でも事業継続ができる体制の構築を目指していたそうだ。
Zoom phoneの導入後は、全職員が使用するスマートフォンやタブレットに加えて、校内にデスクフォンを設置し、いつでもどこでも職員が電話を受けられる柔軟な業務環境を確立できているという。
「お客様がZoom Phoneに切り替える主な理由は、迅速なサービスの導入、一元管理が行えること、モビリティ、TCO(総所有コスト)が抑えられること、品質とサービスの信頼性の高さの5点です」(吉田氏)