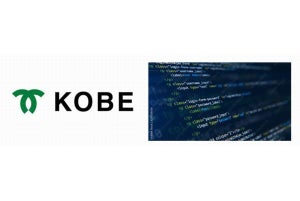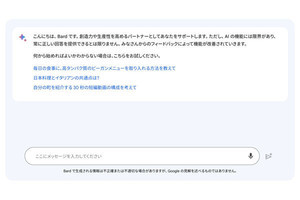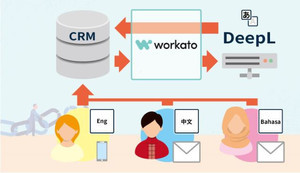独DeepL(ディープエル)は5月12日、メディア向け説明会を開き、2023年7月に日本拠点を東京に開設することを発表した。
DeepL 創業者 兼 CEOのヤロスワフ・クテロフスキー氏は、「当社にとって日本は世界で2番目に大きな市場となる。現在、日本では15人以上の社員が活動しているが、2023年末にかけて人数を倍増させる。企業での翻訳ツールソリューション実装や、翻訳の活用シーン検討などについてベストな方法を提案していきたい」と日本での事業拡大に向けた意気込みを語った。
AI活用と人による品質評価で翻訳精度を向上
説明会では文章作成を支援するAIツール「DeepL Write」が紹介された。2023年1月17日(現地時間)から、英語とドイツ語に対応した同ツールのベータ版がリリースされている。
同ツールはWebブラウザで利用するもので、文章を入力すると単語のスペルや文法の間違った箇所とともに文章の修正案が提示される。
クテロフスキー氏は、「DeepL WriteではAIによるバイアスを排除するように配慮している。同ツールは文章案を提示するためクリエイティビティの要素が強く、AIが直近に学習したデータなどのバイアスがかかりやすくなる。正確で信頼性の高い翻訳のために改善点を常に探している段階だ」と説明した。
DeepLでは翻訳の精度向上にもAIを活用している。説明会では、同社サービスへのAI活用法が紹介された。
同社ではクローラーを用いてインターネット上からペタバイト級のデータを継続的にスクレイピングし、多言語のコンテンツからAI学習のためのデータを収集しているという。AIに悪影響のあるデータを除外するなどのフィルタリングを行い、同社独自のニューラルネットワーク技術を活用してAIモデルに学習させて、サービスへと学習内容が反映される。
翻訳の品質評価は、最終的には人が行っているそうだ。人間の翻訳者がDeepLの翻訳内容をチェックするほか、同一の文章に対して競合他社も含めたツールの翻訳をブラインドで比較する試験を何千回と繰り返し、スコアを付けて評価しているという。
このほか、クテロフスキー氏はデータセキュリティやプライバシーに対する同社の対応を紹介した。
「セキュリティとエネルギー効率を考慮し、自社サーバでサービスを稼働させ、欧州の自社データセンターでさまざまなデータを管理している。データセンターの運用にあたっては定期的に侵入テストを実施するなどエンタープライズレベルのデータセキュリティを実現している。また、翻訳された文章は一時的に当社のサーバに保存した後に削除している」とクテロフスキー氏は明かした。
日本の公共機関とAI利用について対話
話題は社会におけるAI活用に及んだ。クテロフスキー氏は、利便性や革新性、AIを活用することで見込める収益性などにより、今後もAIの研究・応用・投資が活発化すると見込む。一方でAIをどのように現実世界に組み込むかが最大の課題になるという。
「元々、AIは品質の評価が難しく、AIに実行させる要件定義の難易度も高い。また、AIが人に代わって意思決定をするようになると、AIの決定が信頼に足るものかどうかが問われる。モデル作成者のミスや悪意によって、AIの行動パターンがユーザーの意図しないものとなることも考えられるため、『AIの責任ある利用』が重要になる」(クテロフスキー氏)
AIの責任ある利用では、AIを利用することで考えられるリスクの見極めとともに、人がどのように監督するかを決め、AIによる意思決定にどのような要素が反映されているか理解することが求められるという。
今回の来日で、DeepLは日本の公共機関とAIに対する規制やガイドライン作成などに関する対話を進めている。説明会では、5月11日に自由民主党の関係者とクテロフスキー氏が対話を行ったと明かされた。
クテロフスキー氏は、「当社は欧州の企業であり、テクノロジーの社会実装と規制対応の経験が豊富だ。企業規模を問わず、日本の企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)や事業変革を支援し、責任あるAIを日本にもたらすことに真剣に向き合っていく」と語った。