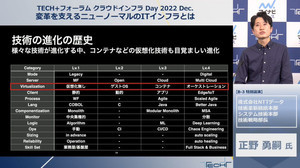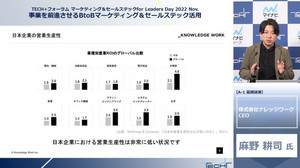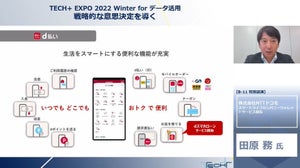市場を取り巻く環境が日々めまぐるしく変化する今、製造業の多くが「良いものを安く」から「価値を価格に変える」という方向に発想を転換し始めているという。これを具現化していく上で避けては通れないのがDXであることはもはや言うまでもない。とは言え実際、製造業はDXとどのように向き合っていけばよいのだろうか。
1月19日に開催された「TECH+セミナー 製造業DX Day 2023 Jan. デジタルがものづくりにもたらすもの」に、京都大学 経営管理大学院 客員教授で、オムロン イノベーション推進本部 シニアアドバイザーの竹林一氏が登壇。「ものづくり企業の未来をデザインする」と題して、製造業のDXにおいて、未来を見据えて考えるべきことや、育成すべき人材について解説した。
社会的課題の解決がイノベーションにつながる
講演冒頭で竹林氏は、DXのベースになるのがイノベーションであり、実現するには「イノベーションとは何か」という組織全体の共通認識が必要になると語った。オムロンにおいては、イノベーションとは「社会的課題の解決」だと定義されているという。同社がこれまで開発してきた製品やシステムには世界や日本で初となったものが数多くあるが、それらは全て社会的課題を解決すべく世に送り出したものだと同氏は強調する。
例えば、1964年に開発した全自動感応式電子信号機は、当時の社会的課題である交通渋滞を解決するためのものであったし、1967年に開発した自動改札による無人駅システムは、高度成長期における駅員の負担を軽減することが目的だった。いずれも常に社会的課題の解決をベースとしてビジネスを展開してきたのだ。
「社会的課題を1つ解決すると、イノベーションが1つ起きているのです」(竹林氏)
「自律社会」に向けて製造業は何を考えるべきか
社会的課題を考えるための海図となるのが、1970年にオムロンの創業者が国際未来学会で発表した未来予測理論「SINIC理論」だ。この理論の基本的な考え方は、新たな科学によって新たな技術が生まれ、それが支えとなって社会が変化していくというものである。これには社会の変容の予測も書かれており、2005年までが情報化社会、現在は最適化社会、2025年以降は自律社会になるとされている。
自律社会では各自の価値に見合うサービスや商品が提供され、企業それぞれが持つ強みを生かして社会貢献するようになる。また、技術がさらに進化し、自動生成や3D、ブロックチェーン、ARといった技術が社会を支えるようになる。では、そこで製造業は何をすべきなのだろうか。
オムロンはこれまでもセンサーのメーカーとして、自動車が流れているところに信号機、人の流れがあるところに自動改札を作り、血流のあるところに血圧計を作ってきた。次の流れは何か。竹林氏は自律社会に向けて、「いよいよデータの流れがビジネスになる時代が来る」と先を読む。
「流れのあるところには課題が生じ、それを解決するところにビジネスチャンスがあるのです」(竹林氏)
また、社会的課題はますます複雑になり、多方面と連携し共創する必要があると竹林氏は予測する。今後、分野を超えたデータ連携を実現するため、オムロンはデータ社会推進協議会にも参画、「DATA-EX」というデータ連携の取り組みにも注力している。この取り組みにはメーカーだけでなく、情報・通信をはじめさまざまな業種の企業が参画している。1社ではできないこともデータやAPIの連携によって解決できるようにしているのがポイントだ。
「これからはデータとものづくりが連携する世の中になっていきます」(竹林氏)