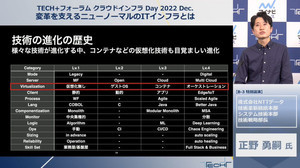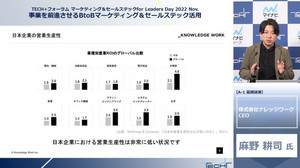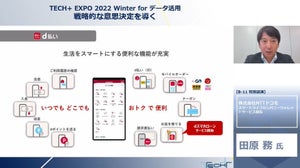フィンテックという言葉が登場して数年、ここにきてブレイクの機運が高まりつつある。一般社団法人Fintech協会 代表理事会長であり、チャレンジャーバンク※のナッジを立ち上げ、代表取締役を務める沖田貴史氏が1月20日、オンラインイベント「TECH+ セミナー 金融DX Day 2023 Jan. DX推進から金融業界を変革する」で、未来の金融をテーマに話した。
※ 新たに銀行免許を取得し、金融サービスを提供する事業者。
Fintech協会立ち上げから8年、450社が参加
沖田氏は大学在学中に電子決済のベリトランス(現:DGフィナンシャルテクノロジー)を共同創業したのを皮切りに、SBI Ripple Asiaの代表取締役などを歴任したシリアルアントレプレナーだ。
Fintech協会は、元々はFintechスタートアップのカジュアルなミートアップが起源だが、翌2015年に法人化した。沖田氏は発足時、金融審議会「決済高度化のスタディグループ」にも参加しており、2020年から会長を務めている。
発足当時フィンテックという言葉は新しかったが、現在ではすでに第8期に入り、会員数は約450社に増えた。その中には金融機関、大手企業に混じって、120社を超えるフィンテックベンチャーが名を連ねる。「保険」「コンプライアンス」「融資・与信」など業態やテーマごとに10の分科会が随時開催されているそうだ。
「オープンイノベーションをどんどん推進していく体制に変わってきています」(沖田氏)
金融業界でも”パワーシフト”が起こる
フィンテック業界に長く身を置く沖田氏は、フィンテックの本質を「パワーシフトだ」と説く。インターネットはさまざまな業界の産業構造を大きく変えているが、このパワーシフトの波が金融分野にもやって来るというわけだ。同氏はさらに、「金融は本質的に情報産業。デジタル化との親和性は高い」とし、「本来親和性が高いにも関わらず、なかなか進んでいない。本格的に波及すると大きなインパクトがあるのではないか」と続けた。
では本当に金融分野でもデジタル化は進むのか。実は2012年時点でも、個人の株式売買については73%がオンラインだと沖田氏は明かす。そのため、世界で台頭し始めたチャレンジャーバンクについても、日本市場でも可能性はあると見る。
日本人の銀行口座保有率は97%と高く、口座開設・維持のための手数料は原則不要であるといったことから、日本にはチャレンジャーバンクが必要とされる素地がないという見方もできるが、沖田氏は「国や地域によりサービス特性は異なる」と見解を示す。チャレンジャーバンクのビジネスモデルも一様ではなく、付加価値も同じではないとした上で、「従来、金融サービスの担い手は金融機関だったが、新しいユーザー体験で再定義される」と説明した。
「ユーザーの視点で考えると、十分に(利用する)機会はあると見ています」(沖田氏)
そして同氏は、日本でチャレンジャーバンクが生まれることで、金融の民主化と、金融サービスを提供する主体の多様化が加速すると説く。
金融の民主化は、インターネットによるパワーシフトの結果として、銀行業務もユーザー起点になるというものだ。金融サービスを提供する主体の多様化については、これまでも小売など異業種からの参入があったが、エンベデッドファイナンス(embedded finance)でこの流れが広がり、加速するだろうと説明する。
外資系チャレンジャーバンクの日本進出、既存のフィンテック企業のチャレンジャーバンク転向、さらには既存金融機関の進出などから、沖田氏は「2020年は日本におけるチャレンジャーバンクの前夜」だったと言い、2022年には全銀ネットの開放、ペイロールの解禁など、周辺環境の整備も進んだことを紹介した。