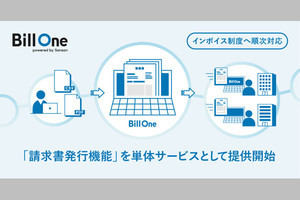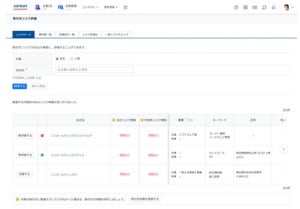SansanのEightが、2012年のサービス提供開始から10年の節目を迎えた。当初は、名刺管理アプリとしてスタートしたEightは、名刺交換後もSNSでつながり続けられる環境を整備し、「ビジネスのためのSNS」へと進化。
さらに、2022年には一人ひとりのキャリア形成を後押する「キャリアプロフィール」としての役割を持たせ、名刺を起点にしてサービスを拡充してきた。そこで、Sansan 執行役員 Eight事業部キャリア ソリューション部 部長の小川泰正氏に、Eightのこれまでの10年と、今後の方向性などについて話を聞いた。
初めて四半期業績で黒字化
Sansanは、2007年に設立。社名にもなっているSansanは、現在でも同社の主力サービスだ。その後、オンライン名刺サービスもスタートし、現在では営業DXサービスと位置づけている。
また、クラウド請求書受領サービスのBill One、クラウド契約業務サービスのContract One、キャリアDXサービスのEightなどを展開。「出会いからイノベーションを生み出す」をビジョンに、「働き方を変えるDXサービスを提供している企業」と、自らを位置づける。
2022年5月期の業績は、売上高が前年比26.2%増の204億2000万円、営業利益は14.2%減の6億3100万円、当期純利益は369.7%増の8億5700万円。成長投資の実行により営業減益となっているが、コロナ禍において加速した企業のデジタル化を背景に、売上高は高い伸びを見せている。
Eightは、2012年から事業を開始。2022年5月期の実績は、売上高が前年比39.9%の22億1300万円と高い成長を記録しながらも、営業損失はマイナス3億8600万円の赤字。だが、第4四半期には1000万円の黒字に転換し、サービス開始から10年の節目で、初めて四半期業績で黒字化した。
Sansan 執行役員 Eight事業部キャリア ソリューション部部長の小川泰正氏は、「本来であればもっと早く黒字化したかった」としながら、「10年間に渡り、多くのユーザーに利用してもらっているということは、企業や個人から求められているサービスであるという手応えもある。黒字化したことで、Eightのビジネスの風向きも変わる」と語る。
Eightのユーザー数は310万人、中小企業向けの名刺管理サービスのEight Teamの導入件数は2819件に達している。
そして、Sansanが推進する「働き方を変えるDXサービス」の提案のなかで、Sansanは「営業DX」、Sansan名刺メーカーは「総務DX」、BillOneは「経理DX」、ContractOneは「契約DX」を提案。Eightは「キャリアDX」を提供することになり、同社の成長戦略の一角として、重要な役割を担っている。
Eightの転換点
Eightの歴史を振り返ると、いくつかの転換点がある。
2012年のサービス開始当時は、「すべての名刺を持ち歩こう」をコンセプトに名刺管理のためのアプリとして誕生。2013年にはメッセージ機能、2015年にはフィード機能、2016年にはシェア機能を追加するなど、SNSとしての機能を拡充。さらに、SNS関連機能の強化を前後して、2015年には学歴やキャリアを掲載できるプロフィール機能を搭載。2016年にはオンライン会議や商談などでも名刺交換ができるオンライン名刺交換機能を提供してきた。2019年には、ユーザーのキャリア形成をサポートする機能として、Eight Career Designの提供を開始。機能を追加しながら、Eightのサービス範囲を広げている。
「Sansanのプロダクトの多くは、社会環境の変化やユーザーの新たなニーズを捉えて、進化を遂げてきた。Eightも同様であり、最初からいまの10年後の姿を描いていたわけではない。名刺管理だけの機能だけでは成長が鈍化すると感じた時期もあった。名刺管理の機能を生かしながら、新たな機能を追加することで、Eightならではの付加価値を提供してきた」とする。
そして、2022年から、Eightは新たな方向性を打ち出している。それは、名刺を起点とした「キャリアプロフィール」という提案である。
タグラインも、従来の「名刺でつながる、ビジネスのためのSNS」から、「名刺管理に、転職に」へと刷新し、ビジネスパーソンが転職する際や、企業が人材にアプローチする際に、Eightを使ってもらえるサービスへと進化させた。人材と企業のマッチングを後押しする役割を備えたというわけだ。
小川執行役員は、「コロナ禍において、対面でのビジネス活動が制限されるなかで、名刺の役割も変化し、Eightも新たな進化を遂げる必要があった。そこで、名刺管理という利用目的はそのままに、新たにキャリア支援の方向性を打ち出した。Eightが、個人のビジネスのライフタイムに伴走し、昇進や転職、キャリアチェンジした後も変わることなく、キャリア形成を支援することができることを目指した」とする。
キャリアプロフィールという方向性を打ち出した理由
Eightが、キャリアプロフィールという方向性を打ち出した理由はなんだろうか。
小川執行役員は、「グローバルの状況をみると、コロナ禍において、仕事をすることに対する価値観や、働く環境が大きく変化している」と前置きし、「企業にとっては、人材の確保と定着化の課題が深刻になっている。その一方で、入社後のパフォーマンスや定着を考えて、従来型の採用方法を見直し、SNSの活用やリファラル(紹介)採用、アルムナイ(出戻り)など、つながりを中心とした新たな採用手法を用いる企業が増加している。日本においても、こうした採用手法を取り入れる企業が増加している」と指摘する。
グローバルの調査では、採用活動における投資としてソーシャルメディアにフォーカスすると回答した企業は51%、LinkedInにフォーカスするという回答も39%に達している。
また、「個人にとっても、コロナ禍で、自分の時間が増え、働き方やキャリアについて内省することが増加。キャリアの棚卸しをして、自身の価値観を軸に仕事選びをしたり、異なる業種や職種への転職といった新たな挑戦を求めたりする人が増えている」と述べる。
Sansanの調査でも、コロナ禍以前よりも転職を考えるようになった人は48.0%を占め、とくに20代は72.8%を占めている。また、転職を考えた理由として、「自分のキャリアや働き方を見直したため」とする人が45.4%と半数を占めた。また、20代の58.4%が、自分の採用市場のニーズを客観的に図るために、転職活動以外のタイミングでもキャリアを棚卸ししているという。
こうしたデータからも、働くことに対する個人の価値観が大きく変化してきたことがわかる。
さらに、海外の調査では、労働者が仕事を見つける方法としては、求人検索サイトが59%であるのに次いで、リファラルが46%、SNSが39%となり、つながりによって求職活動を行っているケースが増えていることがわかる。
「日本の転職市場は就業者全体の4.7%に留まっている。これは、米国などに比べて、転職活動の際に、つながる手段がないことが背景にあると考えている。Eightの機能を用いることで、現職で働いている人たちのキャリアの棚卸しのサポートと、転職を考えている人たちと企業との接点を作ることができると考えた」と語る。
Eightのキャリアプロフィールの登録は、Eight Career Designの機能をベースにしており、自分の名刺を登録し、そこにキャリアを追加。名刺に記載されることがないキャリア情報も、Eightに蓄積できるようになっている。
また、2022年4月以降、新たにキャリアタブを搭載し、キャリア情報にアクセスできる機能を追加した。これにより、「プロフィールを自動作成」「名刺情報を管理・検索」「近況情報が届く」「キャリア情報に出会える」「企業からスカウトが届く」という5つの機能が提供されることになった。
キャリアタブでは、仕事に必要なスキルを向上させるためコンテンツを動画で見ることができる「スキルレポート」、Eightが様々な企業にインタビューした動画を紹介する「企業レポート」、ユーザーの属性に合わせて、Eight Career Designの利用企業の求人情報が表示される「求人情報」、スキルアップやキャリアアップに役立ち、すぐに参加が可能なイベントを表示する「オンラインイベント」を用意している。
Eightでは、キャリアプロフィールの機能のなかで、転職意向度を設定しているが、「転職活動している」、「いい話があれば聞いてみたい」に設定している人が多いという。つまり、企業側にとっては、Eightを利用することで、潜在層の様々な転職シグナルをいち早くキャッチし、プロフェッショナル人材に、他社に先んじてアプローチができるともいえる。
また、Eightでつながっている人が対象になるため、企業側は、つながっている社員から意見を聞くことで、ミスマッチが少なくなったり、転職を考えている個人にとっては、仕事内容についてイメージが沸きやすく、知人がいることで社内になじみやすかったりといったメリットがある。
「転職サービスの多くは、人を求めている企業と、仕事を探している人を、点と点で結びつける方法であった。だが、Eightでは、進化する個人の状況を捉えながら、名刺を起点としたつながりがある企業との接点を作ることができる。企業は、プロフェッショナル人材にダイレクトにアプローチができるダイレクトスカウトだけでなく、自社とつながりのある候補者に対して、スカウトを送信できる。そこに、Eightならではの特徴がある」と強調する。
Eightの今後
同社によると、2022年4月以降、Eightにおける求人に関する閲覧数は25%増となり、求人への応募数は50%増となり、ユーザーのキャリアに関するアクションがかなり増えていることがわかる。また、2022年7月実績で、新規ユーザー累計数は前年同月比7%増、月間アクティブユーザー数は同9%増を記録。「Eightの利用者は、30代、40代が多いが、キャリアプロフィールの機能を強化して以降、20代の登録が増えている」という。
こうしたデータを示ししながら、小川執行役員は、「名刺管理アプリとしての利用から、キャリアという観点での使い方が増加している」と、Eightの刷新にすでに手応えを感じているようだ。
現時点では、用意されているキャリアタブは営業職だけだが、今後、新たな職種を順次追加する予定であり、年内には経営企画、マーケティングのタブが用意する予定だ。また、来年以降、IT専門職や開発などにも広げていくという。
Eightは、今後もキャリアプロフィールの機能を強化していく予定だという。
「登録された名刺やプロフィールをもとに、業種や役職などにあったニュースや各種コンテンツをレコメンドして提供。名刺の交換領域から、スキルの専門領域を可視化したり、プロフィールには、どんなところで働きたいかといった希望を登録できたりといった機能強化も検討している」という。
Eightのなかのプロフィールを充実させることで、これまでの職務経歴書の役割を置き替えることができるようになるともいえる。「Eightのなかに職務経歴書のようなものが作られ、これに対して、別のEightユーザーが紹介や推薦を加えるといったこともできるようにしたい」という。Eightの画面では、「自分タブ」が用意されており、今後、この機能を充実させ、よりパーソナライズ化できるようにする考えだ。
同社では、10周年企画として、プロフィール登録を充実するための企画を実施しており、キャリアアップのチャンスを掴みやすくしたり、次のキャリアを考えるきっかけを提供したりするという。さらに、同じ業種や職種の人がどんなところに転職したのかといったEightが持つ統計データを使いながら、診断サービスも提供する。
「現職を続ける人にとっても、自らのキャリアアップに必要な情報を提供したり、キャリアチェンジによる新たな挑戦をする人には、新たな業界などに関する情報や必要なスキルの情報を提供できる。名刺情報をもとにしたキャリアアップ、キャリアチェンジの支援がでは、Eightを使っていれば、ビジネスにおける体験の向上や、ライフプランの設計を支援できる」。
また、次のステップでは、転職だけでなく、副業やボランティア、あるいはフリーランスの仕事探しといったところにもサービスの範囲を広げることも検討しているという。
「名刺管理は、管理が目的ではなく、出会うことが目的である。名刺をもとにしたビジネスマッチングの広がりにもEightの特徴が発揮できる。そのためには、名刺の情報、自らが書くプロフィール、そして第三者とのつながりをベースにした情報が大切になる。ビジネス機会の創出、情報共有のきっかけ、転職など、様々な形でマッチングが広がっていくことを目指す」という。
日本のビジネス慣習で一般的となっている名刺を活用し、これにプロフィールを加えることで、つながっている企業や人を通じた活動ができたり、自分の職種にあわせたスキルアップができたりする点が、日本生まれのEightならではの機能と進化だといえるだろう。
Eight事業は、2023年5月期見通しとして、売上高は前年比31.0%~36.0%増となる29億円~30億1000万円を目指す。また、通期では初の黒字化を目指す。
「第4四半期の黒字化の原動力のひとつに、カンファレンスや特定領域に絞ったイベントなど、大型ビジネスイベントの開催による効果があった。今年度も、四半期ごとにこうしたイベントを開催することで、BtoBの売上高を高め、黒字化につなげていく。また、プロダクトに紐づく部分でも、しっかりと売上げを確保する基礎体力がついている」と語る。
今年度の黒字化を達成することで、Eightの機能がさらに強化される地盤が整い、サービスの範囲が広がることになりそうだ。そうした意味でも、通期黒字化を目指す10年目の節目は重要な1年になる。