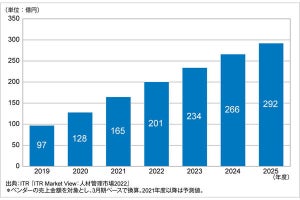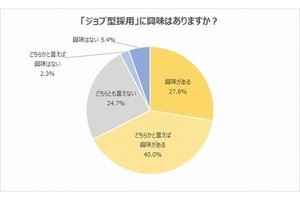日立製作所(日立)は、事前に職務の内容を明確にする「ジョブ型雇用」への転換を加速している。同社の2022年度の採用計画では、ジョブ型の採用比率を94%(1100人中1030人)にする方針で、技術系職種だけでなく、営業や人事、経理などの事務系職種のジョブ型採用も進めている。
具体的には、経験者500人、新卒(技術系)500人、新卒(事務系)30人をジョブ型で採用し、残りの新卒(事務系)70人を、採用してから職務を決めるメンバーシップ型で採用する計画だ。同社は今後、新卒のジョブ型採用に向けた取り組みを強化していく考えだ。
日立の「ジョブ型インターンシップ」とは?
新卒のジョブ型採用の取り組みの一環として、日立では「ジョブ型インターンシップ」を2021年度から実施している。このインターンシップでは、ジョブ型採用と同様に、ジョブディスクリプション(職務記述書)で実施内容と必要スキルを明示して、職務に基づいたスキルを持つインターン生を募る。2週間~1カ月間の長期間型のインターンシップで、実際の職場の業務体験を行うプログラムだ。
2021年度は、技術系職種を中心に約300名(応募約4800人)の学生にジョブ型インターンシップを行った。2022年度からは事務系職種のジョブ型インターンシップも開始、技術系と事務系合わせて400人に拡大する計画だ。学生は「どんな会社かを知りたい」ではなく、「X職種、X事業分野で専門性や経験が生かせるかを確かめたい」という動機でインターンシップに参加している。
では、同社のジョブ型インターンシップとはどのようなものなのだろうか。9月5日~9月16日までの期間、日立本社(日本生命丸の内ビル)で実施されている、事務系職種のジョブ型インターンシップに潜入してみた。以下、その模様を紹介しよう。
事務系職種のインターンシップに潜入
事務系のインターンシップには、約20名(応募約1000名)の学生(主に文系大学学部3年生、修士1年生)が参加している。取り組みのテーマは経理や人事、調達、営業、法務と幅広い。実施内容は職場ごとに大きく異なり、必須スキルなどもポジションごとに異なる。
人事業務を体験する福田陽水さん(都内大学3年生)には、「日立に興味のない優秀学生を“トリコ”にする画期的な採用イベントを検討せよ」というミッションが与えられている。9月16日に自分が考えた採用イベントを発表しなければならない。
福田さんは、優秀な学生が企業に求めるニーズを探るため、知人の大学生50人に対してアンケート調査を実施。その調査結果から得られた志望業界や就活の軸を考慮して、企画を練っていた。
「日立の魅力を探るため、国分寺にある中央研究所にも訪れ、実際に働いたときのイメージを膨らませました。自分が立てた仮説が正しいのか、日立以外の会社の方にもヒアリングしています」と、福田さんは試行錯誤している様子だった。
単刀直入に「日立のジョブ型インターンシップはどうか」と聞くと、「本当にリアルな仕事が体験できて、人事の業務が自分に合っていると確認できました。自分に足りない部分にも気づけたので、人事として働く将来像がクリアになりました。日立のこともよく知ることができて、志望度が高まりました」と答えてくれた。
なぜ日立は「ジョブ型」に転換するのか
なぜ、日立は「ジョブ型」に転換するのだろうか。それは「グローバル市場で勝ち抜いていくため」と、日立製作所 人財統括本部 人事勤労本部 タレントアクイジション部 部長代理の大久保健一郎氏は語る。
同社はグローバル展開に注力しており、2021年度の売上収益と従業員数は、ともに海外の割合が50%を超えている。今後さらにグローバルに事業を拡大させていく考えで、国籍や年齢などの属性によらず、本人の意欲や能力に応じた適所適材の配置を行う。
「一つ一つのジョブを明確にし、グローバルで適所適材を実現していく。環境や事業変化に対応しながら、必要なスキルを従業員が自律的に獲得し続け、多様な人材がワンチームで業務を遂行する組織を目指している」(大久保氏)
ジョブ型の組織への移行を加速させるためには、採用の入口となりうるインターンシップにもジョブ型の考え方を適用する必要がある。今回の取材で、日立が「会社について理解を深めてほしい」ではなく「X職種、X事業について学生に理解を深めてほしい」という具体的な目的を持ってインターンシップを実施していることが分かった。
ただし、明確な目的がないままジョブ型に移行してしまうと、うまく機能しないまま失敗する恐れがあるという。「日立はグローバル事業の成長性を考えてジョブ型に転換している。メンバーシップ型からジョブ型に移行しようと考えている企業は、『なぜメンバーシップ型はだめなのか。ジョブ型に移行する理由はあるのか』といったことを明確にする必要があるだろう」(大久保氏)