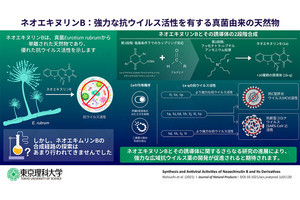東京大学(東大)は2月17日、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の従来株に感染した際に誘導される免疫が長期間にわたって維持されること、そしてこの維持された免疫はデルタ株による再感染に対しても有効であり、かつ個体間での飛沫感染を抑制することも明らかにしたと発表した。
同成果は、東大 医科学研究所ウイルス感染部門の河岡義裕特任教授を中心に、米・ウィスコンシン大学、米・ミシガン大学、国立国際医療研究センターの研究者が参加した国際共同研究チームによるもの。詳細は、ライフサイエンス全般を扱う学術誌「CellReports」に掲載された。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)用のmRNAワクチンは、ファイザー社「BNT162b2」、モデルナ社「mRNA-1273」ともに、パンデミック初期のウイルス(従来株)の遺伝子情報をもとに設計されたものだ。そのため、これらのワクチンの接種、あるいは従来株の感染によって誘導された免疫応答が、その後発生した変異株に対しても感染防御効果を有するかどうかは良く分かっていない点も多いという。
今回の研究では、2021年に世界中で爆発的な流行を引き起こした「デルタ株(B.1.617.2系統)」に焦点を当て、従来株に対して誘導された免疫応答が、高い増殖性と感染伝播力を持つデルタ株への感染防御にも有効かどうか、COVID-19感染動物モデルであるハムスターを用いて検証が行われたとする。
具体的には、ファイザーならびにモデルナのmRNAワクチンを接種した人から採取した血清の、デルタ株に対する中和活性を調査したところ、mRNAワクチンの被接種者血清のデルタ株に対する中和抗体価は、従来株に対する中和抗体価と比べて、ファイザー製で3.9倍、モデルナ製で2.7倍低いことが判明したほか、感染モデルハムスターを用いた調査として、従来株への感染から回復して2か月が経過したハムスターの血清における中和抗体活性について解析を行ったところ、ワクチン被接種者の血清と同様に、デルタ株に対する中和活性は従来株よりも低いことが確認されたとする。
また、従来株の感染から回復したハムスターが、その後のデルタ株の再感染に対して抵抗性を示すかどうかの調査として、従来株による初感染から長期間(2.5か月または15か月)経過したハムスターにデルタ株を再感染させたところ、デルタ株に再感染したハムスターの鼻から検出されるウイルス量は、感染歴を持たないハムスターと比べて低く、再感染個体の肺からはウイルスは検出されなかったという。
さらに、再感染個体と非感染個体の間で飛沫を介した感染伝播が起こるかどうかについての調査として、従来株に感染して4か月が経過したハムスターを、デルタ株に再感染させ(感染個体)、その感染個体のケージから、直接接触が起こらない飼育環境下で、感染歴のないハムスター(曝露個体)を飼育したところ、デルタ株に初めて感染したハムスターでは感染後の肺や鼻でウイルスが効率よく増殖し、さらに曝露個体すべてからウイルスが検出された一方、再感染させられたハムスターでは、肺や鼻でウイルスは検出されず、曝露個体でも、鼻洗浄液を含む鼻と肺の検体からウイルスは検出されなかったという。
これらの結果は、従来株の感染によって誘導された免疫は、長期にわたり記憶され、抗原性の変化した変異株に対する感染防御に寄与することを示すものだという。ただし、この免疫が現在、爆発的に感染者が増加しているオミクロン株に対しても感染防御効果を有するかどうかは今後検証する必要があるとも研究チームでは説明している。
なお、今回の研究を通して得られた成果は、変異株のリスク評価など、行政機関が今後のCOVID-19対策計画を策定、実施する上で、重要な情報となると研究チームではコメントしている。