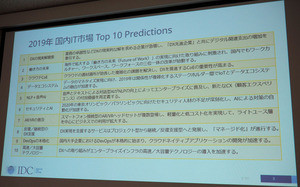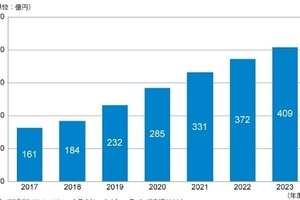IDC Japanは8月20日、国内ベンダー/企業の「データエコシステム」に対する取り組み状況の調査結果を発表。これによると、流通データの最大化、データ共有を行う事例の多様化、公共性の高いユースケースにおける事例の先行といった、3つの傾向がみられるという。
同社は、企業内部における多様なファーストパーティデータを外部のセカンドパーティ(協業先の組織)/サードパーティ(協業先以外の外部組織)データと掛け合わせ、新たなビジネスモデル/収益モデルを創出すべく形成するステークホルダーの集合体を「データエコシステム」と定義している。
今回発表した調査では、データエコシステムに関わる多様なプレイヤーの中でも、「産業横断データ取引基盤」「Data as a Service」「情報銀行」「データ流通推進活動」に関わる事業者に焦点を合わせた。
3つの傾向のうち1つめとして、情報銀行などのパーソナルデータ流通を推進する事業者では、データ提供側に対して新鮮かつ継続的な体験を生み出すことにより、流通データを最大化しようとする傾向がみられるという。
パーソナルデータを利用する地方創生、副業支援、融資サービスの最適化など、ユースケースは多岐に渡るとのこと。
産業系データを中心に扱う産業横断データ取引基盤やData as a Service(DaaS)を推進する事業者では、データ流通基盤上で多種多様なデータを配合してデータ利用側がビジネスにつなげやすい形にする「データブレンディング」が、データエコシステムの活性化には肝心と考えているという。
加えて、プライバシーやコンプライアンス管理の手間を軽減するための取り組みも、データ提供側/利用側の双方に対してベネフィットを生みだす重要な差別化要素となりつつあるとしている。
2つめとして、企業または産業を横断する形でデータ共有を行う事例が多様化しており、その方向性は「非競争領域のデータ共有」「地域特化型データ共有」「デマンドチェーン型データ共有」に分類されることがわかったという。
また、業種や立場が異なるステークホルダー間でデータ共有をスムーズに行う上では、データの収集、保護、品質管理、統合、準備、学習、分析、活用などの各プロセスと、それを支えるテクノロジー及び、各プロセスに関わる組織や人の概念である「データパイプライン/DataOps」の整備が必須になりつつあるとのこと。
その上で、「データ標準化に向けたルール作りや関連する技術開発」と「データビジネス創造に向けた人材間/組織間連携の推進」が不可避な取り組みになると、同社はみている。
3つめは、パーソナルデータの使い道について不安視する個人消費者が未だ少なくない中で、感染症の予防対策、防災、治安の維持など、公共性の高いユースケースにおいては、パーソナルデータの活用に対する受容性が比較的高く、事例が先行する傾向がみられるという。
また、地域密着型でパーソナルデータ流通を推進する事業者では、特定地域において、まずはパーソナルデータ利用の成功事例を確立し、将来的に国内外の多様な地域にデータ流通基盤を横展開していくといったロードマップを描くケースが目立つとのこと。
こうしたことから公共性と地域密着性を重視した上でのユースケース作りが肝心になりつつあると、同社は考えている。
同社コミュニケーションズのシニアマーケットアナリストである鳥巣悠太氏は、「データエコシステムに関わるベンダーは、DX/IoTソリューションを企業に提供する際、データエコシステムを最大限活用することで、POC(Proof Of Concept)フェーズにおける活用データを増やし、データから生み出すアイデアの幅を広げることが必須となる。また、ソリューションのKPI(Key Performance Indicator)を設定する際、活用可能なデータ量や種類、データパートナーやアイデアの数などを複合的に評価することも肝心となる」としており、また「COVID-19の影響により、人々の働き方に対する考え方が大きく変化する中、専門職の人材が持つ感覚的能力や、人に対する同僚、顧客、知人、家族からの評価など、人の能力や評価をあらゆる角度からデータ化して流通させる必要がある。それにより、従来と比較して圧倒的に柔軟なワークスタイルが確立し、また適材適所な人材リソースの配分が可能となる」と述べている。