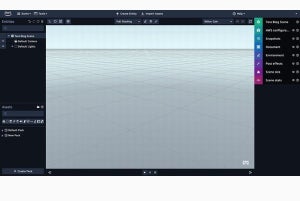国内外のベンダーからさまざまなデバイスが発表され、「VR(Virtual Reality:仮想現実)元年」と言われた2016年。それから約2年が経つが、VR、AR(拡張現実)、MR(複合現実)は、企業においてどの程度導入が進んだのだろうか。そもそも、VR/AR/MRはビジネスでの利用にどのようなメリットをもたらすのだろうか。
今回、VR/AR/MRのビジネス利用の可能性を探るべく、ガートナー ジャパン ITインフラストラクチャ&セキュリティ 主席アナリストの針生恵理氏に話を聞いた。
グローバルと異なり、VRよりもARが進む日本市場
ガートナーは、VR/ARを(「イマーシブ・テクノロジ」と総称)2018年の戦略的テクノロジの1つと位置付けている。VRは「現実世界を遮断したデジタル環境を構築すること」、ARは「物理的な世界の上にデジタル・コンテンツを重ねる」と定義している。MRは、VRとARの両アプローチを拡張し、物理的な世界の取り込みを強化するものである。
針生氏は、ビジネスにおけるVR/ARの特徴として、AI、モバイル、クラウドとつながっていることを挙げた。これに対し、コンシューマーユースにおいては、単体で使われているという。
ご存じの方も多いと思うが、ガートナーは、テクノロジーを5つの段階(黎明期、「過度な期待」のピーク期、幻滅期、啓蒙活動期、生産性の安定期)で市場の成熟の過程を示す「ハイプサイクル」を公開している。
2017年のエンドユーザー関連テクノロジのハイプサイクルによると、日本において、VRは「過度な期待」のピーク期の上り坂に、ARは下り坂に位置しているという。現時点では、VRよりもARのほうが進んでいるというわけだ。この点について、針生氏は「ビジネス利用においては、現実感を残しておいたほうが、なじみやすいから」と語る。
ちなみに、グローバルのハイプサイクルにおいては、VRは「啓蒙活動期」、ARは「幻滅期」に位置し、より実用段階に近づきつつあるが、日本ではビジネス活用では試行錯誤の段階にある。
針生氏は「日本において、VRとARがビジネスに浸透するテクノロジーになるまでには、5年から10年かかる」と話す。
利用が進んでいる業界は病院、建設、製造、自動車
とはいえ、少しずつではあるが、日本企業でもVR/ARの利用は進んでいる。そうした業界の1つが病院だ。
「病院では、治療の質を向上するため、シミュレーションにおいてVRやARが使われている」と針生氏。VR/ARを用いて、画像情報の共有、動画での確認、映像コンテンツの提供、仮想手術の実施といったことが行われている。
建設業界でもVR/ARの導入が進んでいる。例えば、大成建設はシミュレーションによりデータセンターの気流を可視化することで、冷却の効率化と品質の向上を目指している。また、明電舎では、VRを用いた安全管理システムの運用を開始して安全教育を目指しているが、これもまた「利用者の仕事の質を向上することに役立つ」という。
針生氏は、「建設業界の最大の特徴は、身近なものを見ることがなかなかできないこと。建設の現場も遠くにあったり、複数あったりすることから、現場にいること自体難しい。また、事業の規模が大きいため、仮想空間で見る意義も大きい。そのため、もともとシミュレーションに対するニーズがあった」と話す。
また、「建築物は試しに作ってみるわけにはいかない」こともVR/ARの導入を促進する要因だそうだ。「マンションの場合、日当たりの状況などを、事前に顧客に見せることができないが、それが後からクレームにつながることもある。そうした問題を解決する用途として、セールスやマーケティングのツールとしても使うことができる」と針生氏はいう。
同様の理由により、製造や自動車業界でも、VR/ARの導入が進みやすいそうだ。例えば、マツダでは塗装シミュレーションシステムにMRを導入している。このシステムにより、エンジニアとデザイナーの情報共有の効率が上がり、これまで必要だった「すりあわせ」や「手直し」といった作業が減ることになる。
そのほか、米GEでは、航空機のエンジンのメンテナンスに「デジタルツイン」を活用している。デジタルツインとは、物理世界に実在するものをデジタル上に再現するという考え方をいう。これにより、遠隔のメンテナンスをより安全に行うことが可能になるという。
針生氏は、VR/ARの導入メリットとして「業務の質の向上」「効率化」「コラボレーション」を挙げる。そして、「やり直しがきかない、いわゆる"命に関わる"製品やサービスを提供する業界で、VR/ARの導入の意義がある」と話す。