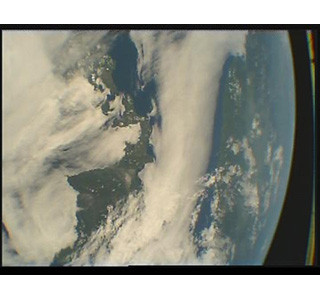東京大学は7月7日、理化学研究所(理研)と共同で、植物などの光合成/水分解の仕組みを利用することで、中性の水を分解して電子を取り出す人工マンガン触媒を開発したと発表した。
同成果は、理研 環境資源科学研究センター 生体機能触媒研究チームの中村龍平チームリーダー、山口晃大学院生リサーチ・アソシエイト、東大大学院 工学系研究科の橋本和仁教授らによるもの。詳細は、英国のオンライン科学雑誌「Nature Communications」に掲載された。
水分子は、自然界に最も豊富に存在する電子源の1つであり、水素または有機燃料の製造を担う重要な化学資源である。自然界では、植物などの光合成生物がマンガンを含む酵素(生体マンガン酵素)を利用して水から電子を獲得し、その電子を用いて二酸化炭素から炭水化物を作り出している。この植物の水を分解する酵素の構造を模倣し、水から効率よく電子を引き抜く人工マンガン触媒の開発が行われてきた。人工マンガン触媒は、強酸や強アルカリ環境では効率よく水から電子を引き抜けるが、中性環境では活性が大きく低下する。しかし、人工マンガン触媒が中性環境で駆動しない理由や、生体マンガン酵素と人工マンガン触媒の活性の違いの起源については不明のままだった。
研究グループは、中性環境における生体マンガン酵素と人工マンガン触媒の活性の違いとして、電子/プロトン輸送の機構の違いに着目し、人工マンガン触媒の電子/プロトン輸送の経路を調べた。その結果、水分解過程(2H2O→O2+4e-+4H+)において、生体マンガン酵素では電子とプロトンが同時に移動するのに対し、人工マンガン触媒では、電子とプロトンが個別のタイミングで移動することを突き止めた。この結果に基づき、人工マンガン触媒にプロトン受容能力が大きい塩基を添加し、電子とプロトンの移動タイミングを調整すると、中性環境における水分解活性は15倍増大し、強アルカリ環境で得られる値の60%にまで到達したという。
研究グループでは、今回の成果が、クリーンで豊富な中性の水を電子源とした水素製造ならびに低環境負荷の有機燃料製造につながることが期待できるとコメントしている。