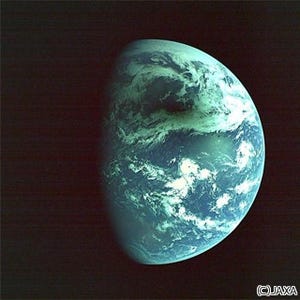カーナビやスマートフォンの普及によって、位置情報が得られる衛星測位サービスは身近なものとなった。この衛星測位に用いられているのは主に米GPSだが、より安定した高精度な衛星測位サービスを実現するために進められているのが、準天頂衛星システム(QZSS)だ。
準天頂衛星システムは2010年に初号機となる「みちびき」が打ち上げられ、JAXAが運用を行っている。「みちびき」は数字の「8」に似た準天頂軌道を描き、1日のうち8時間、日本の上空の高仰角の位置にある。このみちびきとGPSを合わせて利用することで、例えば、ビル街など低仰角では補足しにくい場所でも測位サービスが利用可能になるといったメリットが得られる。
みちびきに続いて、同じく準天頂軌道上2機と、静止軌道上1機の開発が決定しており、2016年度から2017年度にかけて打ち上げられる予定となっている。準天頂軌道上の3機は、順に8時間ずつ日本上空に位置し、1日24時間をカバーする仕組みだ。
この準天頂衛星システムは2018年度から本格的なサービスを提供する予定で、2013年3月に設立された民間の準天頂衛星システムサービス株式会社(QSS)がその運用などを担うこととなっている。
2月13日、この準天頂衛星システムサービスが主催する、準天頂衛星システムの最新情報や利用促進のを目的とした「準天頂衛星シンポジウム」が都内で開催された。
シンポジウムでは、内閣府 宇宙戦略室 参事官である野村 栄悟氏が「2020年の東京五輪での活用も考えながら整備を進めていく」と挨拶を述べ、日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)の坂下 哲也氏が準天頂衛星への期待を、また宇宙航空研究開発(JAXA)が初号機みちびきの成果を講演し、衛星測位利用促進センターの松岡 繁氏は観光やIT農業など様々なシーンでの実証実験やその推進体制について説明を行った。
準天頂衛星システムサービスはシンポジウムの中で、準天頂衛星利用拡大に向けた取り組みについて、2018年までの事業計画情報や準天頂衛星システム利用者会の設立、UI仕様書の公開スケジュール、準天頂衛星システムロゴなどの発表を行った。
準天頂衛星システムは2012年度末から、国直轄の衛星システム事業と、PFI(Private Finance Initiative)としての運用等事業で構成されている。このうち後者を担うのが準天頂衛星システムサービスで、事業期間は20年間。総合システムの設計、地上システムの整備・維持管理、総合システムの運用、利用の拡大推進が事業のメインとなっている。
地上システム事業では、準天頂衛星システムサービスのもと、総合システムの設計や地上システムの整備を日本電気(NEC)と三菱電機が請け負っている。地上局については、まだ案の段階だが、主管制局を常陸太田(主局)と神戸(副局)に設置することが紹介された。
準天頂衛星システムを利用した実証実験は、準天頂衛星システムサービスとしても利用拡大の一環として行っていくとしており、2014年度から公募を開始して順次進めていく予定。
また、「準天頂衛星システム利用者会(QSUS)」の設立も発表され、同日より、同社Webサイトでの会員登録が開始された。QSUSは情報交換の場として位置づけられており、誰でも無料で参加できる。同社では、サービスや製品の提供者だけではなく、それらを利用するユーザーなど多くの人に参加して欲しいとしている。
QSUSでは会員向けイベント(直近ではUI仕様書説明会を開催予定)や最新情報の提供、実証実験への応募サポートなどを行っていく予定。準天頂衛星システムサービスUI仕様書の公開も、一般公開に先駆け、QSUS会員向けに公開するという。
準天頂衛星システムサービスUI仕様書は、4月の一部公開に向け、ドラフト公開や意見募集を行っていく予定。
 |
準天頂衛星システム ロゴ |
このほか、アプリコンテストの開催や、2013年12月に秋葉原で開催された準天頂衛星システムを利用したサービスのアイデアソン結果報告、準天頂衛星システムのロゴが発表された。
ロゴは準天頂衛星システム(QZSS)の「Q」や準天頂軌道の「8」をイメージしたものとなっており、準天頂衛星システム対応製品の目印などとして今後利用していくという。
 |
準天頂衛星システムサービス 村井 善幸氏 |
最後に、同社 村井 善幸氏は「2013年の設立から(1年が経ち)ようやくこのような活動が軌道に乗ってきたかなと思っています。2018年度のリアルオペレーション・実利用の開始に向けて進めていくとともに、この準天頂衛星システムの成否は、衛星がいいものかとか、地上施設がいいものかとか、そういったことだけではなく、使って頂く人にとって準天頂衛星からの信号でこのような良いことができたという成果が出てきて、それが評価されるのだと思っています。今後とも、ものづくりだけではなく、利用拡大に向けて頑張っていくつもりです」として、シンポジジムを締めくくった。