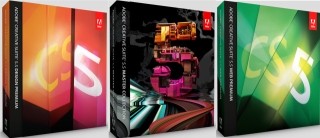アドビ システムズはこのほど、「Adobe Digital Publishing Suite 記者説明会」を開催した。「Adobe Digital Publishing Suite」は、同社が開発・運営する電子出版ソリューション。「InDesign CS5/CS5.5」で作成したレイアウトデータから、iPadやAndroid端末用の電子書籍を作成できるのが特徴だ。説明会では、電子書籍市場の現状や、同ツールで電子書籍を出版するまでのワークフロー、最新の事例などが紹介された。サービス開始は2011年7月下旬。
電子書籍市場の今後
同社のデジタルパブリッシング マネージャー 小槌健太郎氏は、MM総研のデータを元に日本の電子出版事情を解説。2009年度に574億円規模だった電子出版市場は、2015年度には3500億円市場にまで成長すると予測されている。そして、利用者数人口は2010年度が113万人だったのに対して、2015年度には1696万人にも膨れ上がる見通し。また、興味深かったのは、電子書籍のコンテンツについてだ。いま電子書籍で流通しているコンテンツは、雑誌&マンガと書籍の比率が4:6。これが、2015年度には3:7になるのではないかと予測されている。今後、現状では電子書籍化されにくい一般書籍が、数多く出版されていくのかもしれない。
小槌氏は、Adobe Digital Publishing Suiteについて「このツールの魅力は、紙媒体を制作しているワークフローに取り込めば、電子書籍の制作も平行して行なえるところ」と語る。定期刊行物を購入した場合、バックナンバーの有無を確認したり、定期購読を申し込むことも可能。読みたいと思っている雑誌を毎月検索する手間が省けるので、雑誌や書籍が好きなユーザーに歓迎されるだろう。その裏付けとして、本ツールで作られた電子書籍は、現在世界中で324媒体配信中だ。

|

|
|
本ツールの強みはバックナンバーの紹介や定期購読の申し込み受け付けなど。また、iTunes AppStoreとAndroid MarketPlaceだけでなく、その他の販売サイトでも販売可能(左)。SiteCatalystを使うと、販売冊数や人気記事の調査、広告の閲覧回数など、細かなデータを収集可能。正確な広告の効果測定は広告主からも歓迎される(右) |
|

|

|
|
本ツールを使った電子書籍の一部。世界中ではすでに324種類発売されている(左)。日本で作られた本ツールを用いた電子書籍は日々増え続けている。ナショナルジオグラフィックからも日本語版の電子書籍が発売される予定(右) |
|
複数の制作者と共同作業ができるワークフロー
続いて、同社のデザイングループ製品担当の岩本崇氏は、「InDesign CS5.5」と本ツールを使ったワークフローを紹介した。誌面データの作り方は従来の紙媒体と同じだが、電子書籍にはボタンやスライドショウなどのインタラクティブオブジェクトを組み込む作業が必要。インタラクティブオブジェクトはInDesign CS5以降に追加された「Overlay Creator」機能を使用する。
電子書籍のすべてのデータが整ったら動作確認の行程に移る。動作確認はローカルではできないため、作成した電子書籍データは一度ADPSのサーバー上にアップロードする。本ツールのベータ版のころはローカル環境でも動作確認可能だったが、正式サービスでは不可能になった。この仕様変更について岩本氏は、「動作確認のために、わざわざPCと端末(iPadなど)をケーブルで接続するのは手間がかかっていた。ですが、正式版のDigital Publishing Suiteでは、作った電子書籍データをネットからダウンロードできるようになったので、使いやすくなりました」と語った。また、ネット経由で作業するため、複数の制作者が異なる場所にいる場合でも、制作から動作確認までスムーズに行なえるというメリットも紹介された。
Digital Publishing Suiteの最低運用コストは年間60万円から
本ツールのサービス開始が2011年7月下旬に決定し、運用コストも発表された。出版社の規模によってプロフェッショナル版とエンタープライズ版の2種類が用意されるのはすでに発表済みだが、プロフェッショナル版の価格は年間60万円に決定。このなかには5000ダウンロード分のサーバー使用料も含まれている。もしも年間に5000冊以上販売したい場合は、別途追加サービス費用がかかる。ただし、これらのダウンロード数のカウントは、定期刊行物を出版したときだけ発生する。定期刊行物ではなく、電子書籍のアプリとして単体で販売する場合は、何タイトル出版しても、何冊販売しても追加料金はかからない。 そして、もうひとつのエンタープライズ版は、ビューワーのカスタマイズやAPIの開発などによってコストが大きく変わるため、価格は定められていない。