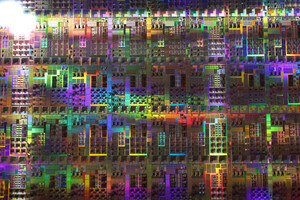電子教科書にも求められる変化
最後にジョンソン氏に、"教育環境"の一環の話しとしてコンテンツ/マテリアルとして注目され始めた「電子教科書」について訊ねた。
──電子教科書についての考えをお聞かせください。
「電子教科書」という用語は、個人的には好きではありません。それは、技術やITを使った学習のメリットをきちんと表していないからです。コンテンツのデジタル化は重要だと思いますし、教員がどのように使うのかというのも大切なテーマです。しかし、これからは今までのような教科書の使い方とは大きく異なっていくということを、それぞれの国で深く検討することが重要だと思います。
単純にPDF版の教科書を作るというのでは、導入費用はかからないかもしれませんが、総体的な学習コストとしては高くなっていくでしょう。そこからは、何よりも「デジタルコンテンツ」で学ぶ利点も強みも得ることができません。米国、イギリス、オーストラリアなどでは、すでにデジタルのコンテンツ化が進められています。
ジョンソン氏が挙げる「デジタルコンテンツ」のイメージは、以下のとおりだ。
- 生徒一人一人がPCを持ち、そこに様々なデジタルコンテンツ(学習アプリ)が入っている。生徒の作業をPCがモニタリングし、教員へフィードバックを行う。これによって、学習の評価や今後の目標設定などを加えたり修正するといった作業も可能になる
- フォーム型の教科書ではできなかった、学習のパーソナライズ化が可能となる。子どもたちが各自、のめり込み易い学習経路を辿りながら、中核となる学習コンテンツに到達することができるようになる
- インターネット接続によって、同じ教室にいなくてもコラボレーションして学習作業ができる
- これまでのコンテンツの概念とは異なったものになる。世界中のアイディアがつながることも可能になり、さらに縦型データシステムと連携させて、教育庁、教育委員会、教員、親が学習の進捗情報を把握することができる
──教科書のデジタル化を進めるにあたっての今後の課題は何でしょうか
先ほど、教師がプロジェクト型思考の手法に教え方を変えていく必要があると述べましたが、その際に、コンテンツ提供側や教科書出版側にも課題があると思っています。
先生が、教え方を変えられる支援をできるようなコンテンツを提供していかなければならない。すぐに結果が出るやり方ではなく、記述型のものに変わっていかなければなりません。
デジタルの教科書を作るというのは、書籍をPDF化することではなく、また教科書会社がシフトすべきは、PDFプロバイダーではありません。評価、コンテンツ、より専門的な知識を習得するための支援などが一つにマージされて、子どもたちの学習につながっていかなければならない。ですから、現在ある教科書制作会社は、10年後には教育と技術を融合したサービスを提供する「エデュケーショナル・テクノロジー企業」となっていくのではないかと考えています。
 |
さらに政策関連での縛りを解くことができれば、コンテンツ配信に関しても自由になり、より均一な質の教材を子どもたちに提供可能となります。パラダイムシフトを起こしていかなければならないのですが、こうした政策を決定し実行する年配の関係者たちは、コンテンツのデジタル化はPDF化することだとしか考えていないかもしれない。そこで、ハイテク企業やハイテク教育企業で、古い意識をリードするビジョンを示していくことが必要だと感じています。「コンテンツのデジタル化によって、どれだけの学習効果があるのか」といった利用モデルを作って、政策変更に反映していかなければならないと考えています。
* * *
ジョンソン氏は、こうした取り組みに対して、韓国とフィンランドがすでに良い成果を出してきており、また、その事例を積極的に学ぶ国も出てきていると述べる。インドでは、昨年6月に就任した教育大臣が素早い改革に挑み、9月には従来の試験制度を廃止、点数至上主義から理解度の向上を促す制度に変更したという。400億ドルの投資で様々な改革を行う中で、子どもたち全員がノートPCを持ち活用するオーストラリア、批判的思考や創造性にスポットが当てられ教育改革を進めている台湾なども注目する国として挙げていた。
また、米国での新しい動きとして、従来は州ごとの管轄にある基準策定や評価法制定などの作業を、リソースを共有しながら全州で協力して進めているという。
「インテルは世界中の教育機関と関係を持ち、テクノロジー企業としての重要な役割を担っていると思います。特に各国の政策決定者に対して、フォーラムやオンラインで、成功例や失敗例を安全に共有できるようにしてもらうことが重要であると考えています。『変化』は難しいことですし、一つの完璧な解答があるわけではないと考えています。もしそうであれば、教育改革はとっくに終わっているのですから」(ジョンソン氏)