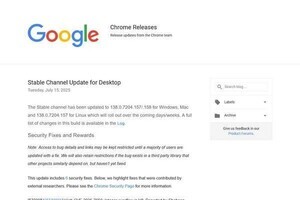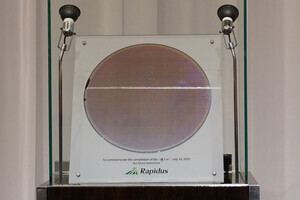富士通総研 BCM事業部長 伊藤毅氏は富士通グループ全体のBCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)の策定を担当しているということで、同グループでの事例を交えつつ講演は進められた。
同氏はまず、BCM(Business Continuity Management:事業継続管理)について説明した。BCMは、「何(重要業務)を、いつまでに(目標復旧時間)、どのようにして(復旧継続方法)」を定める事業継続戦略が核となるという。事業継続戦略は、技術的な側面を有する「事前リスク対策」と人間的な側面を有する「危機対応能力」を踏まえたものとなる。そして、この戦略・対策・対応能力の見直しと継続的改善を行っていく。
同氏は、「実際に危機が発生して初めて、わかることもある。そのため、事前の計画内容に注目しすぎると、柔軟な対応ができなくなり、正しい対応が進まないことがあるので注意していただきたい。重要なのは、実際に起きていることを正確に判断し、それに基づいて的確な対応を実施すること。そこでは人間・組織が適切に動くことが求められる。したがって、体制や役割分担を明確にするとともに、日頃から訓練を行うことが不可欠」と述べた。
BCMは大まかに「戦略策定」と「運用改善」のフェーズに分けられるが、ほとんどの日本企業は前者の戦略策定の段階にいるという。同氏は、理想的な行動計画の要点として、「5W1Hが明確でポイントが絞られた簡潔な記述になっていること」と「文書が構造化されており、メンテナンスが用意であること」を挙げた。「日本企業が策定するBCPは、あらかじめ立てた詳細な被害想定に基づいて対策や発生時の行動計画を決めることで細かくなりがちだが、有事の際は必ず予想外の被害が起きるので、それらが役に立たない可能性がある」と同氏。
次に、新型インフルエンザ向けのBCMについて説明がなされた。同氏によると、今年4月末の新型インフルエンザA(H1N1)が発生した時点で、企業が用意していた行動計画は、高病原性のH5N1、いわゆる鳥インフルエンザを想定したものだった。しかし、実際に発生した新型インフルエンザは低病原性のH1N1だったため、初めに作成された行動計画がそのまま実施されているわけではないという。例えば、フェーズ4の時点での海外駐在者の帰国指示や国内発生時の事業所内入館規制などは、当初の行動計画から大幅に緩和された内容で実施されているのが実情だ。