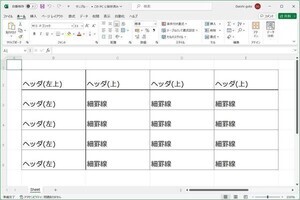6月10日、千葉県千葉市の幕張メッセにて「Interop Tokyo 2009」がスタートした。日本開催16回目となる今回は、「IMC (Interop Media Convergence) Tokyo 2009」「DSJ (Digital Sinage Japan) 2009」「RSA Conference Japan 2009」の3つのイベントも併催。不況の影響により展示ブース数は全盛時の1/4となったが、それでも336社/926小間のブースが設けられ、会場を賑わせた。
本稿では、Interop Tokyo 2009の基調講演として行われた日本アイ・ビー・エム 代表取締役社長 橋本孝之氏による『Smater Planet ~新しい可能性を未来の原動力に~』の模様をお伝えしよう。
フラット化の弊害
「ご存知のとおり、現在の環境問題は深刻な状態にある。このままでは"地球丸"という大きな船が壊れ、生きていくのが難しくなる」――橋本氏は講演の冒頭、このように話し、現状を憂いた。
「世界のスモール化/フラット化」といった現象は、企業にも消費者にも多くのメリットをもたらしてきた。しかし、その一方で、「金融同時危機」「気候変動」「限りある天然資源の争奪」「サプライ・チェーンの複雑化」「テロリズム、サイバーテロ」といった問題も引き起こしており、これらの解決が喫緊の課題となっている。
こうした現状に触れた橋本氏は、その問題解消の1つの手がかりとして「無駄を省くこと」を挙げた。例えば、日本では渋滞で、のべ38億時間がロスしており、これを賃金に換算すると12兆円にも上るという。実にGDPの2%に相当する額だ。また、米国では在庫切れによる小売業の機会損失が9.3兆円に達するほか、日本人の食料9000万トンのうち約21%が廃棄されているなど、"非効率"に該当する事象はさまざまな分野で存在するという。
交通量25%削減! ストックホルムの渋滞解消策
以上のように、あちこちに散在する"非効率"解消のキーワードとしてIBMが今年度から打ち出しているコンセプトが「Smarter Planet」である。これは、先進のICT技術を活用して、効率的な"賢い"惑星を作り上げることで、環境を改善していこうという取り組みで、昨今のコンピュータの高性能化や、RFIDの普及などを考えると決して難しいことではないという。
すでに象徴的な事例もいくつか存在している。例えば、スウェーデンのストックホルムで実施した通行料課金システム。朝の通勤車両渋滞に悩まされていた同市は、市への入り口となるポイントにETCゲートを設置して、朝の通勤時間帯に限り通行料を課金する制度を2006年に試した。その結果、交通量は25%減少。公共交通機関を利用する人が1日あたり4万人も増え、CO2排出量も14%削減されたという。IBMでは、同国で培ったノウハウを国内にも展開できないかと検討中だ。
そのほかにも、水、電気、ガスなどの利用メーターをシステムと連携させ、Web経由で確認できるようにする「スマートメーター」や、住所変更などの事務処理を1つの金融機関に対して行っただけで関連する口座の情報も自動的に置き換わる「スマートな金融機関」なども紹介された。特に金融機関のシステムに関しては、過去2度にわたり大規模な作り替えをしてきた経緯があるが、SOAをベースに柔軟にサービス連携/再編が可能なアーキテクチャを採用することで、既存資産を活用するかたちでシステムを拡張できることを強調。「第4次オンラインシステムは必要ない」(橋本氏)と説明した。
その後、橋本氏は、Smarter Planetにおける目下のキー技術として、「SOA」に加えて、非構造データのOLTP処理と蓄積された構造化データのデータマイニング処理を組み合わせた「ストリーミング処理」や、プライベート/パブリック双方における「クラウドコンピューティング」などを列挙し、これらが特に販売促進活動やシステム開発における環境構築などに有効であることを具体例とともに示した。
そして、橋本氏は、講演の最後に、20世紀前半に活躍した経済学者ジョセフ・シュンペーター(Joseph Schumpeter)氏のものとして、「技術開発の母は不況である」という言葉を紹介。「この不況をチャンスととらえ、前向きに取り組んでほしい」と述べ、講演を締めくくった。