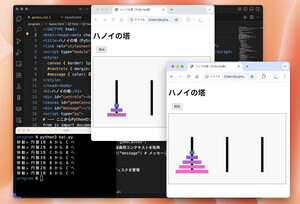広島市は7月1日から、携帯電話やインターネットカフェのPCに対し、青少年の利用が見込まれる場合、有害サイト閲覧制限のためのフィルタリングを義務付ける条例を施行する。出会い系サイトやネットいじめによる被害が相次ぐ中、「青少年と電子メディアとの健全な関係作りを目指す」(同市)としている。
広島市では、2000年から青少年問題協議会を設け、インターネットなどの電子メディアと青少年との関係について議論し、啓発活動などさまざまな取り組みを行ってきた。
2005年には、長時間のネット依存や出会い系サイトを通じて犯罪に巻き込まれるなど、児童・生徒のネット利用に関する問題が深刻化してきたのを受け、こうした問題に対処する条例の制定を訴えた提言を発表。この提言を受けた形で今年3月、「青少年と電子メディアとの健全な関係づくりに関する条例」が制定された。
同条例では、携帯電話販売店やネットカフェ事業者に対し、携帯電話やインターネットカフェのPCを18歳未満の青少年が利用することが見込まれる場合、フィルタリング機能を備えた上で販売や貸与、利用提供を行うことを義務化。また、家庭のPCについては、未成年の使用が見込まれる場合は、フィルタリング機能をPCに備えるよう販売事業者が推奨することを義務化している。
だが、インターネットカフェに関しては、18歳以上の利用者も多く、全てのPCにフィルタリング機能を付加することは難しい。この点について、同条例を所管する広島市教育委員会 青少年育成部 育成課 主幹の烏田順子氏は、「インターネットカフェの事業者から、青少年専用のブースを設けるなどの提案を受けており、そうした方向で対処してもらうことを考えている。ネットカフェのPCの全てにフィルタリング機能を付加する必要はない」と話している。
また、フィルタリングをかける際の有害サイトの基準に関しては、保護者代表や学識経験者、法律専門化、青少年の発達過程に詳しい医師などをメンバーとした審議会を今月末までに設置、基準づくりを行うとしている。
事業者が同条例に違反した場合は、勧告や指導、立ち入り検査を行い、それでも従わない場合は、事業者の代表者氏名や所在地などを公表する。
烏田氏によれば、条例でフィルタリングを義務付けたのは、ネットカフェのPCに対し義務付けを行った鳥取県に次いで2例目。広島市の条例について同氏は、「青少年とインターネットの関係においては、有害サイトの問題だけでなく、長時間のメディア利用などさまざまな問題がある。今回の条例では、よりよく電子メディアを利用していくための取り組みを行えるよう定めており、保護者、事業者などが一体となって取り組んでいきたい」と話している。