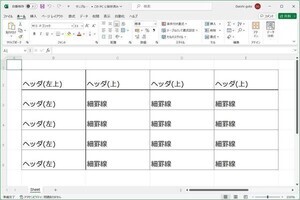米Googleは10月9日(現地時間)、自律的に走行する自動車、いわゆるロボットカーの技術開発を公式ブログで報告した。公道を使用した試験走行を、すでに140,000マイル(約225,000キロ)以上も行っているという。
公式ブログで自律走行車プロジェクトを説明しているのはGoogleのDistinguished Software EngineerであるSebastian Thrun氏だ。スタンフォード大学のコンピュータサイエンス学部の教授であり、同大のStanford Artificial Intelligence Laboratory (SAIL)のディレクターも務める。2005年に米国で行われた無人ロボット自動車レース「DARPA Grand Challenge」の第2回大会において、同氏が率いるスタンフォード・レーシングチームの「Stanley」が初の完走優勝を果たした。Googleのプロジェクトには、Stanleyのソフトウエア責任者で2007年に市街地を舞台にした無人ロボットカーレースを制したCMUチームのChris Urmson氏、自律走行型のオートバイでDARPA Grand Challengeに参加したAnthony Levandowski氏など、DARPA Challengeで活躍したエンジニアが集結している。
Googleのロボットカーの試験走行車は、カメラ、レーダーセンサー、レーザーレンジファインダーを用いて周りの障害物や道路などを把握し、詳細なマップ(人が運転する車で最新データを事前に収集)と照らし合わせてナビゲーションを決定している。ロボットカーが収集した大量のデータをGoogleのデータセンターで処理することで、すばやいマッピングが実現する。試験走行では、同社のマウンテンビュー本社からサンタモニカ・オフィス(大半が高速道路)、サンフランシスコ市内からゴールデンゲートブリッジ越え(信号や歩行者の多い市街地と、混雑する橋)、パシフィックコーストハイウエイを走行(海沿いの曲がりくねった道路)など、様々な種類の道路を走破してきたという。プロジェクトでは安全が最優先されており、ロボットカーはボタン1つで手動運転に切り替わるように設計されている。試験走行では常に熟練したドライバーが運転席に乗り、またソフトウエアの状態をモニターするソフトウエア技術者が助手席に同乗する。
自律走行車技術の開発は「テクノロジを用いて大きな問題を解決する」というGoogleの理念に従ったプロジェクトの1つだという。この場合の大きな問題とは「交通事故と交通渋滞」だ。World Health Organizationによると、交通事故で毎年120万人以上が亡くなっている。「われわれの技術は、この数字をおそらく半分程度にまで削減できる可能性を備える」とThrun氏。また今日のカーシェアリングの形を変え、車の利用を大幅に減らし、「ハイウエイ列車」のような新たな交通手段を生み出すと指摘。道路を利用してより多くの人が効率的に移動できるようになれば、エネルギー消費の削減と共に、より多くの時間を生産性に割り当てられるとしている。