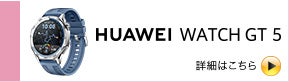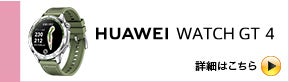HUAWEI から新たなスマートウオッチ「HUAWEI WATCH FIT 4 Pro」が発売された。デザインが洗練され、より使いやすく、より多彩に機能が進化するなかで、登山を安全・快適に楽しむための専門的な機能も充実しているとのこと。その実力をたしかめるべく、「HUAWEI WATCH FIT 4 Pro」を身につけて、東京・奥多摩の三頭山へと向かった。初夏を迎えたこの季節、木々には新緑が芽吹き、山全体が淡い緑色に光り輝いていた。
-

今回の登山で使用したのは汗を書いても快適な加工が施されたナイロンベルトのグリーンモデル。ブラックモデルは特殊なウェーブ構造で手首にフィットするフルオロエラストマーベルトを採用
「HUAWEI WATCH FIT 4 Pro」の詳細はこちら
三頭山は東京都の西端、山梨との県境に位置している標高1,531mの山。山頂から東側の一帯は「檜原都民の森」として整備され、森林館やレストランなどの施設も充実しているため、休日には多くのハイカーでにぎわう人気の山域だ。登山口の標高は1,000m。5月中旬となり、街ではTシャツで過ごせるような暑さの日もあるが、山はまだまだ涼しい。
-

檜原都民の森の入り口。登山もここからスタート
-

高度計測モード。地図上での登山口の標高は1,000mで、誤差はほぼない
「HUAWEI WATCH FIT 4 Pro」を腕に装着し、まず感じたのは着け心地の圧倒的な軽快さだ。約9.3 mmという本体の薄さはスマートウオッチとしては業界最薄で、重量はわずか約30.4g 。バンドには通気性の良い立体的なナイロンベルト(編み込みベルト)を採用している。手首にフィットして、大げさではなく、着けているのを忘れるぐらいだ。
素材にもこだわっており、屋外の厳しい環境での使用を想定した構造になっている。登山で使うことを考えれば、頑丈さや傷がつきにくいことは機能に匹敵する重要な要素である。「HUAWEI WATCH FIT 4 Pro」の画面部分には、サファイヤガラスを使用。ボディには航空機にも採用されているアルミニウム合金、ベゼルにはチタン合金を採用している。
-

本体の薄さは約9.3mm! ナイロンベルトは立体的な構造で装着感は快適
登り始める前に、今回の登山のルートを表示させる。ルートはYAMAPなどの登山地図アプリで設定し、HUAWEIヘルスケアアプリを経由して「HUAWEI WATCH FIT 4 Pro」に転送しておけば、登山中はスマートウオッチ上でルートの確認などができるようになる。道迷い防止に有効な機能だ。また、登山やトレイルランニング向けの新機能として「等高線入りのフルカラーマップ機能」が追加されている。オフラインでマップを利用するには、事前にHUAWEIヘルスケアアプリで使用したいエリアのマップをダウンロードして、スマートウオッチと同期させておく必要がある。山中でスマートウオッチの機能を最大限に活用するためにも、こうした事前設定は確実に行っておきたい。
登山口からしばらくは舗装された道が続き、森林館の先で登山道へと入る。鞘口峠までは標高差100mの登りだ。登り始めはまだ元気なこともあり、ついスピードを上げてしまう。ふとスマートウオッチを見ると、運動強度を示すメーターが「極限」まで上昇している。このペースではどう考えても体力が持たないだろう。いったん立ち止まって呼吸を整え、強度を「有酸素」まで落として、以後は歩くペースを上げすぎないように注意して登っていく。
鞘口峠からは尾根沿いの道を登っていく。ブナやカエデの新緑が美しく、野鳥たちのさえずりがあちらこちらから聞こえてくる。
ときどきマップを見て、自分の現在地がルートから外れていないことを確認する。
「HUAWEI WATCH FIT 4 Pro」は、5種の衛星システム(GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou、QZSS)に対応するヒマワリ型アンテナを搭載しているため、位置測定はかなり精確だ。マップは本体側面のリューズで簡単に拡大・縮小できるので、見やすいサイズに調整しておくといいだろう。
マップ関連の機能としてはほかに、ルートが大きく屈曲する地点を音声と文字で事前に知らせてくれるナビゲーション機能や、現在地がルートから大きく(100m前後)外れたときに音声と文字で知らせてくれる道迷い防止機能などが搭載されている。
三頭山は東峰、中央峰、西峰の3つの山頂で構成されている。東峰には展望台があり、周辺の山々の眺望が楽しめたほか、ヤマツツジが鮮やかな朱赤色の花を咲かせていた。
西峰は台地状の広々とした山頂で、ここで遅めの昼ごはんを食べることにした。
落ち着いたところで、試しに「血中酸素レベル」を測定してみた。血中酸素レベルとは血液中に含まれる酸素の量を示す値で、登山では身体への高度(低酸素)の影響を判断する指標となる。三頭山の標高は1,500m台なので、血中酸素レベルは99%と街とまったく変わらない値を示したが、富士山や日本アルプスなど標高2,500~3,000mを超える山を登る場合には高山病を予防するために血中酸素レベルの測定は有効な機能となるはずだ。ちなみに、登山ワークアウト中も常に計測しているので、画面をスライドすればすぐに数値が確認できるのも便利なポイントといえる。
なお、「HUAWEI WATCH FIT 4 Pro」では心電図や皮膚温度など、より高度な測定機能も搭載している。
山頂からは、往路を引き返すのではなく、南側に延びる尾根を下っていく。10分ほど下ると、登山道は登りへと変わる。「下っているのに、なぜ登りに!?」「もしかして道を間違えた?」と一瞬思ったが、マップの等高線を見るとルートは標高差50mほどの登りとなっている。
等高線を見ることで、ルートの登り・下りや大まかな地形の形状が把握できるので、登山用のマップにはやはり等高線は必須だ。下りの分岐では、間違った道に入り込んでしまう可能性が高い。必ず立ち止まって、目の前の登山道が延びている方向と、「HUAWEI WATCH FIT 4 Pro」のマップ上のルートを比較・確認し、正しいルートから外れないように注意して下っていく。
山頂から1時間30分ほどで「檜原都民の森」の入り口に下山する。ワークアウトを終了すると、行動時間、消費カロリー、平均速度などの行動データは自動的に計算されて、スマートウオッチとHUAWEIヘルスケアアプリに記録される。行動記録は、その日の行程を振り返り、次の計画を立てるときの参考にもなるので、こうして自動的に記録が蓄積していく機能も便利だ。
スマートウオッチというと、バッテリーの持続時間も気になるところだ。今回の登山では撮影のためにさまざまな機能を頻繁に使ったが、それでも1日で25%ほどしか減っていなかった。登山のワークアウトモードを起動しながらGPSを連続使用しても、約18時間バッテリーが持続する。なお、通常の使用であれば最大10日間はバッテリーが持続するそうなので、山中で何泊もする縦走登山でも安心して使うことができるだろう。
なお今回試したように、登山に役立つ機能が満載な「HUAWEI WATCH FIT 4 Pro」だが、ほかにも日本の99%以上のゴルフ場に対応するゴルフナビ、水深40mまでのフリーダイビング、トレイルランニング、スキーなど多彩なワークアウトに対応した機能を搭載している。ヘルスケア機能も充実し、睡眠の質をモニタリングしたり、ユニークな「情緒測定」機能も備えている。
ちなみに現在、HUAWEIのフラッグシップモデルとして「HUAWEI WATCH GT 5 Pro」が発売されているが、機能面を見ると「HUAWEI WATCH GT 5 Pro」と「HUAWEI WATCH FIT 4 Pro」はほぼ同等だという。また、よりカジュアルに使えるFITシリーズのスタンダードモデルとして「HUAWEI WATCH FIT 4」も発売中だ。好みのデザインや使いたい機能・価格帯に合わせて、セレクトするのをおすすめする。
***
登山を安全・快適に楽しむには、確実なルート維持や自分の体力に合ったペース配分などが欠かせない。高性能スマートウオッチを使いこなせば、登るルートや現在地、時間、高度、方位、気圧変化、心拍数、運動強度、血中酸素レベルなど、あらゆる情報を手首の端末で把握できる。「HUAWEI WATCH FIT 4 Pro」が、登山の心強い相棒となってくれることは間違いないだろう。
「HUAWEI WATCH FIT 4 Pro」の詳細はこちら
[PR]提供:ファーウェイ・ジャパン