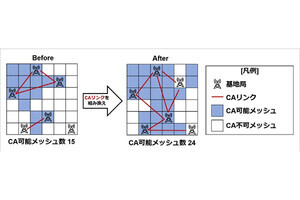2018年3月23日、名古屋のミッドランドスクエア マイナビルームにて「企業間競争に勝ち残るビッグデータ活用術」と題するセミナーが開催された。製造業におけるIoT、ビッグデータ、AIなどの活用について、第一線で取り組む有力企業各社が、さまざまな導入事例を交えながら解説を行った。本稿では、同セミナープログラムの中から、「最新のIoTデータも使いこなそう! ビジネスに“効く”データの利活用術」と題してインフォテリア株式会社 ASTERIA事業本部 マーケティング部 部長・垂見智真 氏が行った講演の内容をレポートする。
IoTデータ活用は「現状把握」から「分析」へと進化
講演冒頭に垂見氏が紹介した総務省の調査資料「ビッグデータ時代における情報量の計測に係る調査研究」(平成27年)によれば、日本国内における総データ量は2005~2014年の10年間で9.3倍、IoTデータは同期間中に10.8倍に増加したとされており、この10年前後でデータ量が爆発的に増加してきたことが伺われる。さらに今後のデータ量の推移については、全世界の合計データ量が2011年の1.8ゼタバイト(ZB)から2020年には40ZBまで増加。M2Mデバイスのネットワーク接続は2015~2020年の5年間で4.7倍増加して、30億個のM2Mデバイスが接続されるようになると予測されている。
国内企業のIT投資の意向もこうしたデータ量の増加に呼応して高まっており、IoT/M2M導入の可能性は非常に高くなっているが、その一方で企業のデータ利活用状況に目を向けると、「データの収集・蓄積」や「現状把握」といったレベルでのデータ利用は進んでいるものの、「データ分析による予測」や「業務効率の向上」「付加価値の拡大」といった一歩進んだレベルでの利用まではまだ対応できていない企業が多いことが、総務省「IoT時代におけるICT産業の構造分析とICTによる経済成長への多面的貢献の検証に関する調査研究」(平成28年)といった資料などから浮き彫りになってきている。
「現状把握」あるいは「見える化」とは、企業活動の中で「何が起こったか」をデータから分かるようにすることであり、企業におけるデータ活用の第一歩であるといえる。これをもう一歩進めて、単なる「見える化」ではない「分析」レベルでデータを活用できるようになると、データから得られる知見をもとに「なぜそれが起こったか」が分かり、「これから何が起こるか」を予測して、「次に何をすべきか」というアクションを決定することができるようになる。これからのビジネスでは、このような成熟度の高いデータ活用とそれを可能にするシステム構築が課題となってくると考えられる。
IoTシステム成功のカギは「データハブ」
ビジネスにおけるIoTデータの活用には大きく分けて「制御・自動化」と「分析・活用」という2種類の利用方法があると垂見氏は整理する。
このうち、制御・自動化の部分は、センサなどを使って収集したデータをリアルタイムに利用する仕組みである。生データを常時監視することで、プログラム起動のトリガーとなる信号を検知・感知し、そこから実際に命令実行して機器の動作制御を行うことによって業務自動化を進めるというプロセスである。
もうひとつの分析・活用の部分は、蓄積した生データを解析・分析して業務改善やビジネス改革に役立てるということであり、これまで見えていなかった問題をデータから可視化して価値創造につなげるプロセスである。このとき重要なのは、生データを整型して解析しやすいように整える準備作業であるとする。
こうしたIoTデータ活用システムを実際に導入する際のポイントとして、垂見氏は次の3点を挙げている。
(1)「既存業務は既存システムをできるだけ変えない」ということである。IoTを活用するために、既存の業務・システムに手を入れて、システムをイチから作り直すような進め方は、抵抗が多く上手く進まないことが多いためである。
(2)「現場からの変更要望に迅速に対応できる」こと。現場からはさまざまな形の要望が上がってくるので、それらに迅速に対応していくことによって実際に使ってもらえるシステムになっていく。
(3)「提供する分析レポートに柔軟性をもたせる」ということを挙げている。分析レポートは専門家だけでなく、現場の人間が使えるものを選択する必要がある。
「こうしたポイントを踏まえてシステムを構築していくにあたっては、スピードとアジリティ(柔軟さ)が重要になります。また、出所も形式も異なるさまざまな種類のデータを連携させることになるので、システムの中でデータの整型を行って扱いやすくまとめたり、複数のシステムを疎結合したりするためのデータハブ的な存在が重要です。このハブさえしっかりしていればIoTは上手くいく」(垂見氏)
また、IoT導入事例が増えるにつれて分かってきたこととして、「勝手にデータを取られているようで気持ちが悪い」と感じる人が多くなっているという問題があるという。このような状況ではシステム利用が上手く進まないので、データ収集側だけでなくデータ提供側にもメリットがあるような近江商人的「三方良し」のデータ活用・分析のあり方を追求していくことが大切とも指摘していた。
信頼性の高いデータハブ機能を提供する「ASTERIA WARP」
実際のIoT活用ソリューションでは、上述したように出所も形式も違うさまざまなデータを組み合わせて利用するため、システム連携しやすい形にデータ変換処理を行うことになる。このとき形式の異なるさまざまなデータを滑らかにつないで利用するためのデータハブの存在が重要になる。このようなハブ機能をもつツールとして、同社が提供している製品がデータ連携ミドルウェア「ASTERIA WARP」であるという。
連携させるデータとしては、社内データベースに蓄積している情報、外部オープンデータ(例えば気象庁が公開している気象データなど)、センサモジュールから得られるIoTデータなどがある。特に、最近になってよく利用されているデータとして、「API・フロー型の外部IoTデータ」があると垂見氏は指摘する。
API・フロー型外部IoTデータの一例としては、スマートフォンのWi-Fi機能がオンのときに発信しているビーコン情報がある。空間内の3か所に無線アンテナを置いてスマートフォンからのビーコン情報を取得すると、三角測量の原理によってその空間のどこに何人くらいの人がいるかという情報をリアルタイムで把握できる。こうしたタイプのデータにも「ASTERIA WARP」を使ったデータ連携で対応できるようになっている。
「建物の何階に何人くらい人がいたかというデータ、当日の売上げ、天候、花粉、周辺の渋滞情報など、さまざまなデータをいろいろなところから拾ってきて、それらをつないで利用することがASTERIA WARPを使えば簡単にできるようになっています。こうした仕組みを業界ではEAI(Enterprise Application Integration)と呼んだりしていますが、ASTERIA WARPはおかげさまでEAIツールとしては11年連続でシェア1位を頂戴し、6500社以上の導入実績のあるツールということで安心してご利用いただいています」(垂見氏)
「ASTERIA WARP」の大きな特徴は、プログラミング言語を扱えるソフトウェア開発者でなくても、アイコンを並べていくフロー作成操作によって業務設計・システム設計・開発を行うことができる「ノン・プログラミング環境」を備えていることである。これによってシステムの構築期間を大幅に短縮でき、業務に携わる人自身が日々の業務を自動化・効率化することができるようになっているという。
「ASTERIA WARP」を使ったシステムで使用するサーバについては、Microsoft Azure や Amazon AWS といったクラウドサーバ上で処理することもできるし、現場に設置したサーバを使うこともできる。サーバの運用形態は特に問わないので、目的に応じたシステムを構築すればよい。
もうひとつの特徴は、システムに拡張性をもたせるための「アダプター」が標準で豊富に用意されている点である。アダプターを使うことで、当初の要件として挙がっていなかった連携先についても、多くの場合対応可能になるとしている。アダプターの具体例として垂見氏は、Googleカレンダー、Googleドライブ、GoogleコンタクトなどGoogleが提供している各種のウェブアプリケーションに接続するための「G Suite アダプター」を紹介していた。
たとえば、同アダプターで拡張した「ASTERIA WARP」を用いてミーティングルームの人感センサのデータをGoogleカレンダー上でのスケジュール管理と連携させたソリューションでは、ミーティングルームが予約済みの時間帯であっても、実際のセンサ情報から使用されていないことが確認できた場合にはGoogleカレンダー上の予約状況の表示を自動的に書き換えて、他の人がミーティングルームを利用できるようにするといったことが可能になっているという。
同社製品を利用したIoTソリューションの具体例については、東京・大井町の同社本社に設置された「IoT Future Lab.」にて実際のシステムに触れながら検証できるようになっている。同ラボではすでに50種類を超えるデバイスが設置されており、デバイスは今後も倍増の予定。さらに同ラボは、システム検証だけでなく、ビジネス協業まで視野に入れたIoT協創の場として位置づけられている。
また、同社が運営する「ASTERIA WARP 製品ブログ/つないでみた」でも、同社製品を使った具体的なソリューション事例をブログ記事として豊富に紹介している。
「ASTERIA WARP」についての詳細はこちら
[PR]提供:インフォテリア