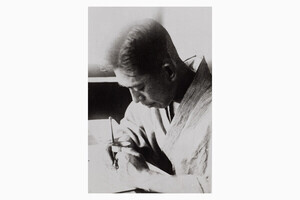フォントを語る上で避けては通れない「写研」と「モリサワ」。両社の共同開発により、写研書体のOpenTypeフォント化が進められています。リリース開始の2024年が、邦文写植機発明100周年にあたることを背景として、写研の創業者・石井茂吉とモリサワの創業者・森澤信夫が歩んできた歴史を、フォントやデザインに造詣の深い雪朱里さんが紐解いていきます。(編集部)
文字の形を変える
ルビ植字装置の開発とおなじころ、茂吉はもうひとつ、写真植字機を大きく特徴づける開発をおこなっていた。アタッチメントを機械につけることによって文字の形を変える「変形レンズ」である。カマボコ型のレンズで、これをもちいると通常の正体 (せいたい) の文字盤から、縦に細長い「長体 (ちょうたい) 」、横に平たい「平体 (へいたい) 」、斜めになった「斜体 (しゃたい) 」の変形文字を印字することができた。
活版印刷の活字は物理的な鉛のかたまりなので、もしも同じことをやろうとすればそのつど、長方形、扁平、斜体に変形した活字母型を使用サイズと同サイズで必要な文字数分だけつくり、鋳造しなくてはならない。レンズを変えるだけで文字盤ひとつからさまざまに文字を変形できるのは、写真植字だからこそ実現したことである。
ヒントとなったのは、計算尺についていたカーソルのレンズだった。計算尺とは、対数の原理を利用した計算道具だ。奇しくもほぼ同じ時期にふたりから、茂吉に提案が寄せられた。
ひとりは海軍水路部の写真植字機オペレーターとして潮汐表などの印字をしていた柘植寿治だ。ある日、仕事中に計算尺のカーソルがはずれてしまい、それが印刷物のうえに落ちた。よく見ると、文字が変形して見えるではないか。そこでこれを写真植字にも利用できないか? とかんがえたという。もうひとりは満州・興亜印刷局の関真である。関もやはり、計算尺用カーソルのレンズで文字が変形して見えることに気がつき、茂吉にアイデアを寄せた。
茂吉は、彼らからのヒントをもとに研究をはじめた。写真植字機の暗箱の構造を変更し、あらたに設計したカマボコ状の変形レンズをレンズターレットの上部に装填できるようにした。同時に、同じ装置で拡大レンズの装填も可能にした。
変形レンズの具体的な開発時期は、はっきりしていない。しかしこれをもちいた最初の印刷物が、1935年 (昭和10) 9月につくられている。志茂太郎主宰のアオイ書房による愛書誌『書窓』第1巻第6号である。とすればおそらく変形レンズの開発時期は、1933年 (昭和8) 以降1935年 (昭和10) 以前とかんがえられる。[注1]
詩集への採用
この画期的な変形レンズは、『書窓』に続き、同1935年 (昭和10) 11月に千代田書院から刊行された『西條八十詩謡全集 第2巻 抒情詩篇 前』に使用された。じつはこの全集が、変形レンズ開発の具体的な動機となった。
〈この研究は西條全集を印字するようになって急にやったことです。私の印字部の方に出入りしている飯田覚之助君 (東京高等工芸出身) が、全集の装釘家の河野鷹思氏と親友の関係から、いろいろ考案してくれまして、詩集とあるからには豪華な印刷にしてみたい。それには趣向の変った印字を採用したいというので、各巻字体別というようなことになりました。その結果長体をやってみようというのでアタッチメントを工夫したのです。お蔭で出版元にも著者にも大変気に入られました。も一つ、アオイ書房から出る恩地孝四郎氏の詩文集 (筆者注:『季節標』[注2]) にもこの明朝長体を用いました。此種の出版物には最も適切な文字形ではないかと自負しています。――それから、これは余談ですが、植字機の方も満州で成績がよいので、近く其処に採用されることになるかもしれません (後略) 〉[注3]
茂吉は『印刷雑誌』は同1935年 (昭和10) 12月号の取材に対し、変形レンズ開発の経緯をこんなふうに説明している。話の結びには、満州でも変形レンズが採用されそうだと言い、その後は現在取り組んでいる他の研究について〈研究としては面白いものですが、これとて、商売にはなりませんよハハハ〉と上機嫌に語っている。[注4]
『西條八十詩謡全集』は、印刷においても画期的なものだった。本文は地模様の色刷りの上に、写真植字による印字が墨で刷られた2色オフセット印刷。その美しい印刷を手がけたのは共同印刷だ。もともと全6巻の予定で、最初に刊行された第2巻 (1935年11月) と1936年(昭和11) 3月に刊行された第3巻が明朝長体、1935年 (昭和10) 12月に刊行された第6巻は楷書長体となっている。[注5]

-

写真植字機の変形レンズによって本文が印字された『西条八十詩謡全集』
上:明朝長体が使用された『西条八十詩謡全集』第2巻 (抒情詩篇 前)、千代田書院、1935
国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1233480 (参照 2025-02-12)
下:楷書長体が使用された『西条八十詩謡全集』第6巻、千代田書院、1936
国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1228894 (参照 2025-02-12)
これを報じた『印刷雑誌』は〈この全集が、印字以外の点でも印刷界に一寸したトピックを与えるに十分な出版である〉〈活版印刷では一寸真似の出来ない芸当なのである〉〈この試みは果然、出版物それ自体の性質にぴったり当嵌ったとみえ、相当以上の好成績を示し〉と熱く綴っており、著者の西條八十自身がその出来ばえにひじょうな満足ぶりで、にわかに写真植字礼賛者になったという噂も伝わってきた、とも記している。[注6] みずからの研究が美しい書物として姿をあらわしはじめたのである。このころの茂吉が上機嫌に研究を語ったのもうなずける。
ひとつ残念なことは、当初全6巻で計画されていた『西條八十詩謡全集』は、6冊それぞれで書体や組み方を変えて制作される予定だったが、結局、第2巻、3巻、6巻の3冊が刊行されたのみとなってしまったことだ。[注7] しかしそれでも、この見事な書物の奥付に、著者の西條八十や装釘の河野鷹思、印刷所の共同印刷と肩を並べて写真植字機研究所と石井茂吉の名が堂々と掲載されたことは、茂吉をおおいに力づけた。[注8]
-

『西条八十詩謡全集』第2巻の奥付。写真植字機研究所と石井茂吉の名が製版担当として明記されている
『西条八十詩謡全集』第2巻 (抒情詩篇 前)、千代田書院、1935
国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1233480 (参照 2025-02-12)
(つづく)
出版社募集
本連載の書籍化に興味をお持ちいただける出版社の方がいらっしゃいましたら、メールにてご連絡ください。どうぞよろしくお願いいたします。
雪 朱里 yukiakari.contact@gmail.com
[注1] 「文字に生きる」編纂委員会 編『文字に生きる〈写研五〇年の歩み〉』写研、1975 pp.32-33
また、「簡単なレンズ附加装置一つで 写真植字機の字型が変る」『印刷雑誌』18 (12) 昭和10年12月号、印刷雑誌社、1935 p.38にも〈この長体文字は、石井氏の苦心によって、三ケ月程以前に完成された〉とあり、1935年8~9月ごろに開発されたことがうかがえる。
[注2] 恩地孝四郎『季節標』、アオイ書房、1935 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/8311658 (参照 2025-02-12)
[注3]「簡単なレンズ附加装置一つで 写真植字機の字型が変る」『印刷雑誌』18 (12) 昭和10年12月号、印刷雑誌社、1935 pp.38-39
[注4] 同上
[注5]『西条八十詩謡全集』第2巻 (抒情詩篇 前),千代田書院,昭和10. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1233480 (参照 2025-02-12)、『西条八十詩謡全集』第3巻,千代田書院,昭10至11. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1228878 (参照 2025-02-12)、『西条八十詩謡全集』第6巻,千代田書院,昭10至11. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1228894 (参照 2025-02-12)
[注6]「簡単なレンズ附加装置一つで 写真植字機の字型が変る」『印刷雑誌』18 (12) 昭和10年12月号、印刷雑誌社、1935 pp.38-39
[注7]「文字に生きる」編纂委員会 編『文字に生きる〈写研五〇年の歩み〉』写研、1975 pp.32-37
[注8] 本稿は、「文字に生きる」編纂委員会 編『文字に生きる〈写研五〇年の歩み〉』写研、1975 pp.32-37、「簡単なレンズ附加装置一つで 写真植字機の字型が変る」『印刷雑誌』18 (12) 昭和10年12月号、印刷雑誌社、1935 pp.38-39をもとに執筆した
【おもな参考文献】
「文字に生きる」編纂委員会 編『文字に生きる〈写研五〇年の歩み〉』写研、1975
「簡単なレンズ附加装置一つで 写真植字機の字型が変る」『印刷雑誌』18 (12) 昭和10年12月号、印刷雑誌社、1935
【資料協力】株式会社写研、株式会社モリサワ
※特記のない写真は筆者撮影