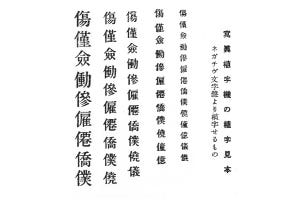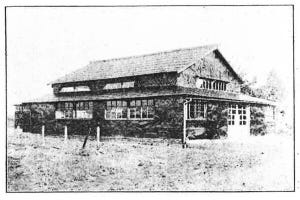フォントを語る上で避けては通れない「写研」と「モリサワ」。両社の共同開発により、写研書体のOpenTypeフォント化が進められています。リリース予定の2024年が、邦文写植機発明100周年にあたることを背景として、写研の創業者・石井茂吉とモリサワの創業者・森澤信夫が歩んできた歴史を、フォントやデザインに造詣の深い雪朱里さんが紐解いていきます。(編集部)
茂吉の茶目っ気
レンズの研究をはじめてからというもの、茂吉は毎晩2時、3時まで計算に没頭する日々だった。しかしそんな茂吉も、根を詰めているばかりではない。時おり気分転換をしたり、茶目っ気を見せたりすることがあった。
机に向かいつづけて疲れると、茂吉は柴田をつかまえては雑談をした。話題は科学や文学、宗教、人生など多岐にわたった。柴田は〈 いつも先生の明快な論旨や鋭い推理、独創的な考え方に魅了されるのが常 〉だった。[注1]
真夏のある日、茂吉は柴田に小説の話をしていた。そこに、茂吉の25歳下の末弟・秀之助がたずねてきた。秀之助は当時、中学生だった。すると茂吉は、柴田と秀之助に漢字の読み方競争をさせた。
「杉村楚人冠」
と書いて見せ、ふたりにその読みを聞いた。
秀之助は「スギムラ ソジンカン」と答え、柴田は「スギムラ ボンジンカン」と読んだ。
それを聞いた茂吉はほほえみながら「ボンジンカンではソジンカンがかわいそうだよ」と柴田に教えてから、「腹が痛くてどうにもならない!」と子どものように大笑いをした。その無邪気な笑顔は、柴田の心もあたためた。
また別の日には、柴田の机のうえにいつのまにかデボーの幾何学が置いてあった。[注2] 高価な書籍で、図書館に行くと柴田がときどき手にとっては読んでいたものだった。うれしくなって柴田がすぐさま茂吉のところにお礼を言いに行くと、茂吉はなにも言わず、ただにこにこと笑っているのだった。
〈 先生はいつもわたしが解析学のほうばかり読んでいるのを見て、幾何学がどんなにたいせつであるか、また学科に好き嫌いがあってはならないということを無言のうちに教えてくださったものだと、強い感銘を受けると同時に、その後は幾何学はたいそう好きになりました 〉[注3]
柴田はふりかえってそんなふうに語っている。夢中になると根を詰めがちな茂吉だが、そんななかでもひとときの息抜きがあったこと、誤りの許されない緊張感のある作業を進めるなかでも、助手とあたたかな関係を築いていたことが伝わってくる。
1928年 ( 昭和3 ) のはじめごろ、茂吉はついに計算を終えた。石井方式で計算をはじめて1年半が経っていた。当初3年から4年はかかると言われていた計算を、そのわずか半分の期間で成し遂げたのだ。
レンズの試作を依頼
写真植字機用レンズ6種類の計算をやり終えた茂吉は、計算結果にかんたんな小論を添え、最初にレンズについて相談をした日本光学工業のレンズ設計部長、砂山のもとをたずねた。
「レンズの試作をお願いしたいのです」
訪問から1週間ほど経つと、砂山から手紙が届いた。茂吉のレンズ設計計算方式のすばらしさを高く評価したもので、論文にまとめて大学に提出すれば理学博士の学位取得はまちがいないと書かれていた。その道の専門家に認められることは、自分の計算方式の正しさが証明されたことでもある。茂吉はおおいに喜んだ。あとでわかったことだが、谷方式でも茂吉方式でも、導かれる答えはおなじであった。
茂吉は、多忙をきわめていた。砂山は学位論文の提出をすすめてくれたが、写真植字機の実用化のためには、現在直面しているレンズの問題を解決し、その後、文字盤にも取り組まなくてはならない。学位論文を執筆する時間はなかった。
砂山に依頼したレンズの試作は、ちょうど1年後、1929年 ( 昭和4 ) の春に完成した。しらせを受け、茂吉は日本光学工業にかけつけた。てのひらの上にのせられた6個のレンズは、茂吉にとってダイヤモンド以上に貴重なものだった。総額750円。当時、工員の月給が35円で、750円は一戸建ての家が買えるほどの金額だった。なにより、レンズを改良しなくてはと茂吉が着手しはじめてから、約3年の月日が過ぎていた。その研究の成果が、ようやく形となったのだ。[注4]
写真レンズの征服
やっとのおもいで手にしたレンズだったが、いざ写真植字機に装着してみると、結果はよくなかった。像が鮮明に結ばず、おおきさも正確ではなかった。材料のガラスにも問題があるのかもしれないし、加工もていねいではなかった。茂吉は、またもや壁に突き当たってしまった。
どうにも方策がない。そんな局面にあたると、茂吉はいつも自分の手でやろうと決意する。レンズの材料としてドイツ製のイエナガラスを銀座の服部時計店で買い求めた。また、レンズ研磨のための装置である研磨皿も、自分でつくった。加工自体は、東京・西巣鴨にある旭光学工業 ( 現・ペンタックス ) に依頼した。会社の規模が大きすぎないほうが、今回のような小さな仕事にもていねいに取り組んでくれるだろうというのが理由だった。 旭光学工業は、梶原熊雄が1919年 ( 大正8 ) に創立した会社で、当初は掛眼鏡や双眼鏡レンズの製造をおこなっていた ( 同社が国産カメラレンズの設計を初めて完成させるのは1931年のこと )。梶原は、茂吉から見てもひじょうに研究心の強いひとだった。[注5] 彼は茂吉のむずかしい注文にこころよく協力し、日本光学工業よりもずっと安い価格で引き受けてくれた。これでどうにかやっと、レンズの見通しがついた。
取り憑かれたようにレンズの研究に没頭する茂吉の姿をいちばん身近で見ていた助手の柴田は、茂吉を〈 独創力と何事もやりとげねばおかない強い精神力の持ち主 〉と言った。[注6] その精神力が、どんな専門家に相談しても「素人に写真レンズなんか絶対にできるものか」[注7] と言われたレンズを完成させたのだった。
約30年後、いつも謙虚な茂吉が当時開発したレンズについて「今みてもそんなにおかしいレンズではないですか」とたずねられ、こんなことを語っている。
〈 レンズそのものはお粗末なものですが、写植機用としたらば結構シャープな像が出ます。写真レンズとしてはずいぶんお粗末なものではあるけれど、ともかく写真レンズの征服ということはね、日本で私が始めて ( ママ ) なんです。といってもいいと思うんです。当時は ( 筆者注:写真用の ) レンズを作っている会社はありませんでした。〉[注8]
「写真レンズの征服」という、茂吉らしからぬ強い言葉で語るほどに、彼にとってレンズの開発はおおきな成果だったのである。
(つづく)
[注1] 柴田久三「石井先生」『追想 石井茂吉』写真植字機研究所 石井茂吉追想録編集委員会、1965 p.93
[注2] デボーヴ『平面幾何学研究法』冨山房、1914 のことか?
→デボーヴ 著 ほか『平面幾何学研究法』、富山房、大正3 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/952192 ( 参照 2023年10月29 )
〈デボーの幾何学〉の記述は柴田久三「石井先生」『追想 石井茂吉』写真植字機研究所 石井茂吉追想録編集委員会、1965 p.94 より。
[注3] 柴田久三「石井先生」『追想 石井茂吉』写真植字機研究所 石井茂吉追想録編集委員会、1965 p.94
[注4] 『石井茂吉と写真植字機』写真植字機研究所 石井茂吉伝記編纂委員会、1969 p.98
[注5] 旭光学工業については、ペンタックスウェブサイト「COURSE OF HISTORY」https://www.ricoh-imaging.co.jp/japan/pentax/pentaxhistory/course/ ( 2023年10月29日参照 ) を参考にした。また、梶原熊雄が〈 非常に研究心の強い人 〉という茂吉のコメントは、橘弘一郎による石井茂吉へのインタビュー「対談第9回 書体設計に菊池寛賞 株/写真植字機研究所 石井茂吉氏に聞く」『印刷界』1961年10月号、日本印刷新聞社 p.95 を参照した。
[注6] 柴田久三「石井先生」『追想 石井茂吉』写真植字機研究所 石井茂吉追想録編集委員会、1965 p.92
[注7] 「発明」編集室編「本邦印刷界に大革命を招来する 『写真印字機』の発明者 石井茂吉君に聴く」『発明』1933年12月号、帝国発明協会 p.68
[注8] 橘弘一郎による石井茂吉へのインタビュー「対談第9回 書体設計に菊池寛賞 株/写真植字機研究所 石井茂吉氏に聞く」『印刷界』1961年10月号、日本印刷新聞社 p.95
【おもな参考文献】
『石井茂吉と写真植字機』写真植字機研究所 石井茂吉伝記編纂委員会、1969
「文字に生きる」編纂委員会 編『文字に生きる〈写研五〇年の歩み〉』写研、1975
『追想 石井茂吉』写真植字機研究所 石井茂吉追想録編集委員会、1965
森沢信夫『写真植字機とともに三十八年』モリサワ写真植字機製作所、1960
馬渡力 編『写真植字機五十年』モリサワ、1974
沢田玩治『写植に生きる 森澤信夫』モリサワ、2000
「邦文写真植字機遂に完成」『印刷雑誌』大正15年11月号、印刷雑誌社、1926
「発明者の幸福 石井茂吉氏語る」『印刷』1948年2月号、印刷学会出版部
「発明」編集室編「本邦印刷界に大革命を招来する 『写真印字機』の発明者 石井茂吉君に聴く」『発明』1933年12月号、帝国発明協会
橘弘一郎「対談第9回 書体設計に菊池寛賞 株/写真植字機研究所 石井茂吉氏に聞く」『印刷界』1961年10月号、日本印刷新聞社
【資料協力】株式会社写研、株式会社モリサワ
※特記のない写真は筆者撮影