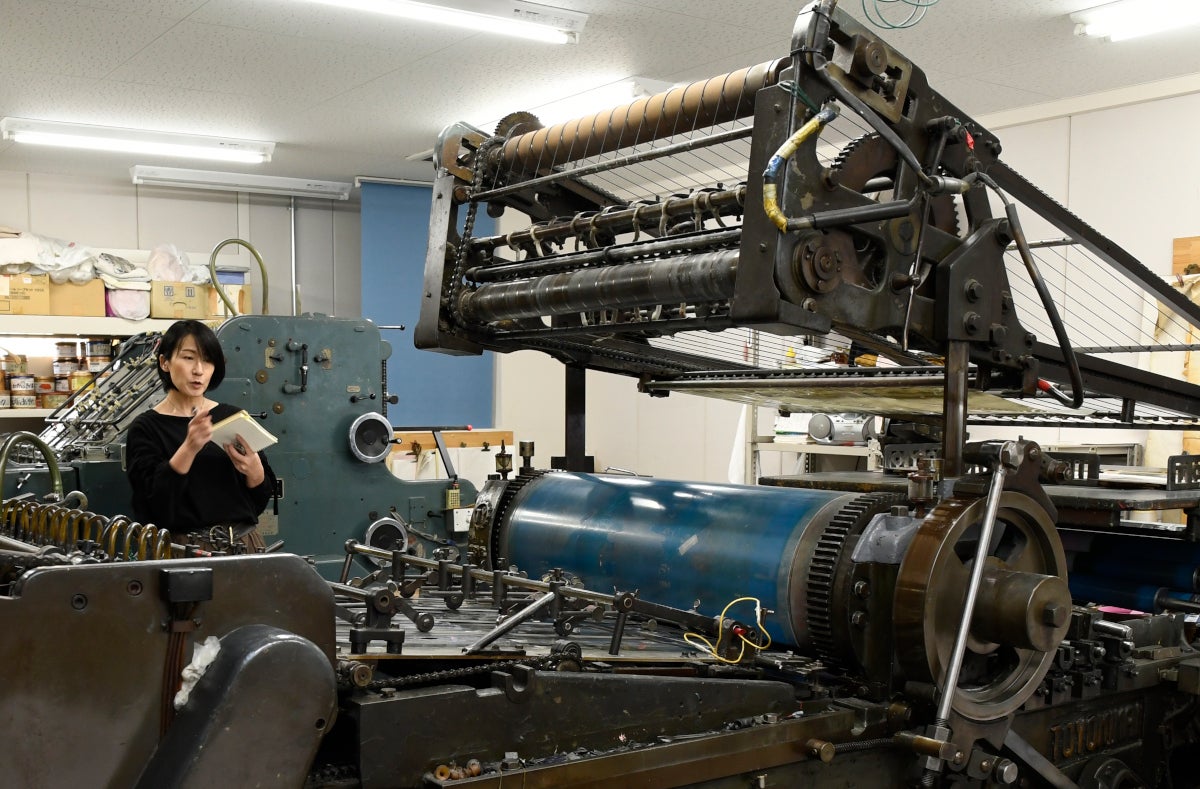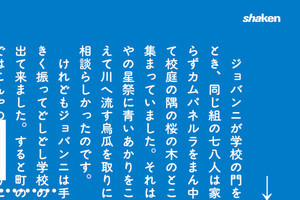フォントを語る上で避けては通れない「写研」と「モリサワ」。両社の共同開発により、写研書体のOpenTypeフォント化が進められています。リリース予定の2024年が、邦文写植機発明100周年にあたることを背景として、写研の創業者・石井茂吉とモリサワの創業者・森澤信夫が歩んできた歴史を、フォントやデザインに造詣の深い雪朱里さんが紐解いていきます。(編集部)
最初の「邦文写真植字機」
1924年 (大正13) 7月24日、わが国初の写真植字機の特許が、森澤信夫と石井茂吉によって出願された。来たる「邦文写真植字機発明100周年」が来年 (2024年) と設定されているのは、ここが起点となっているからである。[注1]
このとき出願され、1925年 (大正14) 6月23日に公示された特許第64453号「写真装置」に記載された機械は、基本的なしくみはできているものの、のちにふたりが発表する実用機とはかなりかけ離れた素朴なものだった。
はたして最初の「邦文写真植字機」構想は、どのようなものだったのだろうか。
特許の目的は〈従来の印刷方法の如き活字の製造、文撰、及植字作業の如き極めて煩雑なる諸工程を全々除去し即ち活字を使用する事なく印刷作業を為し時間及経費の激減を得せしめ時代の要求に適応したる印刷作業をなしめんとするにあり〉。[注2] 星製薬の印刷部で活字の煩雑さにさんざん苦しめられ、なんとかしてもっと合理的に作業が進められないかと悩んだ、信夫の切なる願いに聞こえる。
特許明細書に掲載された図面は3点。第1図が正面図、第2図が側面図、第3図が摺動子の正面図である。「摺動」とは「しゅうどう」または「しょうどう」と読み、機械の装置などをすべらせながら動かすこと。[注3] 「スライドする」と言い換えるとわかりやすいだろうか。
こまかな説明は難解かつ長くなるので、興味のある向きは特許明細書の原文 (特許情報プラットフォーム) にあたってほしい。
本機は、左右に長く、前後 (奥行き) のせまい台 (1) ( 第1図内の青丸数字を参照。以下同 ) に置かれている。この台の上には井桁状の枠があり、上にのっている暗箱 ( 2 ) が左右にスライドできるようになっている。さらに暗箱の上部 ( 3 ) は前後にも動くようになっている。
( 2 ) の暗箱のなかにはフィルム胴がおさめられており、中央に中空管 ( 4 ) が立てられている。暗箱の底には長方形口があけられていて、中空管はここを貫通して下に突き出ている。中空管の上端は、暗箱のなかのフィルム胴の直下に開口しており、下端は (1) の台に近接して開口していて、なかにレンズとシャッター ( 5 ) がおさめられている。
( 6 ) は文字板である。文字板とは、「光を透過できるようにした数多くの文字を配列したもの」とある。つまり、ガラス全面を黒くし、文字部分だけが光を通すように透明になった、いわゆる「文字のネガ板」だ。これが (1) の台に水平にセットされている。この文字板は、交換可能である ( つまり、それによって書体や字種を変えることができる )。
図面には明示されていないが、本文を読むと、 ( 6 ) の文字板の下には光源が置かれる。暗箱中央の中空管を前後左右にスライドさせることにより、目的の文字に中空管の下端の位置を合わせ、下から光を当てることでフィルムに文字を撮影する。そしてボタンを押すとフィルム胴が1字分だけ回転し、また次の文字に中空管の位置を合わせて撮影していく。
こうして文章を撮影し終わったら、フィルムを取り出して現像する。特許明細書では、「フィルムを現像したあと、これをじかに亜鉛板に焼き付けて、印刷用亜鉛板を製作する」としている。
「印刷用亜鉛板」とは、活版印刷で用いられる「亜鉛凸版」のことだろう。つまり信夫は、この段階ではあくまでも、印刷方法自体は活版印刷を想定していたものとおもわれる。
フィルム(のちには印画紙にも)に直接印字できる写真植字機は本来、やはりフィルムを介して印刷用の版をつくるオフセット印刷 [注4] と相性がよい。20世紀初頭にアメリカで生まれたオフセット印刷は、精巧な画像が印刷でき多色刷りに適していることから欧米に広がった。
日本では1910年代 (大正初期) にオフセット印刷が導入されたものの、信夫と茂吉が邦文写真植字機の特許を出願した時期にはまだ少なく、中心となっているのは活版印刷だった。[注5] だから、信夫が邦文写真植字機を、あくまでも亜鉛凸版をつくるための方法と考えたのも自然なことだ。
この当時、オフセット印刷で文字を刷ろうとおもえば、まずふつうの活版印刷と同様に活字を組んで版をつくり、活版印刷機できれいに印刷をした「清刷り」[注6] を写真製版してフィルムにし、さらにそれを金属版に焼き付けてようやく印刷版をつくることができた。オフセット印刷をするのに、まずは活字を組んで印刷する工程が必要だったのである。だからこそ〈これを何等かの方法で活字を使わないで、文字の種板をつくることが出来たならば如何に便利であろうということは大分前から考えられていた〉(『実業之日本』1925年12月号 p.130 )。[注7]
つまり、オフセット印刷を使わずとも、「活字を使わずに文字が組める」こと自体が画期的な出来事だったのだ。
ちなみに、馬渡力 編『写真植字機五十年』(モリサワ、1974) では暗箱のなかに〈フィルムなり印画紙なりを収めた〉と書かれているが [注8] 、特許明細書には「印画紙」という言葉は登場せず、この時点ではあくまでも「フィルム」に撮影するものとして書かれている。
文字盤を改良したはずが
1924年 (大正13) 7月24日に茂吉や彼の紹介してくれた弁理士・馬場頴一の助けを借りて特許 (第64453号) を出願した信夫は、わずか3カ月半後の同年11月13日に「写真装置の改良」という特許を出願している (第67702号 ) 。
最初の特許出願と並行して、模型からより実用に近づける試作機の構想を練るなかで、いまだ構想のみで実物をつくっていなかった文字盤 ( 1回目の特許出願時には「文字板」、2回目からは「文字盤」となっている) をつくろうといざ考えたときに、信夫は気づいたのだろう。前回の特許第64453号では、「文字盤は光線を透過できる数多くの文字を配列したもの」=つまり、背景が黒、文字部分を透明にしたネガ状の板としていたが、その製作は難しく、膨大な費用がかかるということに。
そこで「写真装置の改良」では、もっと簡単に文字盤がつくれる方法を考え、それにともなって機械にも変更を加えた。
まず文字盤は、「普通の活字を並べたもの」または「その印刷物 (つまり、清刷り) 」を用いる。それを撮影可能にするために、レンズとシャッターを取りつける位置を変える。暗箱のなかに中空管を通すのではなく、暗箱の側面に取り付け、内部にレンズ、シャッター、プリズムなどを収蔵する。透過板ではないので、文字盤下の光源は不要となる。
「すでにある活字や、活字を印刷した紙を文字盤とするのだから、これをつくるのは簡単だ! どうだ!」と信夫はおもったかもしれない。1回目とおなじく、特許権者 (発明者) は森澤信夫で、特許権者として石井茂吉が名を連ね、弁理士は馬場頴一。この特許第67702号は1925年 (大正14) 10月23日に公示され、1926年 (大正16) 3月6日に特許となったが、具体化されることはなかった。
それもそのはずである。
「邦文写真植字機」は活字から解放されるために発明されたはずなのに、「改良」したはずの第67702号では、文字盤をつくるのに結局「活字」または「活版印刷の刷りもの=清刷り」が必要になってしまっているのだ。それでは「写真植字機」を使う意味がない。
しかしそんな矛盾にも気づかずに「写真装置の改良」の特許を申請するほど、彼らの前に立ちはだかった「文字盤」は、当時の技術のなかで、製作の困難と多大な費用がかかることが予想される難物だったのだ。
(つづく)
[注1] 「モリサワ OpenTypeフォントの共同開発で株式会社写研と合意」 (2023年5月30日参照)
[注2] 特許第64453号「写真装置」明細書より。特許情報プラットフォーム (2023年5月30日参照)
[注3] 松村明編『スーパー大辞林3.0』(三省堂/物書堂、2008)
[注4] オフセット印刷:平版印刷の一種。水と油が反発する性質を利用して平らな金属板にインキのつく部分とつかない部分をつくる。その印刷版から一度、インキ画像をゴムブランケット面に転写し、それを紙などの被印刷物に転写して印刷する方法のこと。現在のオフセット印刷の版材は、アルミPS版が主流。
参考:日本印刷学会編『印刷事典 第5版』(印刷学会出版部、2002) p.91
[注5] 参考までに、1922年 (大正11) の調査によると、東京・大阪の主な印刷所におけるオフセット印刷機の数 (四六倍判、四六全判、四六半裁判、菊判あわせて/欧米各社・日本製あわせて) は、東京が合計102台、大阪が合計63台。関東大震災後である1926年 (大正15) 時点での東京のオフセット印刷機の数は、合計122台となっている。
矢野道也「日本に於けるオフセット印刷」『印刷雑誌』大正15年11月号 (印刷雑誌社、1926) pp.4-6
[注6] 清刷り:きよずり。活字組版をオフセット印刷など、他の版式で使用する版下として用いるために、活字組版の原版から活版印刷機で鮮明に刷った印刷物のこと。これを写真製版して、オフセット印刷の版に用いた。
参考:日本印刷学会編『印刷事典 第5版』(印刷学会出版部、2002) p.153
[注7] 杜川生「印刷界の一大革命 活字無しで印刷出来る機械の発明」『実業之日本』大正14年12月号 (実業之日本社、1925) p.130
[注8] 馬渡力 編『写真植字機五十年』(モリサワ、1974) p.94
【おもな参考文献】
『石井茂吉と写真植字機』(写真植字機研究所 石井茂吉伝記編纂委員会、1969)
森沢信夫『写真植字機とともに三十八年』モリサワ写真植字機製作所、1960
馬渡力 編『写真植字機五十年』モリサワ、1974
産業研究所編「世界に羽打く日本の写植機 森澤信夫」『わが青春時代(1) 』産業研究所、1968
日刊工業新聞編集局『男の軌跡 第五集』にっかん書房、1987
杜川生「印刷界の一大革命 活字無しで印刷出来る機械の発明」『実業之日本』大正14年12月号、実業之日本社、1925
橘弘一郎「対談第9回 書体設計に菊池寛賞 写真植字機研究所 石井茂吉氏に聞く」『印刷界』1961年10月号 (日本印刷新聞社)
倭草生「恩賜金御下賜の栄誉を担った 写真植字機の大発明完成す ―石井、森澤両氏の八年間の発明苦心物語―」『実業之日本』1931年10月号、実業之日本社、1931
日本印刷学会編『印刷事典 第5版』印刷学会出版部、2002
矢野道也「日本に於けるオフセット印刷」『印刷雑誌』大正15年11月号、印刷雑誌社、1926
松村明編『スーパー大辞林3.0』三省堂/物書堂、2008
特許情報プラットフォーム
【資料協力】
株式会社写研、株式会社モリサワ
※特記のない写真は筆者撮影