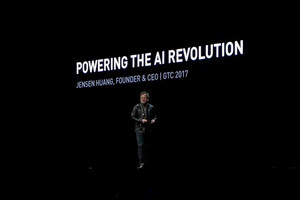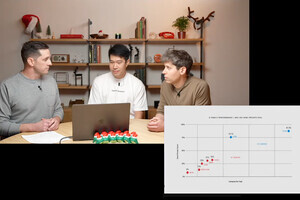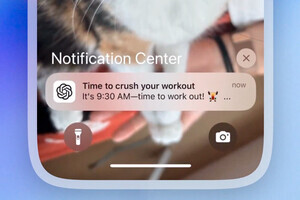最初に取り組むのはソフトバンクグループ用のAIの開発
このSB OpenAI Japanが最初に取り組むのが、ソフトバンクグループ用のクリスタル・インテリジェンスの開発ということになる。
孫氏によれば、ソフトバンクグループでは現在、約2,500の業務システムが稼働しているという。これらは30年前から順次開発されて運用されており、開発当時の担当者がすでに退職していることも珍しくないが、クリスタル・インテリジェンスがすべてのソースコードを読み、何を意味しているのか、どういう機能を持っているかを読み取り、最新の言語に置き換えたり、どこをバージョンアップしたらよいのかといった点まで判断できるようにすることを目指す。
また、社内で開催されるすべての会議、顧客との折衝の際にもクリスタル・インテリジェンスが参加するようになる。コールセンター対応も同様だという。すべての資料、社員の業務用メール、仕様書や設計書といったものもすべて読み込んだうえでクリスタル・インテリジェンスが会議などの場に参加することで、長期記憶を活用しながらの業務運用が可能になるという。
この“長期記憶”は、この日のプレゼンテーションで孫氏が強調したキーワード。同氏は2015年~2016年にかけて長期記憶とその強化学習について複数の特許を取得しているのだという。この日のプレゼンテーションではその特許の内容は具体的には語られず、クリスタル・インテリジェンスの有用性・優位性につながるものかどうかはわからないが、孫氏が以前からこの方面に関心を持っていたことは間違いないようだ。
なお、孫氏が語る「長期記憶」のイメージは、「企業内で担当者が退職してしまったり文書が埋もれてしまったりしてもAIはそれを記憶し続け、必要なタイミングで取り出して提示することができる」といったもののよう。前述のクリスタル・インテリジェンスの活用場面でいえば、過去の会議で議論された事項をすべて把握しているエージェントが会議や交渉の席に同席できるようになるということで、確かにそれが実現できれば企業活動においては有利に働くように思える。
また、ソフトバンクグループでは現在、携帯のユーザーが4,000万人ほど、PayPayのユーザーが7,000万人ほど、LINEではでいりーのアクティブユーザーが9,000万人いるという。このユーザーベースの統合作業、企業内の人事や報酬体系の統一などによって大きな負担が生じているが、クリスタル・インテリジェンスがグループ企業間を横断して活動することで、IDやシステムの統合といった負担が必要なくなると想定している。
これだけのシステムだけあって、開発・運用の費用は大きなものになる。ソフトバンクグループがクリスタル・インテリジェンスの開発・運用として支払うのは4,500億円/30億ドルという規模になる。
この契約により、OpenAIに対する資金面の不安や設備投資過剰という懸念は払拭されるのではないかと孫氏はいう。ソフトバンク1社で4,500億円、ソフトバンクグループと同規模の会社が100社、それぞれにカスタマイズされたクリスタル・インテリジェンスの開発を発注するとすれば、45兆円の売上となり、システム費用などのもろもろを勘案しても十分に利益が出るのでは……というわけだ。
SB OpenAI Japanでは、この企業向けのインテグレーションなどを担うセールス&エンジニアとして、1,000名体制の専任部隊を作るという。このほか、OpenAIからのエンジニアも参加する。
またデータセンターなどのインフラはStargateの延長として日本国内に用意される。クリスタル・インテリジェンスの基本的な開発は米国で行われるが、トレーニング/ファインチューニングのためのインフラは日本におかれ、ソフトバンクグループが設定し、OpenAIが中心になった運用を行うことになるという。
クリスタル・インテリジェンスの展開は、まずは1業種1社を想定して進めるという。そのうえで、あるていどノウハウがたまればその縛りをなくすことも考えているようだが、同業の複数の競合企業にクリスタル・インテリジェンスが導入されるとしても、学習内容や知識の再利用はされないため、機密が漏洩するなどの心配は不要とのことだ。