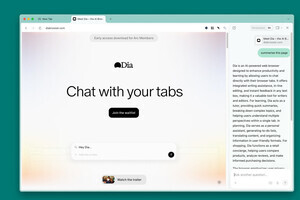スタッフの雇用難が続く飲食店、人手不足による黒字倒産も増加
USENが音楽配信依存からの脱却を図っている。同社は「お店の未来を創造する [店舗総合サービスのNo.1プレイヤーへ]」というビジョンを掲げ、飲食店の開業支援やPOSレジの提供、損害保険販売、電力、ガスの小売りなど幅広いサービスを展開。2018年10月30日には、飲食店向けのセルフオーダーシステム「U-Order」をリリースした。
U-Orderは、テーブルなどに設置するタブレットタイプのセルフオーダーシステムだ。来店客が自らタブレットで注文をするため、店員は注文と用件伺いの手間を省くことができる。現在(2018年11月27日 取材時点)は、食べ放題と飲み放題を対象としているが、順次アラカルトメニューにも対応していくという。
メリットはPOSレジなどと接続する必要のない「独立タイプ」である点。レジと連動していないと不便なのでは? と思うかもしれないが、既存のレジ環境に依存しないため、導入の障壁が低いのだという。
USEN 代表取締役社長の田村公正氏は、U-Orderが生まれた背景について次のように話す。
「最近、飲食店では、日本人だけでなく中国人をはじめとする外国人スタッフの雇用も難しくなってきています。我々も、お客さまから人手不足を解消したいというご相談をいただくことが増えました。音楽配信事業を中心に、さまざまなお店と50年向き合ってきた当社としても、お客様の力になりたいと考え、省人化を実現するU-Orderの開発を決めました」
売り手市場なのは、何も新卒採用だけではない。今はアルバイトの雇用すら困難を極める時代なのだ。優秀な人材は、国籍問わず引く手あまた。そのうえ、ようやく採用できたかと思ったら、すぐに仕事を辞めてしまうケースも少なくないという。
「日本語をまだ完璧にマスターしていない外国人スタッフが接客をすると、お客さまとのミスコミュニケーションが起きることがありますよね。例えば、“タンタンメン”と“タンメン”を聞き間違えてしまったり。そうなると、クレームにつながることも少なくありません。クレーム自体は会社側が処理すればいい話なのですが、問題はせっかく採用した外国人スタッフが辞めてしまうことです」
同社がセルフオーダーシステムを開発した背景には、店舗の作業効率化だけではなく、外国人スタッフを“守る”という目的もあったのだ。母国語の通じない環境で仕事をするのは、簡単なことではない。責任を感じてしまうのか、向いていないと思ってしまうのか、コミュニケーションがうまくいかないことによって、辞めてしまう外国人スタッフも少なくないそう。
「来店された方が自分で注文を入力するので、聞き間違えのようなミスコミュニケーションも減るでしょう。単純な省人化だけでなく、従業員を守るツールとしても、課題解決の一助になればいいですね」
慢性的な人手不足が続いた結果、最近では「黒字倒産」に陥る店舗も増えてきているそうだ。そんな現状を少しでも変えるべく、田村氏はU-Orderの効果に期待を寄せる。
50年以上の営業経験が店舗総合支援への扉を開く
店舗の悩みを解決すべく、セルフオーダーシステムを開発したUSEN。しかし、USENといえば、店舗向けに音楽を配信する事業のイメージが強い。いつから音楽以外の事業に力を入れるようになったのだろうか。
「私が社長に就任した2013年ごろから徐々にシフトしているイメージですが、頭のなかでは10年以上前から考えていました。その背景にあるのは、音楽市場を取り巻く環境の変化。今の若い世代には『お金をかけて音楽を聴く』という文化をなかなか理解できない人も多いのではないでしょうか。USENは著作権の問題がクリアになっているので店舗BGMにはぴったりだと思いますが、今後その世代の人たちが独立して自分のお店を開いたとき、コストを払ってまで店舗でBGMを流すことにはシビアになるはずです。そこで、音楽ビジネスを柱にしながらも、第2、第3の柱をどうやって作っていこうか考えるなかで、開業からお客様の店舗の一生涯に寄り添うという戦略にシフトしていこうと決めました」
1998年に6000億円近くあったCDの生産金額は、今や1500億円程度。インターネットの普及によって無料で音楽が聴けるようになった現代では、BGMに対してコストを支払うという考えが生まれにくいのかもしれない。
そのような環境のなかで、次の柱として「店舗総合支援」を選んだ理由を、田村氏に聞いてみた。
「我々には、50年以上、店舗のお客さまとお付き合いしてきた経験に基づく情報とリソースがあります。例えば、USENをご契約くださっているお客様が閉店する際、解約のご連絡があるのですが、それによって私たちは未来のテナント情報が手に入るのです」
店をやむなく閉めるときには、それまで契約していたUSENも解約する。その連絡を受けることで、USENはどこよりも早く、将来の「空きテナント情報」を知ることができるというわけだ。そして、その情報をもとに、これから開業を考えているオーナーとのマッチングを行うことも可能だという。

「立地や内装がよければ、そのまま“居ぬき”でほかの経営者に売却することができます。テナントで入っているお店は、内装をすべて原状回復してから出ていかないといけないのですが、工事のコストは数百万円することも少なくありません。買い手が見つかれば、冷蔵庫やキッチンなどの設備も売れる可能性があるので、次のビジネスを始めるときの手元資金にできるのです」
将来の空きテナント情報は、買い手だけにメリットがあるものではなく、売り手としてもメリットがあるのだ。さらに、店舗総合支援に役立つのは、情報だけではない。
「USENには1000人の営業と750人のエンジニアがおり、北海道から沖縄まで、全国150拠点で活動しています。我々は“ヒトインフラ”と呼んでいるのですが、何かあった際にお客様の店舗へすぐに駆け付ける体制がしっかりと構築できているのです。他社でこれほどのネットワークを持っている会社はないのではないでしょうか」
店舗営業でヒトインフラを構築してきたUSENには、情報が集まるだけでなく、全国の店舗とのネットワークがある。従来の事業によって、店舗総合支援の土台はできあがっていたといえるだろう。
担当者単位で見れば、従来の仕事を進めるなかで、顧客の課題解決を行い、すでに総合的なサポートを実践していた社員もいるかもしれない。しかし、それを会社の大きなビジョンとして描くことで、全社的に店舗総合支援へと舵を切ることになったのだ。
業務の自動化が進むなかで求められるバランス
店舗総合支援の事業を進めるUSEN。田村氏は今後の店舗のあるべき姿について、どのように考えているのだろうか。
「最近は、無人店舗やキャッシュレス決済が登場するなど、テクノロジーの進化が目立ちます。コンビニなどは利便性の高さが大事なので、オートメーション化の流れはますます加速していくと思いますが、飲食店のなかには“人のぬくもり”を必要とする店舗もあるはず。そのような店舗では、オートメーション化と人が介在するサービスのバランスが大事になっていくのではないでしょうか」
「自動化」と「人の手」、どちらかに寄り過ぎても成功できるとは限らない。サッと食べるだけのファストフードであれば無人化してもいいだろうが、比較的長い時間滞在する居酒屋などの場合は今後も人間が介在するだろう。とはいえ、人手不足の問題を解消するためには、ある程度の機械化、自動化は避けられないはずだ。これからは、2つのバランスが魅力的な店舗を作るのだと田村氏は考える。
「もちろん、大将と女将さんが2人で切り盛りしているカウンターの小料理屋に、タブレットの注文システムは不要です。ただ、そのようなお店でも奥に接待用の個室がある場合、来店客はわざわざ女将さんを大きな声で呼ばなければなりません。呼び出しベルの場合もありますが、一度要件を伺いに行く手間が発生します。そのようなシーンでは、タブレットのオーダーシステムがあっても違和感はないでしょう。自動化と人のぬくもりのバランスを見極めながら、今回リリースしたU-Orderをはじめ、我々の開発したシステムを必要に応じて導入してほしいですね」
U-NEXTとUSENが経営統合して「USEN-NEXT GROUP」が生まれたのが2017年の12月1日。2018年にはライバル会社だったキャンシステムをホールディングスの傘下に迎え、USENは今まさに大きな転換期を迎えている。
音楽配信のUSENから店舗支援のUSENへ。音楽配信事業で培った店舗営業の経験を、開業支援や経営サポートの面で活かしながら、店舗の一生涯に寄り添うサービスを展開する同社は、その実現に向けて、着実に歩を進めているといえよう。
(安川幸利)