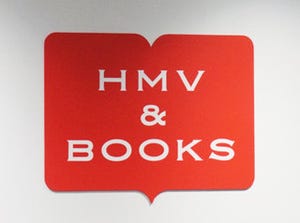コクヨのノートはデジタル化されるのか? アナログの意味とは
デジタル化への取り組みについてはどうか。コクヨはこの流れにまったく乗っていない、というわけではない。コクヨでは2014年にARアプリ「カザスマート」を使い、キャンパスノートの表紙をアプリで映すことで動画や画像を再生させるキャンペーンを行なったり、ノートをデータ化して取り込んでクラウドにアップロードできる「CamiApp」アプリをリリースしている。
しかし、現段階ではキャンパスブランドのアプリケーション化をはじめとした、デジタル化への取り組みは行っていない。
上田グループリーダーは「お客様のニーズがあれば、きちんとウォッチしていきたい」と前置きしつつ、「書く」ということの重要性を説く。「確かにデジタルで便利になっている部分ってあると思いますが、デジタルだけですべてが完結するわけではありません。書くと何らかの形で覚えているんです。"あそこに書いたな"とか、何らかの印象が残っているというのが実は非常に大事だと思っています」。
書くことが記憶につながる。コクヨではキャンパスノートについて「Smart&Positive」というテーマを掲げており、キャンパスノートのカタログには「書きたくなるノートが思考をより深くする。Smartなノートが、人をよりPositiveにする。」とあり、ノートをただ書くためだけのツールとしてとらえていない。
キャンパスノートの人気は、40年続いたブランドとしての知名度はもちろん、デザイン、機能といった顧客のニーズを製品に反映し、「書きたくなるSmartなノート」を目指した幅広い商品開発を行なっている点にあるだろう。それはユーザーの視点からすると、キャンパスノートなら自分の目的にあった書きやすいノートがあるはず、という期待感につながる。
製品を使う意味を把握した上で、ユーザーのニーズをとらえてどう製品化するのかというコクヨにおける商品開発のあり方。それは、文房具市場はもちろん製造業から見ても注目すべき点は多いかもしれない。