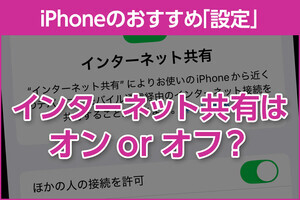日本での研究開発
日本では1999年からインターネット接続が可能な携帯電話が普及してきた。2000年代には、世界各国のモバイル技術に関わる企業が東京に研究開発拠点を置いてきた。iPhone登場時までは特異なほどにモバイルが進化し普及した国として位置づけられていたからだ。
もちろん技術的な背景も大きい。良質な通信インフラやビジネスモデル、パソコンから利用するインターネットよりも急速な発展など、モバイルが伸びる土壌も整っていた。加えて、持つ人々が素早く生活に取り入れたことも、重要な要素だ。
高速無線通信技術を搭載した端末を多くの人が持つことによって、どんな変化が起きるか。生活はどのように変わるか。ビジネスの変化については保守的な面もあり、あまり参考にならなかったかもしれないが、それ以外の分野の研究者たちは、目を輝かせて日本を観察していた。
筆者もこうした研究に大学・大学院時代に関わることがあった。統計的に見たり、経年変化を見たりすることも重要だが、それ以上に面白かったのが、特異な現象を見つけて仮説を立て、より深く理解をするというものだった。
例えば秒単位でケータイメールやワン切りを交わす高校生の日常や、おサイフケータイと財布の使い分け、ケータイカメラの研究など、次世代のサービスや未来、日本以外の国で起きうる事象を予測する上で、こうした研究は重視されていたのだ。
AppleはiPodにしてもiPhoneにしても、日本からの学びを多く生かしているように感じている。10年後のApple製品の礎を、現在の日本の我々の生活から見つけることができるかもしれない。

|
松村太郎(まつむらたろう)
1980年生まれ・米国カリフォルニア州バークレー在住のジャーナリスト・著者。慶應義塾大学政策・メディア研究科修士課程修了。慶應義塾大学SFC研究所上席所員(訪問)、キャスタリア株式会社取締役研究責任者、ビジネス・ブレークスルー大学講師。近著に「LinkedInスタートブック」(日経BP刊)、「スマートフォン新時代」(NTT出版刊)、「ソーシャルラーニング入門」(日経BP刊)など。ウェブサイトはこちら / Twitter @taromatsumura