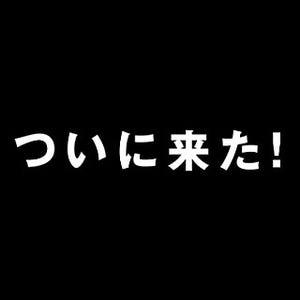NECと東北大学サイバーサイエンスセンターは18日、災害が発生するなど通信インフラが途絶した際に、エリア内に設置したWi-Fiアクセスポイントを臨時ネットワークとして活用する技術を開発したと発表した。
大規模災害時には、ネットワーク設備の損壊や通信の混雑によって、通信インフラが利用不能になり、情報伝達が困難な状況に陥るが、今回発表された技術によって、最大1,000台の公衆Wi-Fiアクセスポイントを臨時ネットワークとして活用し、広範囲にわたって利用可能な情報配信・通信サービスを実現したという。
 |
 |
屋外設置型アクセスポイント |
可搬型アクセスポイント |
NECではスイッチを切り替えることで、公衆Wi-Fiスポットから臨時ネットワークへモード変更できるアクセスポイントのほか、大規模な臨時ネットワークの構築に必要なアクセスポイント間のネットワーク経路を制御する技術を開発した。
同社が開発したアクセスポイントでは、接続した利用者の端末から送信された情報を蓄積し、ほかのアクセスポイントへ近づいた際に情報を伝達するDTN(Delay/Disruption/Disconnection-Tolerant Network)技術やソーラーパネルやリチウムイオン電池の電気を利用する機能を搭載する。
また、近接する複数のアクセスポイントを接続関係に基づいてグループ分けし、異なるグループに属するアクセスポイント群とグループ単位での経路制御を実行することで、100台程度から最大1,000台と、大規模なアクセスポイント間の通信を実現した。
このほか、東北大学サイバーサイエンスセンターでは、利用者に応じて通信の優先度を設定可能な技術を開発。EAP-TLS(Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security)認証方式を利用し、アクセスポイント内の認証サーバと、利用者の端末内にあらかじめ発行したクライアント証明書を通信して認証する。クライアント証明書に、利用者属性情報を付加することで、優先利用者と一般利用者で通信の優先度を設定できるという。