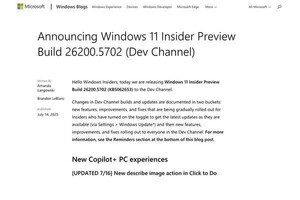前回は、Hyper-Vを採用したシステム(コード名Graviton)について、設計・計画段階での考慮点を中心に紹介した。今回はHyper-Vの実装作業やWindows Server 2008 R2へのアップグレード作業について紹介する。
執筆者紹介
横山哲也(YOKOYAMA Tetsuya) - グローバルナレッジネットワーク
1994年からITプロフェッショナル向けWindows Server教育に従事。2007年にはVirtual Server、2008年からHyper-Vの教育コースを担当している。社内システムの仮想化に関しても、技術アドバイスと一部実作業を実施した。2003年からMicrosoft MVP(Directory Services)を毎年取得。主な著書に「実践Active Directory逆引きリファレンス」(毎日コミュニケーションズ)がある。趣味は猫写真。Twitterアカウントは@yokoyamat。
データセンター
ようやく本来のサーバーが調達されたので、システムを本番環境(プロダクションシステム)に展開することになった。サーバーはデータセンターに設置された。作業は1人でも可能だが、ミスを防ぐためにHyper-Vに詳しい同僚と一緒に出かけた。IT部門の担当者も一緒である。
データセンターは寒く、風が強い。ただしIT部門の担当者によると「これだけ風が強いところは珍しい」ということだ。とにかく寒いのと空調の轟音には閉口した。
セキュリティ上の問題があるため、出入りも不自由だ。もっとも、最初に使ったデータセンターは、インターネット接続可能な休憩コーナーやトイレがセキュリティエリア内にあったので、それほど困らなかった。
その後に契約したデータセンターには、休憩コーナーは設置されていなかった。また、入館キーは事前に登録していた管理者にのみ与えられ、我々のような一時的な作業要員はマシンルームから出ることもできない。この時はIT部門の担当者は同行しなかったので、トイレに行くにもデータセンターの係員に電話しなければならない。マシンルームは寒いので、お腹が痛くなったらどうしようと心配したものである(幸い、作業中にトイレに行くことはなかった)。
ディスク構成
サーバーのセットアップで最初に行なうべき作業は、ディスクの構成である。今回はハードディスク4台構成のハードウェアRAIDを利用した。
耐障害性を重視した場合、システムディスクとデータディスクを分離した上で、ぞれぞれを冗長構成にすべきである。万一の場合の復旧作業が単純になるためだ。
性能面も考えると、システムディスクの冗長構成はミラーリング(2台の冗長構成)、仮想マシンを配置するデータディスクはRAID 1+0(4台以上の偶数台冗長構成)などが適している。
ただし、耐障害性と性能を考慮した最適構成では経済性が犠牲になる。Windowsをインストールするために必要な推奨空き領域は40GBでしかない。余裕を見ても100GB程度だろう。今回利用した各ディスクの容量は250GB程度なので、システムとデータを分離した場合、システムディスクとデータディスクを各2台で構成することなる。2台で可能な冗長構成はミラーリング(RAID 1)しかないため、250GBのミラーリング構成を2組作るしかない (図1)。これはかなり効率が悪い。
今回のプロジェクトは予算削減が最重要課題だったので、2組のミラーリングはあきらめて、ハードウェアRAIDシステムが持つ仮想ディスク機能を利用することにした。4台すべてをRAID 5で構成し、仮想的なディスク装置としてシステムディスク100GB、データディスク650GBを割り当てた(図2)。
RAID 5は書き込み性能に劣るが容量効率が高い。ミラーリングでは全体の半分の容量しか利用できないが、RAID 5では、n台構成で(n-1)台分の容量が利用できる。仮想マシンはディスクへの書き込みを頻繁に行なうため、書き込み性能に劣るRAID 5は不適切であるが、予算の都合なのでやむを得ない。