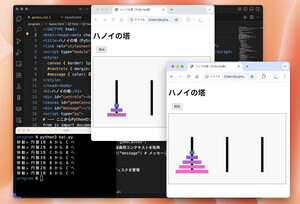企業が生き残りをかけて取り組んだはずの「データ活用」が、社内でなかなか浸透しなかったり、高い成果を生み出せなかったりするケースが少なからず見受けられる。
その要因としては、サイロ化によってデータの収集・管理が難しいことに加え、データを全社的に共有・分析して業務やビジネスに生かすという企業文化が未成熟なことも挙げられる。
こうした課題を取り除き、企業における「データの民主化」と「データ活用文化の定着」を推進していくには、どのような取り組みが効果的なのだろうか?
生き残りをかけたはずの「データ活用」が浸透していない現実
社会のあらゆる領域で急速に「デジタル化」が進む中、企業にとっては、ITシステムとデータを活用して新たな価値を生みだしていく「デジタルトランスフォーメーション」(DX)への取り組みが重要な経営課題のひとつになっている。
世界規模で進むデジタル化の波、すなわち「デジタライゼーション」のトレンドにおいては、あらゆる業種、業界のビジネスモデルが、デジタル技術の力で否応なく変化し、適応できなかった企業を市場から淘汰していく。企業がDX を進めなければならない理由は、変化の波に飲み込まれることなく、新たな市場環境で成長を続けていくためと言える。
DXを構成する要素のひとつは、ITによって蓄積された「データ」の活用から、これまで市場に存在しなかった新しい価値を創出することだと言われる。この「データ活用」の重要性は、日本企業にITが導入されはじめた1980年代以降、繰り返し強調されてきた。以降、ITがビジネスに不可欠な存在となってからは「ビジネスインテリジェンス(BI)」「データマイニング」、2000年代以降は「データドリブン経営」「ビッグデータ」といった様々なキーワードとともに、多様化と大規模化が進む「データ」から、ビジネスに貢献する知見を導きだし、経営や事業に生かす取り組みが模索されてきた。
しかしながら、こうした取り組みを実際に進め、高い成果を生み出せている企業は、まだ一部に留まっているのが現実だ。
総務省が2020年に実施した、日本企業におけるデータ活用の現状に関する調査を見ると、大企業では顧客管理や経理といった領域に加えて、POS やeコマースによる販売記録といったデータの活用も徐々に増えつつあるものの、中小規模企業においては、顧客データを活用している企業が「3割弱」、経理データについては「2割弱」、POSやeコマースの販売記録に至っては「1割未満」と、まだ十分に活用が進んでいるとは言えない状況にある。
また、大企業においても「経営」や「マーケティング」といった、特定の業務領域では、ある程度のデータ活用が行われている(3~4割)一方で、POSやeコマース、GPS、RFIDといった、IoT領域を含た、複合的なデータ活用は1割前後と、本格的な普及はこれからの段階にある。
総務省では、データ活用を進めている企業が「分析の結果をどう活用しているか」についての調査結果を「見える化」「予測」「自動化」の3領域に分類している。これらは、データ活用が進んでいない企業における「最初の目標」と捉えることもできる。企業が理想的なデータ活用を実現していく上で、その妨げとなっている要因は何なのだろうか。
企業のデータ活用とDXの加速に必要となる「データアンバサダー」
クラウド型BIプラットフォームを提供する「Domo」は、Webメディア「ZDNet Japan」(朝日インタラクティブ)と共同で、2020年に企業の「データ活用」に関するアンケート調査を行っている。この調査では、自社のデータ活用に不満を感じている企業は全体の「76%」にのぼるという結果が出た。
不満を感じる理由として最も多く挙げられたのは、データが経営や各事業部門の内部に抱え込まれてしまう「データのサイロ化」により、データの収集、管理が難しくなっていることだった。加えて、「データを全社的に共有、分析して、業務やビジネスに生かしていこう」という「企業文化」が未成熟なことも挙げられた。
こうした、データ活用にまつわる「不満の原因」を取り除き、企業における「データの民主化」と「データ活用文化の定着」を推進していく役割として注目が高まっているのが「データアンバサダー」である。
「データアンバサダー」は、企業の中で、DXを視野に入れた「データ活用」の新たなあり方を実現していく重要な役割を担う。この役割を果たすためには、そのための十分なスキルと権限が必要になるため、業務兼任のいわゆる「ボランティア」的な立場ではなく、専任の役職として擁立されることが必要である。
企業によっては既に「CDO(Chief Digital Officer)」や「CIO(Chief Information Officer)」といった名称で、データ戦略や情報戦略に対し、経営的な側面で責任を負う役職が置かれているケースもある。彼らが経営に対して責任を負うのに対し、「データアンバサダー」は、あくまでも「現場側」を向き、現場におけるベストな「データ活用」のあり方を推進していく点で役割を異にする。
同じ理由から、数理的な専門知識に基づいてデータから知見を導き出す「データアナリスト」とも異なる。「データアンバサダー」の視点は、より業務の現場に近いところにあり、「CDO」「CIO」「データアナリスト」らと連携しながら、現場での「データ活用」の姿を変革していくことが、主な仕事となる。
データアンバサダーの果たすべき「役割」
データアンバサダーは、DXの推進、データドリブンなビジネス環境の実現、データ活用に向けた企業文化の醸成に責任を持つ。その具体的な役割としては、以下のものが挙げられる。
「データの民主化」に向けた活動
企業がデータ活用を進める上で、最大の障害となっているのが、部門やシステムごとにデータが抱え込まれ、高い権限を持った一部の人にしか参照も分析も許されないという「データのサイロ化」だ。データアンバサダーの最大の役割は、サイロ化したデータを開放し、その活用を民主化することである。
ここで言う「民主化」には、部署間でのオープンなデータ連携を可能にするだけでなく、一般の従業員に対して、部署内の重要なデータや全社的な目標に関する情報へのアクセス権を与えることも含まれる。全社員が「見たいデータへ自由にアクセスできる」「自分なりの仮説に基づいてデータを分析し、結果をアクションに生かせる」環境を作っていくことが、企業のデータ活用レベルを高めるための基礎になる。
抵抗勢力との交渉
どんな組織にも「これまでのやり方を変える」ことに抵抗する勢力は存在する。特に自分たちが抱えているデータの価値と力を理解している部門や社員ほど、「データの民主化」には否定的な立場をとりがちだ。データアンバサダーには、全社的な利益を最大化する立場に立って、そうした抵抗勢力と根気強く交渉していくことが求められる。
交渉には、小規模なデータ連携とその分析結果、得られた成果を材料に「データを活用することの価値」を理解してもらうという正攻法もあれば、最終的にはトップの指示で「データの取り扱い方を変えてもらう」といった力技が必要になるケースもある。その意味でもCDO、CIOといったトップとデータアンバサダーが連携し、役割にふさわしい社内的な権限を与えられていることが必要になる。
社員のモチベーションを高め企業文化を変える
データアンバサダーは、現場の従業員が、自分たちの業務やビジネスにおいて日常的に「データ」を生かせるようにするための環境作りを行う。
多くの企業で何らかのデータの可視化、分析ツールが導入されているにもかかわらず、それらが活用されない理由のひとつは、ツールの使い方や、分析結果が自分たちの業務に対してどのような意味があるのかが十分に理解されていないことにある。「データの民主化」によって、アクセスできるデータの範囲が広がれば、その問題はさらに大きくなる。
データアンバサダーの役割のひとつは、各現場の業務とビジネス目標を理解した上で、データから、現場のエンドユーザーにとって価値のある指標を導き出し、それを常に参照できる環境を作っていくことだ。
「このデータがないと仕事が進まない」「このデータは自分のパフォーマンスを上げていく上で価値がある」と感じられる指標をいかに導きだし、プレゼンテーションするかは、データアンバサダーの腕の見せどころだ。こうした環境づくりを行うことで、現場のデータ活用に対するモチベーションは高まり、データ活用に向けた企業文化の醸成につながっていく。
データから正しい知見を得るための支援を行う
「見たいデータにアクセスできる」ようになったとしても、そのデータからユーザーが正しい知見(インサイト)を得るためには、統計やデータ解析に対する、基礎的な理解が必要だ。
例えば、数値上「相関関係」にある2つのデータが、必ずしも「因果関係」にあるとは限らない。これは、データ分析の基本だが、初心者が陥りやすいトラップでもある。データアンバサダーには、データ分析のエキスパートではない現場の社員が、データから正しい知見を得られるよう、アドバイスやトレーニングを行うことが求められる。
現場が自分たちでデータを活用できるよう支援する
データ活用のための環境を、現場の社員たちが自律的に改善、拡大していくことができるように支援するのもデータアンバサダーの役割だ。
民主化を通じてデータ活用が習慣化し、企業文化の醸成が進むと、現場から「こんな形でデータを活用できないか」「分析に新しいデータを加えることで別の知見が得られるのではないか」といったアイデアが、次々に出てくるようになる。そうしたアイデアの価値を見きわめ、見込みのあるものを育てていくためには、ある程度、現場レベルでツールの使いこなし方や、分析の方法などを理解しておくことが望ましい。現場での小規模な試行錯誤の反復が、新たな価値の源泉となる可能性もあるためだ。
データアンバサダーは、そうした環境を作っていくために、現場でのツールの使いこなし方の教育や、データ分析に対する知見の共有、必要に応じたIT 部門への働きかけなども行う。
データとツールの効率的な活用方法を社内に広げる
企業の規模が大きくなるほど、部署ごとのデータ活用のレベルや文化に、大きな開きがでてくる。ある部署では、データ活用を積極的に推進し、次々と新しいアイデアが出てくるが、他の部署では必要最低限の指標を、一部のメンバーがたまに見ているだけといった状況は起こりえる。
データアンバサダーは、もし、ある部署や社員がデータ活用に関して新しい取り組みを始めたり、そこから成果を出したりした場合には、それを会社全体に共有し、伝播させていく役割を担う。ツールの使い方やデータの活用方法のようなナレッジを共有することに加えて、「積極的なデータ活用を称える」ことによるモチベーションの向上や、社内文化醸成といった意味もある。
適切なバランスでのポリシーを策定する
データアンバサダーのすべての活動は「データの民主化」を起点として行われるが、その実現にあたっては「バランス」も不可欠だ。あまりに自由度が高すぎれば収拾がつかなくなり、不要なセキュリティリスクも生じがちになる。かといって、あまりに厳しい制限やルールを設けてしまうと、現場でのデータ活用は硬直化してしまう。
データアンバサダーは、企業とユーザーの双方の立場に立ち、どの程度の「データの民主化」が必要か、ガバナンスとセキュリティをいかにコントロールすべきかを判断し、実現をサポートする必要がある。
定期的に活動状況を把握する
「分析ツールを導入したにもかかわらずデータ活用が根付かない」という課題を抱える企業では、データ活用を「ツールを入れて終わり」の期間限定プロジェクトとして取り組んでいないかを振り返ってみるべきだろう。
ここまでに挙げてきた「データアンバサダーの役割」の多くは、期間を区切って実施されるものではなく、継続的に繰り返される必要があるものだ。データを民主化し、現場での活用方法を探り、その結果を把握して、次のステップで改善のアクションへとつなげていくことが求められている。
"データアンバサダーを、一部のデータ活用に対する意識が高い社員の「ボランティア」的な取り組みではなく、専任の役職として擁立すべきなのは、もし異動や転職などによってその社員が役割を続けられなくなっても、職務として「後任」を任命できるという理由もある。データ活用は、組織として継続しながら、そのレベルを高められるものだ。"
データアンバサダーに求められる「マインド」と「スキル」
 |
「変革」のマインドを持っている |
 |
戦略的未来志向 |
 |
コミュニケーション力 |
 |
テクノロジーよりもビジネスに明るい |
 |
説明責任能力がある |
 |
事業目標への理解 |
データアンバサダーを中心とした企業改革を進めるためのプラットフォーム
経営者や一部の役職を持つ社員だけでなく、すべての従業員がデータにアクセスし、そこからビジネスに価値のある知見を得て、迅速にアクションを起こすことができる環境を持たない企業は、今後、デジタライゼーションのうねりに飲み込まれ、急速に競争力を失っていく。データ活用の活性化を通じてDXを加速させたいと考える企業にとって、そのための環境作りを役割とする「データアンバサダー」の存在は不可欠なものだ。
2010年に米国で設立され、クラウド型のデータ活用サービスを展開する「Domo」は、データアンバサダーをリーダーとして、組織のデータ活用レベルを上げていく上で最適なプラットフォームの提供に注力している。Domoのサービスでは、データ活用を進める企業が「社内外のあらゆるデータを取り込み」「迅速に変換、分析し」「エンドユーザーがアクセスしやすい形で提示する」ための一連の仕組みを、オールインワンのクラウドサービスとして提供している。
導入にあたっては、既存のデータ活用環境を必ずしもリプレースする必要はない。既にデータ活用のためのシステムを構築している企業においては、それらをつなぎ込みながら、企業全体で統合された新たなデータ管理の基盤を構築できる。これまでのデータ活用に対する投資を無駄にせず「データの民主化」を実現できるのだ。
Domoを通じて、データドリブンな組織への変革にチャレンジし、成果を挙げている企業のひとつに、通信大手のKDDIがある。同社では、ファイナンスを担当する経営管理本部に「DX推進部」を設置している。DX推進部では、経営サポートと業務品質の向上および効率化を目的に、2017年に「Domo」を導入。「経営者から現場までをデータを通じてつなげるツール」として活用を進めてきた。活用レベルの向上にあたっては、DX推進部内に「Domo事務局」を設置し、各部門から選出された「パワーユーザー」(現場のリーダー的存在)と連携しながら、ハブ&スポーク型で浸透を図ってきたという。
社内でのハンズオントレーニングやイベントといった施策も実施し、結果としてユーザー数は3年で約28倍、Domoへのログイン回数や機能の利用状況を基に算出する独自指標の「Domo浸透スコア」も約15倍になった。現在では、経営層が日次で決算の着地予測シミュレーションをモバイルでモニタリングできるようになっているほか、事業部では各サービスの稼働状況や日次KPIのチェック、社員はコロナ禍でのテレワーク・出社状況の可視化に基づいた対面打ち合わせの効率的な実施など、データドリブンな業務環境が実現されているという。「データ活用のレベルアップ」を目指すにあたり、このKDDIの取り組みを参考にできる企業も多いだろう。
Domoでは、データプラットフォームや分析ツールの提供にとどまらず、導入時に、これらを十分に活用するためのコンサルティングやトレーニングも合わせて提供している。この中には、企業がデータ活用のKPIを明確にし、現場にとって有用なインサイトを得やすくなるようなダッシュボード作りを支援することなども含まれている。また、Domoを通じてデータドリブンな企業への変革に成功した多くのグローバル企業、日本企業のパートナーとして、ベストプラクティスやアイデアの共有も積極的に行っている。これから「データアンバサダー」を社内で育成し、データ活用とDXを加速させたい企業に対し、強力な支援を提供できる。
[PR]提供:ドーモ