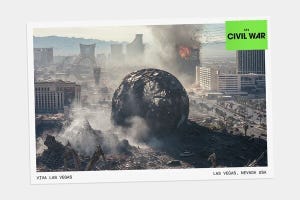OpenAIがプロトタイプ提供を開始した「SearchGPT」を試し始めて2週間が経ちました。課題を理解して使えば、AI検索はとても有用な機能です。ただし、同じAI検索でも、SearchGPT、Perplexity、AI Overviewでは、普及に向けたアプローチが全く異なります。「テックトピア:米国のテクノロジー業界の舞台裏」の回はこちらを参照。
AI検索のプロトタイプ「SearchGPT」発表
Perplexityがソフトバンクと組んでサービスを展開し始め、日本でもAI検索が関心を集め始めました。Googleも「AI Overview」というGoogle検索の結果からAIが要約を生成する機能の提供を日本でも開始しました。
そうした中、OpenAIが7月にAI検索のプロトタイプ「SearchGPT」を発表しました。AI検索では後発でも、すでにChatGPTで先行している優位があり、Google検索対抗の本命とみなされています。その実力はどの程度のものでしょうか。
従来のWeb検索では、ユーザーが検索クエリを入力すると、結果に関連するWebページのリンクが一覧表示されます。対して、AI検索は、ユーザーのクエリに基づいて、AIが情報を収集・整理し、回答を作成して提供します。
自然言語処理に長けているので、ユーザーは自然な言葉で質問でき、AI検索は質問の意味や文脈から推論して質問に対応してくれます。一例として、「パリ五輪には何カ国が参加しましたか?」というクエリで比べてみましょう。
AI検索では、対話するように検索を続けられます。上の例だと、「参加国で最も小さい国はどこ?」というように追加質問すると、AI検索が前の質問を踏まえて、「参加国=パリ五輪の参加国」とみなしてくれます。
同じような質問にはChatGPTも対応してくれます。MicrosoftのBingとの連携機能が組み込まれてから、ChatGPTもWebから最新情報を取得して回答できるようになりました。
しかし、ChatGPTは対話AIであり、検索の目的に応えるように設計されたツールではありません。回答の根拠や情報のソースがあいまいであったり、「ハルシネーション」と呼ばれる生成AIが事実に基づかない情報をもっともらしく生成することもあります。
AI検索は対話AIの対話力を活かしつつ、検索により適切に対応できるように最適化されており、また情報のソースを明確に記してユーザーが確かめられるようにしています。
ソースの表示には、価値のある情報を提供しているWebページにWebユーザーを導くという狙いもあります。AI検索の回答だけで検索の目的が満たせるようになったら、検索ユーザーが情報を発信しているWebサイトにアクセスしなくなる可能性があります。AI検索は充実したソースがあってこそです。
AI検索のプロトタイプ「SearchGPT」発表
AI検索の影響で、情報やコンテンツを提供するメディアやクリエイターが減少すれば、AI検索の回答の質が悪化する悪循環に陥ってしまいます。それを避け、Webのエコシステムを健全なものにするために、有益な情報やコンテンツの提供者と共存共栄する環境作りが欠かせません。
そのため、同じAI検索でもサービスごとに情報提供方法はさまざまです。GoogleのAI Overviewは従来のWeb検索とAI検索の共存を図っています。検索結果の概要という形で、従来のWeb検索の結果とともに表示されます。
PerplexityはAIが検索を代行し、ユーザーが充実した情報を得られる回答を生成します。そのため、情報ソースのリンクは表示されるものの、ソースのWebページを開くことは少なくなります。同サービスが広告掲載を計画しているという報道がありますが、サービスの仕組みからもその可能性を感じ取れます。
SearchGPTもPerplexityと同じように、検索に対して回答を生成して表示しますが、より対話を促すインターフェイスになっています。回答は短くまとめられることが多く、チャット感覚で検索を進められます。各回答にはソースのリンクが付けられ、サイドバーのソース・アイコンをクリックすると、検索に関連するWebページのリストが表示されます。対話しながら検索を深め、回答が簡潔なのでより情報を得るためにソースにアクセスすることも多く、その点でバランスが良い仕組みと言えます。
OpenAIは今年、News Corp 、Axel Springer、Condé Nast 、Financial Times 、Vox Mediaといったメディア大手と次々にライセンス契約を結んでいます。これがSearchGPTの特徴となっており、使っていて私はAppleの「News+」(日本未提供)を思い出しました。News+は、「信頼できるジャーナリズム」を届けることを目的としたサービスです。SNSなどでソースがあいまいなニュースや誤った情報が拡散される中、Appleは契約する400以上の新聞社や出版社のパートナーが提供するトップ記事や電子版の雑誌にアクセスできるようにしています。
AI検索を利用する上で、サービス選びの重要なポイントの1つになるのが、信頼できるソースの情報に基づいて回答が生成されているかどうかです。Perplexityの記事盗用が指摘されるなど、AIのコンテンツ生成における模倣や著作権で保護されたコンテンツを用いた学習に関連する著作権問題の論争が激化する中、大手メディアとのライセンス契約はSearchGPTの強みとなっています。
SearchGPTでは、Perplexityとは逆に、広告に頼らない収益モデルを模索していることがサービスから感じ取れます。ChatGPTの話題性や利用者の規模を考えるとそれを実現できそうな可能性があり、期待が高まります。ただ、コストが積み上がる一方で収益化の具体的な見通しを示せていないのも事実であり、不透明感を拭えない状況が続いています。
また、Perplexity、SearchGPTとも、検索によっては誤った回答を返したり、ハルシネーションを起こすことがあります。調べればわかる検索、例えば「暗殺者のパスタのワンパンレシピを教えて」のような、シンプルに情報を探してもらう検索では正確な回答を得られますが、複数のソースからの情報を総合して答えを導き出すような複雑な質問では、事実と異なる回答が作成されることがあります。ただ、そうしたケースでもAIが集めたソースはとても参考になり、リサーチの効率性を高めてくれます。
-

大統領選挙に関する質問に対して、SearchGPTは世論調査に基づいて「8月26日時点ではカマラ・ハリス候補が優勢」と回答していますが、こうした種類の検索で重要なのは分析です。ソースにアクセスすることで、背景の理解が深まり、情報の信頼性や透明性も確かめられます。
事実の確認のようなシンプルな質問では、AI検索は迅速に答えを提供してくれます。一方、複雑なリサーチや複数の視点を必要とする場合に、AIに答えを求めるのは使い方として適切ではありません。将来AIが人よりも賢くサポートしてくれる可能性はあるものの、今のところ、AIも人と同じように"無茶ぶり"な要求に戸惑います。
AIはあくまでツールであり、最終的な判断はユーザーに委ねられます。リサーチをしている人が包括的な理解を得るのに必要な情報やインサイトを提供してもらい、判断のための"情報的な土台"を築くのにAI検索を活用する。情報キュレーターや調査アナリストのような役割を与えると、AI検索は優れたツールになります。