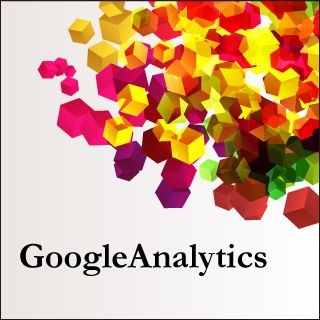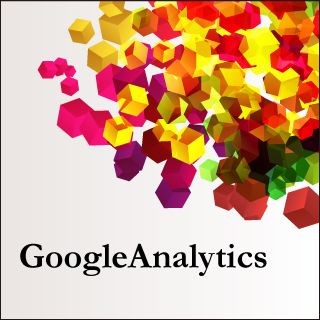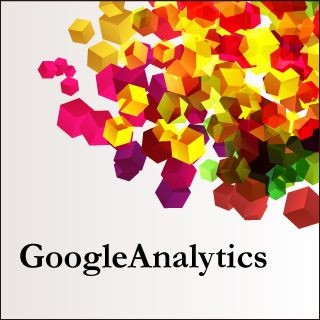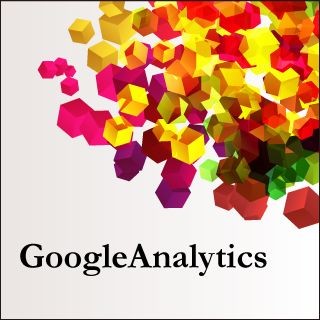Google Analyticsを活用し、「サイトに訪問したユーザーがどのコンテンツを経由し、コンバージョンに至ったのか」を理解することで、より効果的なコンテンツの制作やキャンペーンの運用を行うことを目的に進めてきた本連載。最終回のお話を始める前に、これまでの内容を振り返ってみましょう。
まず、第1回ではコンテンツマーケティングを行う目的を明確化した上で目標値を定義し、その指標(以下、KPI)を測定する方法について紹介しました。ここでは特に、集客の効果指標として「数と質の両方を見ることで目的を達成しているか計測することの重要性」をお伝えしたかと思います。
第2回では、Google Analyticsを活用して分析を行う際に陥りやすい、「直帰率」と「平均滞在時間」の落とし穴について解説しました。例えば、「直帰=クオリティの低い訪問」との認識は正しいのか、「滞在時間」はユーザーが本当に滞在した時間を示しているのかなど、指標の意味を正しく捉えているかを確認しました。
そして、第3回ではGoogle Analyticsのイベント機能を用いて「コンテンツが読まれているか」を測定する方法を、第4回ではUTM タグを活用し「キャンペーンごとの効果を測定・比較」する方法をご紹介しました。
【連載】測定だけで終わらせない! Google Analyticsによるコンテンツ効果分析
1 : コンテンツへの集客前に、目的と効果測定指標を決めよう
2 : あなたは気付いている? 直帰率と平均滞在時間の落とし穴
3 : ユーザーがコンテンツを"読んだか"を測定する方法とは
4 : コンテンツ訪問者の質を把握し、キャンペーンの効果を可視化しよう
最終回となる今回は、「コンテンツへの集客効果の検証と、改善プロセスを動かす"PDCAサイクル"」についてお伝えしたいと思います。
コンテンツへの集客効果を判断するポイント
「せっかくコンテンツ(記事)を作っても、なかなか訪問者が増えない」という悩みを抱えている担当者さんは多いと思います。その改善策として、メールマガジンやSNS、各種Web広告などざまざまなチャネルを用いて集客を試みているのではないでしょうか。
集客を目的としたマーケティングでは、その効果を大きく分けて3つのポイントで検証することができます。
- コンテンツへ導くレコメンドの見出しタイトルや
イメージ画像(クリエイティブ)は、クリックを生み出せているか- コンテンツは読まれているか
(コンテンツは、ユーザーときちんとエンゲージできているか)- ユーザーがコンテンツを読んだあとに、期待した行動を取っているか
コンテンツに集客を行っている企業の視点から見ると、Google Analyticsで計測できるのは、自社(オウンドメディアなど)のコンテンツへユーザーが訪問した時点からです。もし、レコメンデーションサービスなどで集客を行った場合は、当該サイトへ訪問する前の行動、例えば"レコメンドの見出しやクリエイティブの効果"をサービスベンダーにレポートとして出してもらい、効果の検証を行う必要があります。
ここではコンテンツ拡散サービスを利用してコンテンツへの集客を行ったケースを想定し、計測データを基にした施策の改善プロセスを考えてみたいと思います。
この例では、商品Aの認知拡大キャンペーン「prodA_promo」において、直帰率(コンテンツを読まなかったユーザーの割合)が23.56%、新規セッション率が92.11%という結果となりました。
では、このデータから何を学ぶことができ、どのように活かせばいいでしょうか。継続改善(以下、PDCA)のサイクルに当てはめてシンプルに考えてみましょう。
集客キャンペーンの効果を最適化するPDCAサイクル
キャンペーン効果を最適化するためのPDCAサイクルは、下の図のようになります。
| PLAN | キャンペーンの設計 |
|---|---|
| DO | キャンペーンの運用と計測 |
| CHECK | 計測データの評価 |
| ACT | 計測指標に基づいた、仮説と原因の抽出 |
この図において注目したいことは、「PDCAは無限の回転円であり、常に改善を行っていくという考え方が基本である」ということです。これをキャンペーンの運用に当てはめた場合、計測したデータを評価・解釈し、そこから得られた知見をベースに改善のための施策を設計。そして、その施策を実施し再度計測したのちに、その改善施策の効果を確認するプロセスを、次のPDCAサイクルにおいて行っていきます。具体的には、下記の5つの行程が必要だと考えていください。
- 目標値に基づいて、キャンペーン効果を判定
- キャンペーン効果へ貢献した要因を究明
- マイナス要素を排除し、プラス要素を拡大するべく、次の施策を設計
- 次のサイクルで運用
- 施策の効果の是非を分析し、更なる改善への可能性を検討
キャンペーン効果に貢献した要因の究明と、改善施策
先に例示したキャンペーンでは、ユーザーがレコメンドされたコンテンツへ訪問し、内容を閲覧しなかったセッションの割合は、わずか23.56%でした。これは良かったのでしょうか、悪かったのでしょうか。目標値が30%であったとすれば、良い結果です。
では、想定より良い結果をもたらした要因は何だったのでしょうか。第4回で紹介した計測構造を運用していれば、キャンペーン全体としての数値だけでなく、更に細かい、キャンペーンを構成する要素ごとの貢献度合いを分析することができます。
キャンペーンで運用しているコンテンツが複数ある場合は、下記を確認してみましょう。
- 複数ある運用コンテンツページを比較し、
「記事を読まなかった割合」などエンゲージ指標において有意差があったか- 集客用のタイトル(見出し)はうまく機能しているか
▼タイトルがうまく機能しているか判断する基準例
- 一つのコンテンツページに対し、ユーザーの関心や需要の違いを想定して異なるキーワードを5つ用意し、その中でクリック後のユーザー行動が飛びぬけていいものはないか
- タイトルのクリック率は高いにも関わらず、ページに訪問したユーザーが読まずに去ってしまう頻度が高いタイトルはないか
集客のキャンペーンを実施し、ページを読まずに去ってしまうユーザーが多いタイトルや、反応の良かったタイトルがあった場合、それは何を意味しているでしょうか。以下のような点を検証してみてください。
・ユーザーがタイトルを読んだ際に期待した「クリック後に得られる体験」と、
実際のページ内容に大きなギャップがないか
レコメンドタイトルから創り上げた期待と実際のコンテンツ体験との間にギャップがあり、コンテンツに対して失望感を味わったユーザーは、ブランドにとって良いユーザーになるどころか、ネガティブなブランドイメージを持つようになってしまう恐れがあることから、そのタイトルの運用を停止した方がいいかもしれません。・ユーザーが記事を最後まで読んでいる割合が高いタイトルがあるか
期待する行動をしてくれるユーザーを効果的に集客できるタイトル・コンテンツがあれば、同じ方向性のコンテンツ運用を拡大することで、キャンペーン全体の効果をさらに高めることができるかもしれません。・地理的要素はあるか
関東地方では効果がないが、関西ではユーザーにうまく"響く"タイトルがあったりするかもしれません。その場合は集客の際のタイトルの使い分けをしてみてもよいでしょう。
キャンペーンにおいて、プラスの効果を創り出している要素はタイトルかもしれませんし、コンテンツの内容かもしれません。あるいは、単純にそのページのデザインがユーザーにとって読み易い体験を作っているのかもしれません。そのようなプラス要素を発見あるいは仮説立てすることができれば、この要素を積極的に取り入れたコンテンツタイトルやページクリエイティブを導入した改善策を行うことが可能になります。
この仮説に基づいた改善策を設計・運用・計測し、仮説を検証にかけてさらに深いユーザー理解へつなげていくのが、PDCAサイクル2巡目の役割です。改善施策の計測においては、それ独自の計測指標と目標値を設定し、計測タグも当初の「ベースライン」のものとは別の値を割り当てて細分化し、詳細に分析・検討する方が良いでしょう。
まとめ
このように、コンテンツマーケティングにおけるGoogle Analyticsによる計測は、測定だけで終わることはありません。実施したキャンペーンは、ユーザーがどのように反応したかを理解する貴重な機会となります。そのデータを理解し、仮説を組み立てて、実証を繰り返すことで、ユーザーの求めているコンテンツをよりよく理解し、ニーズにマッチしたものを提供することが可能になります。
そして、コンテンツマーケティングを行う本来の目的「ユーザーがコンテンツに触れることで態度変容を起こす」という結果を少しでもうまく作り出せるようになれば、これほど強力なブランド・タッチポイントはほかにないかもしれません。
かなり絞ってお届けしてきた本連載ですが、今後、みなさまのコンテンツがますますユーザーにとって楽しく、有益な情報にあふれ、自然に消費されるようなものとなり、かつ、みなさまの目的も達成する素晴らしいものになっていく一助となりましたら幸いです。
執筆者紹介
アウトブレイン ジャパン 筒井 祐介

世界規模のコンテンツレコメンデーションプラットフォームを活用し、企業のコンテンツマーケティングを支援するアウトブレインジャパンのシニアアカウントストラテジスト。Web解析ツールのエキスパートとして、データを用いたマーケティング施策改善のためのコンサルティングを行う。アウトブレイン入社前は、オーストラリアを拠点に約8年間、デジタルマーケティングの分野でサイト解析や効果分析の業務に携わる。なお、アウトブレインの公式Webサイトは、こちらから。