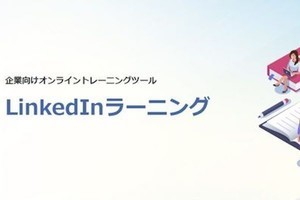リスキルで過去の自分を破壊する
今回は、欧米ではよく使いますが日本ではあまり使わない「Disrupt(名詞 Disruption)」の大切さについて書いてみたいと思います。Disruptは、日本語でいうと「破壊する」という意味です。筆者はプロレスファンなので、破壊といえば「破壊王・橋本信也氏」を思い出しますが(マニアック!)、ビジネスにおいては「建設的な破壊」という意味があります。
随分前になりますが、筆者がCisco Systemsで働いていたとき、同社のリーダシップの定義が「C-LEAD」で、その最後のDがDisruptであったことを思い出します。Cは「Collaborate = 協調せよ」で、それがリーダシップの基盤になり、Lが「Learn = 学べ」、Eが「Execute = 実行せよ」、Aが「Accelerate = 加速させよ」です。そして、Dで建設的な破壊を自らせよ、そんな定義になっています。
日本の企業に破壊することがリーダシップと考えている組織はほぼないと思いますので、C-LEADは今でも新鮮で、この言葉を大切にして仕事をしています。
このDisruptは現在のリスキルにも通じる気がします。リスキルは、まったく新しいスキルを習得して人をトランスフォームすることで、過去の自分をある意味、建設的な破壊をしないといけないからです。英語ではよく、Comfortable Zoneという言葉を使います。長年親しんだ環境である快適なゾーンからなかなか人間は抜け出せないので、「変わらない人」に対するネガティブな言葉として使います。Comfortable Zoneから脱出するためには、Disruptionするわけです。
Disruptはなぜビジネスで重要なのか
続いて、なぜビジネスでDisruptが大事なのかを説明したいと思います。S字カーブという言葉をお聞きになったことがあるかもしれません。これは、テクノロジーの進化と普及の様子を表している言葉で、テクノロジーは最初はゆっくり進化して普及していきますが、成功するとある時点から指数関数的に進化・普及していきます。そして、テクノロジーは成熟すると、進化や普及が踊り場にきてあまり進捗しなくなります。こうした動きがS字のように見えることから、S字カーブと呼びます。
AIを見てもそうですよね。第1次AIブームは1950~1960年代に起こり、「推論」と「探索」が研究され、数学の定理証明など特定の解が提示されました。これはほんの序章です。
そして、筆者がちょうど1990年代の前半にDECで勤めていたときに第2次AIブームとなるエキスパートシステムが浸透し始めました。社内にAIのエキスパートがおり、専門分野の「知識」をコンピュータに取り込み推論を行うことで、コンピュータがその筋のエキスパートのように振る舞うシステムを提案していました。当時は機械学習が無かったので、人間が知識を記述する必要があり、結果としてあまり普及しませんでした。
そして今、ChatGPTを含むAIの急速な進化が起きております。どこまで進化が進み、いつ踊り場にくるか分かりませんが、いつかはS字カーブの終わりにくるのです。テクノロジーが進化すると模倣犯も多く市場に参入して、競争が激しく利益が出ないレッドオーシャン状態になります。
ただ、一部例外的に踊り場が長いテクノロジーや製品がありますね。それは、ERPやリレーショナルデータベース、Microsoft Officeなど、デファクトスタンダードになったものです。進化はしているのでしょうが、他に替えようがなく、クレイトン・クリステンセン氏が提唱したイノベーションのジレンマが示す、低価格の代替製品の攻撃をかわした製品が生き残るのでしょうね。
Disruptをビジネスで起こすために
S字カーブから見えるのは、1つのテクノロジーに頼っていると、やがてビジネスも終焉するということです。適切なタイミングを見極めて、踊り場に来たテクノロジーをベースとしたビジネスを破壊して、次のS字カーブを積極的に生かして長期的な成長をする必要があるということです。S字カーブを連続して作るイメージです。
デジタルの進化が加速する今、S字カーブの幅が短くなってきています。マッキンゼーのレポート「Actions the best CEOs are taking in 2023」では、2023年にCEOが組織を率いる際の行動における重要なトレンドの1位に「破壊的なデジタルテクノロジー」、2位に「継続するインフレと経済の低迷」、3位に「地政学」を挙げています。テクノロジーをうまく管理するのは、業界にかかわらずCEOの仕事になっているのです。
では、このDisruptをビジネスで起こすためにはどうすればいいのでしょうか?それはもちろんCEOだけの仕事ではありません。以下、そのヒントをいくつか紹介していきましょう。
まず、Cisco SystemsのC-LEADで触れたように、企業にリーダーシップを組み込む必要があります。そのような企業文化を形成して、建設的な破壊が推奨される環境を作るのです。そうしないと、Disruptに挑む人が単なる浮いた人になってしまいます。現状維持は戦略ではないことを浸透させてください。しかし、Cisco Systemsは素晴らしい考えを十数年前から持っていましたね。
また、ガートナー社のハイプサイクルように、自社に関連するテクノロジーのライフサイクルをきちんと確認していく必要があります。自社のビジネスが単なる低迷期にあるのか、踊り場に来ているかという判断は難しいですが、市場の全体の成長と経済状況の大局を見て、破壊のタイミングを判断していきます。破壊といっても、新規投資を抑制して現在までの投資を最大限回収するという緩やかな破壊もあるかと思います。
そして、上でも述べましたが、常にS字カーブを複数重ねていく必要があります。これには新しい知識やスキルが必要であり、継続して学ぶ文化や体制、そして、そのようなスキルを持った人の採用などを整備しないといけません。また、企業と取り巻く環境から将来起きるシナリオを分析して、対応を計画するシナリオ・プランニングといった未来を切り開くスキルも大事かと思います。
ただ、どの時点で建設的な破壊を起こすかは、Microsoft Officeの例を考えても難しいものがあります。そして、当然、破壊にはリスクも伴います。タイミングを見るには「死亡前死因分析」が有効かもしれません。これは仰々しい名前ですが、ダニエル・カーネマン氏の行動心理学の名著『ファスト&スロー』で提唱している方法です。
具体的には「今が一年後だと想像してください。私たちは先ほど決めた計画を実行しました。すると大失敗に終わりました。どんなふうに失敗したのか、5~10分でその経過を簡単にまとめてください」と、分析する方法です。
知見を持つ人で集まり、一年後の状況を分析して死亡させるべきものを決めるのは、Disruptを促進する1つの方法です。
ヒト、モノ、カネのリソースには限りがあり、成長への投資のためにも建設的な破壊は大事です。これは、ビジネスにも自分のキャリアにも言えると思います。同じ仕事は永遠には続きません。