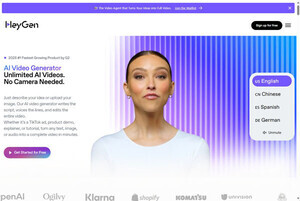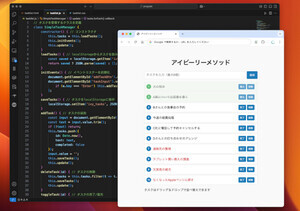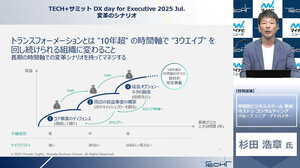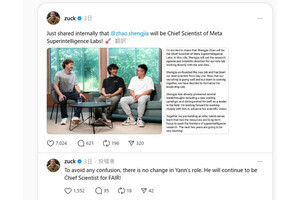1979年の創業以来、当社は時代の要請に応じ、循環資源の製造・提供や循環型事業開発に向けた概念実証の実行支援、サーキュラーサプライチェーン(循環型供給網)の構築支援など、資源やエネルギーを制約としない循環型ビジネスへの移行と持続可能な経営の実現を支援してきました。
そもそも日本はいま転換期にあります。これまでの大量生産・大量消費・大量廃棄というリニア(直線)型経済モデルが、資源枯渇と気候変動による〝安定調達の限界〟、格差拡大・高齢化・雇用不安による〝社会的限界〟、実体経済と金融経済の乖離による〝市場拡大の限界〟という3つの構造的な限界に直面しているからです。
日本は無資源国で人口減少が進む国です。しかしながら、バブル崩壊後の低成長から脱却できないまま、製造業も高度経済成長期に成功した旧来のビジネスモデルに固執し、多くの資源や市場を海外に依存してしまっています。このままでは国内の産業の空洞化が避けられません。
つまり、日本は従来の資本主義モデルからの転換という歴史的なレジーム(体制)の変革を迫られており、製造業を含む全産業が変革を求められているのです。具体的には、資源や製品の再利用など、循環型の仕組みへの変革です。このことは内需市場の拡大にもつながります。
ただ、複雑かつ高度になった現在のビジネスモデルを個社で変革するのは極めて難しい。そこで当社は三井住友ファイナンス&リース、アビームコンサルティング、サーキュラーリンクス、GⅩコンシェルジュと提携し、サーキュラーエコノミーによる製造業のサステナビリティ(持続可能性)経営への変革を支援する「Circular Co︱Evolution」という支援サービスを始めました。この5社連携で、製造業のサステナビリティ経営の企画構想から変革実現、運用改善までを一気通貫で支援し、企業と社会の共進化を目指します。
振り返れば、私が資源循環の気づきを得たのは23歳のとき。叔父が経営する非鉄金属の卸売会社で汚泥を分析したところ、地金の原料であるニッケルが同量の天然鉱山の約10倍含まれていることを発見しました。この活用を取引先の大企業に提案したところ、若造の私が50~60代の工場長から「ありがとう」と感謝されたのです。資源循環の意義を感じた瞬間でした。ただ、これを始めた80年代はリサイクルが浸透しておらず、廃棄物を集めようとしても断られてばかり。皆が「無関心」でした。
「豊かな経済」ではなく「豊かな社会を支える健全な経済」を目指そうと考えていた私は閃きました。無関心なものは安く手に入る。ならば、それを集めて「関心」に変えようと。徐々に廃棄物も集まり、商売として成立するようになりました。
さらに1990年代後半、資源を適切に管理する事業者を評価するため、サプライチェーンを見える化する流れが生まれました。当社は日本初の森林認証審査会社として環境認証審査サービスも始めました。
私はサーキュラーエコノミーと日本人の思想には親和性があると感じています。日本には既存の要素を集めて次につなげる「編集知」があるからです。インターネットで我々の生活や社会が大きく変わったように、経済モデルも今までの経済大国志向から循環大国志向に変えることができるはずです。
経営者は運営者ではありません。そういった未来を見通す力と自ら描いたビジョンを実現させる覚悟が必要になるのです。