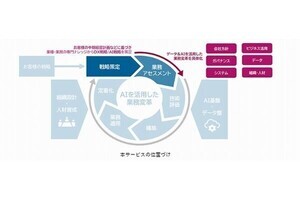投資元本を上回る回収
「この10年間、官民ファンドの存在意義とは何なんだろう? あるいはINCJの存在意義とは何なんだろう? ということをずっと自問自答してきた。非常に難しいかじ取りながらも、日本のためにいいことをやってきたと考えている」
こう語るのは、官民ファンド・INCJ(旧産業革新機構)元会長兼CEO(最高経営責任者)の志賀俊之氏。
INCJが今年3月で全ての投資活動を終え、6月末で退任した志賀氏はこのように振り返った。
【混沌期の中、日本の針路を探る】御手洗冨士夫・キヤノン会長兼社長を直撃!
産業革新機構は2009年、産活法(正式名称は「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」)に基づいて設立。「オープンイノベーションを通じて次世代の国富を担う産業を育成・創出する」ことを目的に、今年まで15年間の時限組織として、投資活動をスタートさせた。
2015年6月には、日産自動車でCOO(最高執行責任者)をつとめた志賀氏が会長CEOに就任。今年6月に退任するまで10年間トップをつとめた。
その後、2018年に同機構の根拠法である産業競争力強化法が改正。産業革新機構は産業革新投資機構(JIC)に商号変更し、会社分割する形でINCJとして活動を続けてきた。
今年3月末までに144件の投資を実施。約8割の116件はスタートアップなどのベンチャー投資。中長期のリスクマネーを提供することや民間だけではリスクが高く、投資が困難な分野への投資という基本方針に基づく投資だった。
すでに143件の投資回収を完了しており、残る1件についても今後、適切にイグジット(投資回収)活動を行っていく予定だ。
15年間の累積投資額は1兆2963億円で回収額は2兆3260億円。イグジットしていない残る1件を除いて1兆円を超える利益を確保したことで、志賀氏も「投資元本を上回る回収ができたことは大きな成果」と考えているようだ。
もっとも、144件の投資に対して1兆円超の利益が出たとはいえ、その内訳をよく見ると、大半はルネサスエレクトロニクス1社の貢献が大きい。
日立製作所、三菱電機、NECの半導体事業が統合して2010年に誕生したルネサスは、翌年の東日本大震災で主力工場だった茨城県の工場が被災。産業革新機構は、2013年に約1383億円を投じてルネサスの株式69.2%を取得。その後、リストラや構造改革を繰り返して経営を再建し、徐々に一部株式を売却。2023年に全株式を売却し、回収総額は1兆3940億円だった。
一方、厳しい結果となったのが、ジャパンディスプレイ(JDI)への投資。JDIは2012年にソニー、東芝、日立製作所の中小型液晶事業が統合して発足。産業革新機構が70%、民間3社が10%ずつを出資して誕生したが、韓国や台湾、中国などの競合が台頭し、価格競争が激化。次世代パネル・有機ELのシフトにも出遅れ、現在まで11年連続で最終赤字が続く。INCJは今年3月に1547億円の損失が確定した。
また、2015年にはソニーとパナソニックの有機EL事業を統合し、産業革新機構の主導でJOLED(ジェイオーレッド)を設立したが、23年に破綻。総額1390億円の投融資が実らなかったことで、国の責任を問う声が高まっていた。
ルネサスにしろ、JDIやJOLEDにしろ、本来、次世代産業の創出という目的だったはずの投資が、時には「ゾンビ企業の救済ではないか?」などと批判されることも多々あった。
そうした中、志賀氏は「何をやっても批判されるのが官民ファンド」と自虐的に話しつつ、「期待されているのは、リスクマネーの供給と国の産業政策を社会実装していくことだが、これは難しい。行政側の産業政策に軸足を置くと収益を上げづらく、収益に軸足を置くと民業圧迫論というのが出てくる。非常に難しい舵取りだった」と語る。
産業政策の失敗の責任は誰が取るのか?
投資だから成功することも、しないこともある。ただ、官民ファンドの原資は大半が公的資金であり、国民の税金だ。
INCJはトータルで利益を確保したものの、政府の巨額投資に見合う成果や利益が出なかった場合、産業政策の失敗の責任は誰が取るのか、そして、業界再編に国がどこまで関わるべきかは、今後も問われる。
現在、政府は〝経済安全保障〟の旗のもと、次世代半導体の製造を目指すラピダスへ、合計1.8兆円規模の支援をすでに決めているが、ラピダスにも「JDIなどの二の舞になるのではないか?」との懸念は尽きない。
産業政策に詳しいIGPIグループ会長の冨山和彦氏は「INCJは新産業、破壊的イノベーション領域へのまとまったリスクマネーの供給を目的としていた。スタートアップムーヴメントがここまで大きくなることに多少なりとも貢献できたと思う。一方で、産業再編型の投資案件に引っ張られたことはやや想定外。イノベーションという言葉の多義性ゆえに便利な財布として使われた部分もあったかもしれない」と指摘する。
INCJは残る1件の保有株式の処分が終わり次第解散し、今後の投資活動は後継組織のJICに引き継がれる。JICの活動期限は2050年まで。今後はエネルギーや宇宙など、より長期的な観点での投資が期待されており、INCJの教訓をどう生かすかが問われることになる。