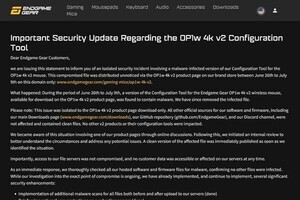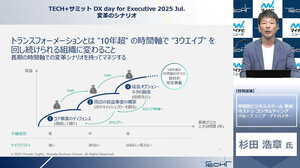環境に優しいブレーキ摩擦材
─ 綿紡績を祖業としていますが、今は無線・通信、半導体のエレクトロニクス事業を主力としながら、ブレーキ事業などその他の事業も手がけていますね。
村上 はい。今は外部環境が大きく変化していますが、当社の事業のうち無線・通信事業が伸びています。これはお客様が国内官需主体となっており、内需が強いからです。当社の無線・通信事業は、日本無線と国際電気の2社が担っていますが、共通するのは防災・減災向けのソリューションビジネスという点です。
具体的には、レーダーやカメラといった機器を組み合わせたシステムをお客様に納めています。イメージとしては災害時などに屋外スピーカーを通じて無線放送を行って緊急情報を広く同時に報じる「同報無線」の進化版です。
─ ブレーキについては?
村上 当社の売上構成比の12%を占めています。最近では、2023年に欧州のTMD社を譲渡したことが大きな出来事でした。TMD社の摩擦材と当社の摩擦材とはモノが全く違います。組成が全く違っているため、作り方も全く違う。買収しても十分なシナジーが出なかったのは、このためです。
─ 市場や用途が別だと?
村上 ええ。当社のブレーキ摩擦材は「ノンアスベストオーガニック材」と呼ばれる「NAO材」です。文字通り、有害物質のアスベストを使っていない製品ですから環境にも優しい。
一方のTMD社のブレーキ摩擦材は「ロースチール材」と呼ばれるもので、金属のスチールが入っている。こちらの方が制動距離(ブレーキをかけてから完全に停止するまでの距離)が短いという強みがあるのですが、その分、摩擦材が擦れて落ちる粉が環境に悪影響を与えてしまうという点があります。
今後は地球環境への負荷を低減した安全性、快適性のある摩擦材で世界をリードしていきたいです。
─ シナジーや環境面を踏まえての経営判断ですね。半導体の手応えはどうですか。
村上 ちょっと心配というのが正直な感想です。当社にはアナログ半導体事業を行っている日清紡マイクロデバイスという会社があります。実はこの会社が昨年、一昨年と会社のグループ業績に対してかなりマイナスの影響を及ぼしてしまいました。要因は半導体不況です。
これはシリコンサイクル(半導体産業に見られる約4年の周期での景気循環)と言われる宿命でもあります。活況を呈した時期もあれば、その反動で一気に落ちる時期もあると。
デジタルとアナログの半導体
─ 半導体でも米エヌビディアは好調を続けています。
村上 はい。AIやデーターセンターなどで使用されるGPU(画像処理装置)ですね。デジタル半導体とも呼ばれていますが、こういった特殊な半導体はエヌビディアなしには成り立ちません。一方で当社や米アナログデバイセズなどはアナログ半導体を手掛けています。当社の規模であれば波に揉まれてもやっていけます。
アナログ半導体では民生用と産業機械用、自動車用があるのですが、当社は3分の1ずつの売り上げ構成となっており、外から見てもベストバランスになっているように見えますが、自動車向けの比率を高めておかないと、どこかで景気感の波に惑わされることになります。
─ なぜですか。
村上 個数が違うからです。民生用はスマートフォンなどのデジタル機器向けで数は大量に出ます。しかし単価は安い。一方で自動車用は数が少なくても単価が高い。特注品だからです。そうすると、工場の稼働率も民生用のボリュームに引っ張られます。民生用の数が減ると工場の稼働率が悪くなり、コストが上がって赤字になるのです。そう考えると、自動車用の比率を高めておかないとシリコンサイクルの波は乗り切れません。
足元では当社がお付き合いしているゲーム機やスマホなどの民生用は追い風が吹いていますが、会社全体を支えるほどのものではありません。また、工作機械や半導体製造装置用の産業機械用も不透明です。ですからトータルで見ると今年も厳しい状態が続くと見ています。
─ デジタル半導体とアナログ半導体は共存できますか。
村上 そう思います。ですから、将来的には成長市場です。ラピダスや台湾のTSMCが手がけるデジタル半導体の世界は超微細かつ大量生産です。対して当社のアナログ半導体は別物。よくAIを活用した音声サービスなどがありますが、このとき我々がスマホを手にして音声を取るときはアナログです。音声はリアルですからね。これをデジタルに変換する必要があります。そこでアナログ半導体の出番になるわけです。
そしてデジタルに変換したデータがサーバーで計算や分析されて整備されたデータの形となって戻ってくる。そのデジタルなデータを再びアナログの音声に変換してスマホに戻すわけです。ですからアナログがないと成り立たないのです。
現在の日清紡ホールディングスが手がける商品群(左から、船舶用衛星通信装置、アナログ半導体、ブレーキ摩擦材)
─ 対立ではないと。
村上 そうです。もの凄く高スペックでどんどん進化していくのがデジタル半導体であり、それを補完するのがアナログ半導体です。アナログも欠かせない存在なのですが、技術がそこまで進化する世界ではありません。デジタル半導体の世界では2ナノ(10億分の2メートル)という数値が出てきますが、それだけ小さなものを要求されます。
一方でアナログ半導体の大きさは進化したと言っても180ナノです。それくらいのサイズでないと、ボリュームが出ないのです。仮に2ナノで大量生産しても用途が限られるため売れません。だから少量なのです。アナログ半導体も一般的には多品種少量なのですが、カスタマイズされたものを作るから少量になっているに過ぎません。
秘書時代に仕えた 社長が抱いた危機感
─ 足元では分断・分裂の様相を呈しています。日清紡グループは「つなげる技術で価値を創る」を標榜していますね。
村上 はい。まさに「つなげる技術」が当社の事業のベースです。アナログ半導体もそうですし、無線もそうです。センシングでデータ化したものを飛ばしてつないで動かすわけです。
─ 祖業の綿紡織事業からの脱却はどう図ったのですか。
村上 06~07年にかけて当社が抱いた強烈な危機感です。当時、私は岩下俊士社長(故人)の秘書だったのですが、岩下社長は「このままでは会社の将来がない」という話をよくしていました。
過去の成功体験にとらわれて、足元では世界がどんどん変わっているのに、ビジネスモデルを変革できなければ社会のニーズに対応できない事業構造になって会社が廃れる。企業にとって大事なことは常に変化することだが、それでは、どう変化していくべきなのかと。
当社は事業活動を通じて社会に貢献することを使命とする会社です。そして昔から事業の中身は問わないと言ってきた。
したがって、繊維やブレーキにこだわる必要はなく、世の中に貢献できるのであれば、それをやろうと。そして、世の中に貢献するためには社会課題を解決するソリューションを提供することにあると考えたのです。
─ それが事業変革の根底にある思想になるのですね。村上さんは19年から今年の3月まで社長を務めました。そもそも村上さんの日清紡への志望動機は何だったのですか。
村上 まずキラキラネームの会社には行きたくなかったんです(笑)。あとは自分の足で、額に汗して稼ぐ会社に行きたいと思っていました。1980年代初頭当時は金融や商社人気でしたが、私は地道にコツコツ事業を行っている会社がいいと思っていたんです。
しかも日清紡は学閥も派閥もなく、真面目にやることが社是でした。社会に貢献することを標榜している会社が、この会社だったのです。「変わった会社やな」と思いながらも入社してみると、凄い質素だというのが第一印象でしたね。今でも質素ですが(笑)。
─ 当時、繊維の売り上げは全体の何割でしたか。
村上 まだ6割は超えていましたね。ブレーキも戦時中から手掛けていましたね。当社のブレーキ摩擦材の事業は陸軍の航空機向けのブレーキから始まりました。石綿(アスベスト)を扱う技術があったので、軍から御用命があったのです。それが戦後には自動車に使われるようになり、アスベストも使わなくなって今に至ります。
工場内の女子寮の責任者
─ 入社後は紡績工場の労務管理業務でしたね。
村上 ええ。徳島と浜松の2つの工場で計7年半勤めました。当時、工場では15歳から22~23歳の女性社員が働いていて、工場の敷地内に女子寮や企業内学園がありました。私は女子寮の舎監と学園の責任者を務めていました。浜松では400人ほどの女性社員がいましたね。
その女性社員の中にも家庭の経済的な事情で高等学校に進学するのが難しかった社員などがたくさんいたのですが、朝早くから昼まで働き、午後から学校に行く人と、午前中に学校に通って午後から働く人と二交代勤務制でした。仕事と勉強というハードな寮生活を送っていたわけです。
─ 心のケアなど大変な業務だったのではないですか。
村上 そうですね。常にトラブルは起きますからね。浜松のときは寮母さんや教師を含めて6人で当たっていました、寮母さんでは手に負えないトラブルは責任者である私が全て対応してきました。
─ 人間には強さと優しさが必要だと言われます。一方で自己規律も大事です。村上さんが大事にしている思想とは。
村上 当時から当社にあった「事業は人なり」です。そして「経営は教育なり」と「経営の自己責任主義」という3つが標榜されていました。これは当社の元社長で日本経営者団体連盟(現経団連)会長を務めた桜田武(故人)の考えです。
結局、経営は教育なりというのも、上に立つ者が偉いわけではありません。これは教え・教えられる関係であると。労使の交渉の場も同じです。経営側も労働組合も教え・教えられる関係にあるわけです。
では、何を教えるかと言えば、会社は世界の情勢と会社の置かれた事業環境を労組に教える。労組は働く従業員のニーズと今の生活レベル、労組から見た就業環境がどうなっているかを会社に教えるのです。
互いに対立するのではなく、お互いに切磋琢磨して健康な拮抗作用の導出を目指していく。切磋琢磨して答えを出していくことが労使交渉だと。これも桜田の考えになります。