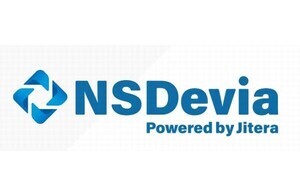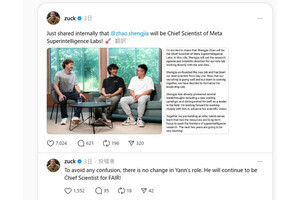参院選を前に、与野党が物価高対策を打ち出し、それが争点になっている。しかし、現金給付や消費税減税を打ち出したところで、ごく一時的な効果しか見込めそうもない。筆者もしばしば「減税ですが、それとも給付金でしょうか?」と尋ねられるが、両方ともNOとしか言いようがない。一時凌ぎはダメだ。
事実関係から述べると、2025年1~5月の消費者物価・総合は前年比が平均3.7%と高い。2人以上世帯の年間消費額365万円をかけると年間+13.5万円の負担増になる(世帯人員1人当たり4.7万円)。この全額を税金で賄うのは、財政負担が大きくなり過ぎる(1人4.7万円×人口1.2億人=5.6兆円)。
では、その代わりにどんな物価高対策をすればよいのか。答えは日銀の利上げだろう。物価高の原因は、円安によって輸入物価が上がりすぎたことにある。金融引き締めで物価を下落させるというのは、教科書的な処方箋である。政治家の口からは、そうした提言が聞かれない。もちろん、トランプ関税の交渉妥結が定まっておらず、すぐに為替を円高にもっていくことはできないが、米国経済が安定成長に戻ったときは徐々に追加利上げをして円安を是正していく。輸出企業の収益状況を見ながら、日銀の利上げを進めていくべきだろう。なお、預貯金金利が+0.5%上がれば、2人以上世帯の受取利息(手取り)は年間5万円ほど増える計算になる。これも金融政策の効果になる。
実は、それ以外にも物価対策として賃上げ効果はそこそこ実績を上げている。25年度春闘は、連合集計(6回目)でベースアップ率が3.71%まで上がってきている。この上昇率は丁度、物価上昇率と同じペースである。春闘結果は、大企業が中心なので、課題は中小企業へと展開していくことだ。大企業・中堅企業に属する雇用者が全体の3割だとすれば、残りの7割にそれを展開してくために、中小企業の成長を促すことが政治の課題になる。野党などから具体的な処方箋が提言されてこない点は、筆者にとっては大変不満なところである。
そのほかに残された問題として年金問題がある。24年の家計構成は、37.9%の世帯が無職世帯である。無職世帯とは、そのほとんどが年金生活世帯である。彼らは、物価上昇率よりも低い年金支給額の増加率に甘んじている。ここが国民の多くが物価対策を求める理由の背景になっている。ここを放置して、給付金をばらまいても、それは一時凌ぎだ。消費税減税をすれば、救済すべき年金生活者の年金給付財源の穴を開けることになって自己矛盾になる。04年の年金改革で、与野党はそれを是正してこなかった。公的年金制度を見直すことこそが、本来政治が取り組むべき改革である。そこを弥縫策で凌ごうとすれば、いつまで経っても国民からの物価対策要求はなくならない。