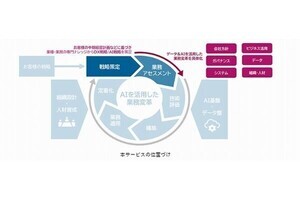米中対立は選別的対立
─ トランプ米大統領の関税政策やイランへの核施設攻撃などで世界が揺れています。こうした状況を寺島さんはどのように受け止めていますか。
寺島 トランプ大統領は一貫して「自国ファースト」を叫び、米国の利害が一番だと主張しています。われわれが眼にしているのは、米国が20世紀に入って続けてきた、世界における指導国としての役割を自ら降りようとしている姿です。
【株価はどう動く?】米トランプ大統領の政策が、日本に「特需」をもたらす可能性も
トランプ氏にとっては、デモクラシーと自由の旗などという精神は関係ない。自国利害中心主義の米国を前提にして、21世紀の世界秩序をどう捉えるかということで、今は世界中で議論されています。
一つは「米国無き世界論」と言って、いわゆるグローバルサウス(新興・途上国)が力をつけてきて、世界の比重が変わりつつあると。分かりやすく言うと、多極化を通り越し、多次元の全員参加型秩序に向かって世界が動いているということ。
もう一つは、「大国の共謀論」というもので、世界の表舞台から米国が去りつつある一方で、米国は裏ではロシアや中国との結びつきもあって、大国の共謀によって自分たちに有利なディール(取引)をして、世界秩序をリードしていこうと。
こういう二つの見方が交錯しているということを理解しておくべきです。
─ 表ではケンカしているように見えても、裏ではしたたかに手を結んでいると。
寺島 ええ。6月18日から、ロシア・サンクトペテルブルクで「国際経済フォーラム」が開催されたのですが、なんと、ここに今年からBRICSに加盟したインドネシアのプラボウォ大統領が参加しました。
BRICSはすでに加盟国が10カ国になり、これからタイやマレーシアまでが加盟しようとしている。これはアジアの国々が米国中心の世界秩序に対して、距離を取り始めていることの表れともいえます。
ただ、もっと驚くべきことは、この会議にロシアビジネスへ興味のある米国のビジネスパーソンが参加しているということです。つまり、資源・エネルギーなど、お互いに米露間でウィン・ウィンになれるところは協力しましょう、という動きが水面下で現実に行われているのです。
─ 複雑な動きですね。これは米中問題でも同じことが言えますか。
寺島 はい。日本人として見抜かなければならないことは、米中対立は選別的対立だということです。確かに先端技術を巡って米中が21世紀の競争関係に入っていることは確かですが、これも大国の共謀という話で、米中2カ国についても、いつ両国でウィン・ウィンの関係を作りましょうなどと言い出しかねません。
米国と中国が激しく対立する時代を生きる、などという単純な図式で物事を考えるべきではないということです。日本は米国とも中国とも断絶する必要は無く、日本は米国との同盟関係を逆手にとって、日本としての活路につなげていくくらいの戦略と知恵が必要なのです。
中国に対しても同じことで、日本は米国の片棒を担いで、米国と連携して中国と対峙するなどという姿勢でいたら本質を見誤ります。むしろ、日本は米中の間に立っていかにプロジェクトなり、政策なりを働きかけていくかが大事なのです。
─ そこに日本の役割があるということですね。
寺島 ええ。昨年、日本の貿易総額における米国の比重は15%になりました。つまり、日本の貿易の85%はアジアなど、米国以外の地域ということです。
一方、対中貿易の比率はどこのエリアまでを含めるかで変わってくるのですが、香港・マカオを含めれば全体の2割、台湾やシンガポールなども含めた大中華圏全体では3割近くを占めます。その意味では、米国の割合は中華圏の半分に過ぎない。
もちろん日米貿易でビジネスをしている当事者にとっては大変な状況ではあります。ただし、貿易総額全体で考えたならば、トランプの高関税政策は、いわば貿易総額の15%部分に影響があるわけで、その他の85%部分では自由貿易を志向するゾーンだという冷静な認識を持つことが重要です。ここは、腹をくくって、大局的な視野から立ち向かっていくべきです。