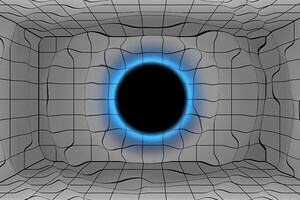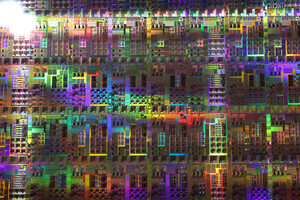政府は経済財政運営と改革の基本方針「骨太の方針」で、インフレや賃金上昇を社会保障費に反映させる方針を決めた。
医療や介護の公定価格の引き上げ幅を極力抑える従来方針を変えるもので、26年度予算編成に反映させる。記録的な物価高により、医療機関や介護施設などの経営が逼迫しており、厚生労働省幹部は「近年になかった大幅な診療・介護報酬など公定価格の引き上げが期待できる」と話す。
従来方針では、財政健全化を優先する考えから社会保障費の伸びを高齢化による自然増分に抑えてきた。いわゆる歳出の「目安対応」と呼ばれるもので、デフレ経済を念頭に置いた考え方だ。近年の物価高騰でも見直されず、診療報酬や介護報酬の引き上げを抑える要因になってきた。
しかし、日本医師会など医療関係の団体から「このままでは経営が成り立たず、地域医療が崩壊してしまう」との悲痛な声が寄せられていた。介護はもともと他産業と比べて賃金水準が低く、施設経営者から「職員が大量離職してサービスが提供できなくなる」と介護報酬の大幅引き上げを要請していた。
厚労省を中心に歳出拡大に慎重な財務省を説得した結果、今回の方針転換を勝ち取った。秋以降、補正予算や報酬改定という形で医療・介護分野などに手当てされる見通しだ。
日医会長の松本吉郎氏は「歳出改革の引き算ではなく、物価や賃金対応分を加算する足し算の論理になった。目安対応とは別枠で物価と賃金の上昇分を(社会保障費に)反映できる」と評価した。