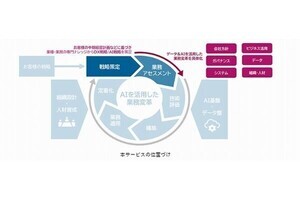「大きな歴史の流れの中で医療を考える必要がある」─河北氏はこう指摘する。東京・阿佐ヶ谷の河北総合病院は2025年7月、隣接地に新病院をつくり開業。1928年の創立以来、地域の中核病院としての役割を果たしてきたが、今、河北氏は「長寿化の中で、新たな医療のあり方を構築したい」と話す。例えば、高齢化の中で増えるがんとどう向き合うかといったことが考えられる。河北氏が考える医療の今後は─。
医療のあり方を見直し進化させていく
─ 2025年6月、河北総合病院が移転、新病院が竣工しましたね。 河北 新病院の竣工は、私達にとって新たなステージだと考えています。
元々、河北総病院は1928年5月に、創設者で、私の祖父である河北眞太郎によって「河北病院」として開院したのがスタートです。
当初は内科・小児科の30床からのスタートでしたが、当時、深刻な国民病と言われていた結核への対応を始め、地域の医療ニーズに応える形で診療科を拡充し、中央線沿線の中核病院としての歩みを進めてきました。
1945年、戦禍を免れた当院は、海軍から復員した私の父・河北恵文が加わり、1950年には医療法の医療法人制度制定に合わせて医療法人財団となり、地域の皆様に支えられながら、医療の近代化を進め、総合病院となったのです。
2028年には創立100周年を迎える節目となります。その先の未来に向け、医療のあり方そのものを見直し、進化させていきたいと考えています。
─ どういった医療のあり方を目指していきますか。
河北 今後の医療は、集学的(多専門職種が連携し1人の患者を診る)、重層的(層を重ねる診療)、地域内完結(住み慣れた地域で完結する医療)、全体最適(患者を取り巻く全てを最適化)といった考え方の下、「人を診る診療」を進めていきたいと考え、「その人らしく生きることを支える医療」に一層取り組んでいきたいと思います。
単に病気を治すのではなく、その人の生き方に寄り添う医療を実現したいのです。
また、身体的なことだけではなく、現代社会においてとても大切な「心のケア」にも注力しており、当院には「心のケアセンター」も設置しています。
今はSNSも浸透し、家族のあり方や友人との関係が変化しつつあります。だからこそ、医療は「こころ」にも目を向けなければなりません。
インフレが医療に与える影響
─ 河北総合病院が進める新たな医療の拠点ができたわけですね。医療全体で言えば、国の医療財政は赤字の状態が続きます。河北さんが考える改革の方向性を聞かせて下さい。
河北 大きな流れが2つあります。1つは1990年頃から、この30年を超えるデフレです。別の言い方をすると、30年間、日本経済は停滞したわけです。日本のGDP(国内総生産)も、この30年間、ほぼ横ばいの状態が続きました。
医療は高齢化が進む、あるいは医療技術が進むということで多少のプラスがありましたから、30年間、医療業界はこの状況の中で黙っていたんです。
ところが、そこにコロナ禍が起き、全世界的にいろいろなことがさらに停滞しました。それが22年になり、コロナが終息し始めた時に、米国の経済からインフレが始まり、このインフレが大きな影響を及ぼし始めているというのが現在の状態です。
─ そこに米国ではトランプ大統領が登場しました。
河北 はい。トランプ大統領によって今後どうなるかはわかりませんが、米国はものすごい経済力を持っています。いくら貿易収支が赤字であっても巨大な経済が動き、そこに周辺国が貿易として連なっているというのが今の世界の構図だろうと思います。
日本も貿易国として輸入も輸出も依存している中で、その影響から日本でも物価が上がり始めており、賃金を上げなければならなくなりました。しかし、賃金が物価の上昇に追いついていないことから、今の日本はスタグフレーション(不況下の物価高)に近い状況になってしまっています。
その流れの中で、社会保障、消費税を含めて、今後医療行政をどうカジ取りしていくかは非常に難しいことだと思います。ですから、少なくともインフレ局面ではGDPの伸びに沿った医療費の財源を確保することは当然だと思うんです。
インフレの伸びに沿えば、物価、賃金の上昇をある程度吸収できるだろうと思いますが、その前の30年間のデフレの中で失われた社会保険、診療報酬を上げる交渉は、ほとんど無意味です。何%上げるかではなく、インフレになったら必ずGDPの伸びに沿った財源を確保しなければ医療はもたないと思っています。
─ 河北さんが、そのように考える理由は?
河北 実は高齢者医療は頭打ちになり始めています。高齢者は今後、多少増えた後、団塊の世代が亡くなり始めると減っていきます。高齢社会イコール医療費が伸びるという構図は、もうありません。
もう1つ、本当に高額な医療技術を、社会保険できちんと収載するかどうかという議論は、やった方がいいと思っています。
そして、先程お話した中でのもう1つの大きな流れは5000年の歴史の中にあります。1991年9月にオーストリアとイタリアの国境にある氷河の中から「アイスマン」、通称「エッツィ」と呼ばれるミイラが発見されました。
このエッツィは、5300年前に生きていただろうと推定される中背で筋肉質の男性です。おそらく狩りをしていた人だろうと見られています。
5000年前の生活ですから、山を走り回って、獣を捕らえ、それを食べていたのでしょう。また、農耕をやっていて、小麦を育て、パンを食べた形跡があるとも言われています。
狩りをして、集団生活をしているのであれば、部族同士で戦って怪我をすることもあるわけです。その生活の中で、人間の身体は、それに対応して発達をしているわけです。
5000年前から今に至る人間の変化は?
─ 人間の身体は、その時代に合った発達をしているということですね。
河北 そうです。走り回るために筋肉が動かなくてはなりません。筋肉が動く最低限の要素として血糖値が高くなければいけません。体内で糖分をつくり、エネルギーを産まなくてはなりません。
もう1つは血圧が高くなければ動くことができません。そのためには塩分が必要で、腎臓の塩分再吸収能力が、血圧を保つことにつながります。
また、清潔な環境ではありませんから、獣からの感染、全く未知のウイルスからの感染に備えて、自分の防衛機能として免疫力を維持する力が生きていく中で作られてきています。
もう1つ、怪我をすると血液が流れますから止血しなければなりません。エッツィを解剖してみると、できるだけ早く血液が止まる機能が、その時代の人間の身体の中にもあったのです。こうした機能で人間の身体は支えられ、守られてきているということなんです。
─ 今の我々と同じような機能を、当時の人間も備えていたと。
河北 はい。そのままほぼ変わらずに4000年、3000年、2000年、1000年、紀元を迎えて、今の2025年まで来ています。
そして今から160年ほど前に産業革命が起きました。それ以前の人間の生活は、自然の中で作物をつくり、獣を獲りという生活をしてきたわけです。
産業革命以降は、物を大量に作り、貿易が盛んになり、植民地をつくりという動きが強まります。蒸気機関ができ、電気、ガスといったエネルギーも作られるようになるなど、人間の活動が大きく広がっていったのです。
それによって、大気中の二酸化炭素濃度が上がってきています。それから生活が安定し、食生活が変わり、清潔な環境、教育レベルの向上など人間の生活は大きく変わってきていますが、人間の身体は5000年前とそんなに変わっていません。
先ほどお話した通り、河北病院は1928年に祖父が創業した病院です。そこから太平洋戦争に敗れるまでの日本人の平均寿命は、おそらく50歳代だったと思います。
その一番の原因は感染症です。結核を代表にして、感染症に耐える力がありませんでした。当時は抗生物質が発見されていませんでした。
抗生物質は1928年から1930年頃に発見され、使われ始めたのが戦後のことです。抗生物質には細菌を殺す力がありますから、結核を含め、感染が抑えられるようになりました。
─ 抗生物質の発見で日本人の寿命が伸び始めたと。
河北 もう1つはレントゲンです。レントゲンによって、人間の身体の中を診ることができるようになり、診断能力が格段に高まりました。抗生物質とレントゲンという2つの要因で人間の寿命が伸び始めました。
そして、人間の寿命に大きく影響するのが食生活です。戦後には豊かな食事を食べることができるようになってきました。そして生活環境が清潔になり、教育水準が高まりました。
それに加えて、わが国では1961年に「国民皆保険制度」という社会制度を構築しました。これは誰もがいつでも、同じ価格で何回でも医療にかかることができるような環境を実現したのです。
こうして日本人の平均寿命は伸び、あっという間に今の男性81歳、女性87歳という、世界でも最も長い平均寿命を実現しました。
身体が変わらない中で生活習慣が変わった
─ 長寿化の中での医療を考える必要が出てきました。
河北 その通りです。80歳を過ぎた平均寿命の中で、皆さんが恐れているのはがんです。ただ、がんは「現象」です。高齢社会はがん社会なんです。
この現象に対して、今までと同じようにがんを撲滅する、強い薬で殺してしまえばいいのか。高齢者では、がんを殺してしまったら、それ以前に本人が亡くなってしまいます。
ですから、高齢者はがんと共存していくような治療を考える必要があります。その人が天寿を全うできるように、がんと付き合う医療が必要です。それが、我々が今後、やっていきたいがん治療の姿です。
その人らしく生き、がんと付き合うような医療が必要です。例えば、ノーベル賞を取るような発見で作られた薬や手段でがんを殺せばいいかというと、決してそんなことはありません。
─ 新しい時代の中で医療のあり方も変わってきますね。
河北 先ほど、ミイラの「エッツィ」の話をしましたが、身体がそれほど変わらない中で生活習慣が変わりましたから、血糖値を上げようとしたら糖尿病になり、塩分を取り過ぎれば高血圧になり、止血が行き過ぎると血管の中で血液が固まり心筋梗塞、脳梗塞になります。
さらに、清潔な環境の中で免疫力が逆に作用し始めて、アナフィラキシーショックやコロナ禍でのサイトカインストームのような免疫疾患も出てきています。
5000年前によかれと思ってつくってきた人間の身体が、ガラッと変わった生活習慣の中で多くの病気を招くようになりました。そういうことを考えるのが私の役割です。社会病理として社会と医療を結びつけるということです。
新しい病院をつくるにあたって、いろいろなことを組み合わせてみると、このような結論に至ってきました。その裏にあることはとても大切で、医療だけでなく全ての経営者にとって経営とは何かというと「つなぐ」ことだと思います。
─ 河北さんは何をつないでいきますか。
河北 人と自然と社会をつなぐ。違う次元のものをつないでいく。何を元にしてつなぐかというと全て「情報」です。アップル創業者のスティーブ・ジョブズも「Connecting the Dots」と言っています。
点をつなげば線になり、線が広がると面になる。私はその面を縦に延ばし、3次元の空間にしなければいけませんし、最終的には思想と時間を加えれば社会という、4次元になります。経営というのはそういうものだと思うんです。
私はシカゴ大学で経済学を学びましたが、「社会的共通資本」を唱えた宇沢弘文先生を尊敬しています。その弟子である岩井克人先生が宇沢先生を評して「冷徹な頭脳より暖かい心」と表現していますが、私は医療の世界で、その流れをつくっていきたいと思います。