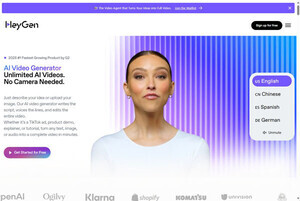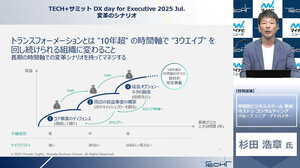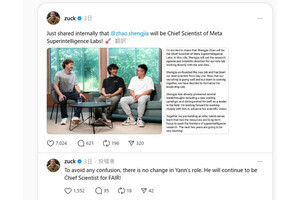「がん保険にとどまらず、お客様をトータルに支えていく」─古出氏はこう力を込める。日本で「がん保険」領域を開拓してきたアフラックが2024年、日本での創業50周年を迎えた。がんが不治の病とされていた時代から、新たな市場を切り開いてきた。そして今、保険に加えて相談サービスや資産形成など、顧客をトータルで支える取り組みに注力。そのために、経営スタイルも変革している。古出氏が語るアフラックの今後は─。
金融市場の変動があっても持続的にサービスを提供
─ 米トランプ大統領の政策、動向で世界の政治、経済に様々な影響が出ています。どう見ていますか。
古出 トランプ政権の動きは予測が難しく、大統領の発言などで金融市場も影響を受けるような変動の激しい時代です。
関税の引き上げを材料に各国と交渉するという手法ですが、これによって米国内のインフレと景気減速のリスクが高まりますし、輸出や投資を通して米国と結びつきが強い国や企業にも直接・間接的な影響が出ることが想定され、日本を含む世界経済全体へのマイナス影響が懸念されます。
今のトランプ政権には、長く続いてきたグローバルな貿易体制を変えようという考えが根底にあるとも言われていますが、確かに私にも、トランプ政権は世界経済の構造を自国により有利な形へとリセットしていくことを目指しているように思えます。
それゆえ、日本として、自国の経済を持続的に成長させていくために、国内外においてどういう政策を行っていくのか、また新しい国際経済体制の中でどういう役割を果たしていくのかなど、さまざまな見直しを迫られていると思います。
─ こうした混沌期での生命保険の役割をどう考えますか。
古出 生保は長期にわたってお客様に安心をお届けするビジネスです。当社もお客様にご加入いただいているほとんどの保険は終身保険です。
場合によっては50年後まで、アフラックを信頼し、ご自身の将来不安やリスクへの備えとしてご加入いただいていますから、長期的な視点で応えることが大事です。
金融市場の変動があったとしても、強固な資本、流動性を維持するためのリスク管理をしていく。そうした経営を続けることが、生命保険会社としてお客様に対するお約束を守るために重要だと考えています。
そして既存のお客様、これから加入してくださるお客様に対して、私たちの商品・サービスを持続的に提供していくことが使命だと思っています。
─ アフラックは50年前に、「がん保険」という当時新しい領域を開拓しましたね。
古出 50年前にはがん保険はなかったですし、がんという病気自体が不治の病だと考えられており、患者さんに告知もしていない状況でした。
その中で保険が成り立つのかと多くの人に思われている中、日本の社会で何とか、がんに苦しむ人々を経済的苦難から救いたいという日本における創業者の強い想いがあってスタートしました。これはコアバリュー(基本的価値観)の1つとして、当社にしっかりと受け継がれています。
がん保険が世の中に認知されていませんでしたから、がんになった時にどういう経済的負担が生じるのか、その備えとして保険が重要だということなど、がんに対する啓発と一緒に、がん保険の販売を進めてきました。がん保険市場を、私たちがつくってきたという自負があります。
─ 2024年に日本における創業50周年を迎えたわけですが、改めてどんな思いを持ちましたか。
古出 がん保険が日本にない中、新しい商品・サービスでマーケットをつくり、日本におけるがん保険市場の伸びとともに会社も成長することができました。50周年を迎えて感無量です。
がん保険ではリーディングカンパニーであるというプライド、実績がありますが、がん治療も日進月歩で変わっています。また、がん治療に関わる課題だけではなく、経済的な問題、精神的な不安、仕事の両立といった社会的課題もあります。
これらに対してトータルソリューションをお届けしたい、社会的課題を解決し、経済的価値を創出するCSV経営をこれからも実践していきたいと考えています。
具体的には、保険も単に経済的な保障をするだけでなく「よりそうがん相談サポート」という、我々の50年にわたる経験とノウハウを生かした相談サービスを始めており、保険と統合した形でお客様にお届けし始めています。
保障自体も、治療中だけでなく、罹患する前の精密検査から、治療が終わった後の相談も含め、「がんと共に生きる」部分まで、保障範囲を広げた保険となっています。
日本法人化でガバナンス強化
─ 古出さんは社長に就任して8年ですね。この間、印象的な出来事は?
古出 創業時は米国保険会社の日本支店でしたが、18年4月に日本法人化しました。お陰様で事業が拡大し、アフラックの収入で7割、資産で8割を日本が占めるなど、日本支店の方が大きくなりました。
それだけ、日本のお客様やマーケットにお応えできてきたということだと考えています。それだけに、日本法人として日本の会社法の下で強固なガバナンス態勢を構築する必要があると考えました。
もちろん、それまでも日本に根ざした経営をしていましたが、さらに深めて、日本でさらに成長していくためのステップにしようと。私としては、社長として日本法人化できたことは嬉しいことでしたし、法人化したからこそ、その後の成長も実現できたと思います。
法人化によるガバナンス強化で、さらに機動性を高めることができたと考えています。
─ コロナ禍は、会社にとってどういう経験でしたか。
古出 日本法人としての最初の試練でした。2020年からの中期経営戦略でビジネスを拡大していこうと思っていた矢先の出来事で、その後3年ほどは、その対応に費やしました。
ただ、その中でも会社が事業継続をしていくことに加え、変革を進めようと考えました。コロナの状況を踏まえた変革に加え、ポストコロナを睨んだ変革の布石を打っていこうということで進めてきました。
オンライン相談サービスも、コロナの時にいち早く取り入れたものです。厳しい状況の中でも、スピード感を持って変革を進めてきたつもりですが、当時はとにかく必死でした。
運用力を生かした資産形成商品も
─ アフラックの営業体制は、代理店が販売するモデルになっていますね。
古出 そうです。直接お客様に接するのは代理店の皆さんです。新商品が出れば、その内容を代理店に説明し、研修を行います。販売に課題があれば、我々が課題解決に向けてアドバイスをし、代理店のビジネスを伸ばせるように支援します。
日本で50年間ビジネスができ、お客様数で約1400万人、ご契約数で約2200万件という実績を重ねることができたのも、代理店もビジネスパートナーとして一緒に成長することができたからです。
─ 保険のあり方も時代に合わせて変えてきていると。
古出 ええ。当社はがん保険などいわゆる第3分野の保険をコアに事業展開をしてきました。そして「『生きる』を創る。」をブランドプロミスのタグラインとしています。
お客様1人ひとりの「生きる」をトータルに支えていきたいという想いで、がんを始めとする病気やケガ、介護、そして老後にまつわる不安、悩みの解決に取り組んできました。
その中で今、日本社会を見た時、高齢化の中で、いかに自分らしく生きていくかを考えた時に、大切になるのが資産です。健康とともに、資産寿命をともに延ばすという点で、資産形成が大きなテーマになっています。
日本政府も「資産運用立国」を掲げ、銀行、証券会社、資産運用会社、他の保険会社も資産形成に非常に注力しています。
その中で私達も、資産形成ニーズに応えていくことは「『生きる』を創る。」というブランドプロミスの実践に整合していますし、私達の強みを活かしてできることがあると考えました。
そこで24年に販売を開始したのが、私達の新たな資産形成商品「ツミタス」です。
資産形成と保障のハイブリッドで、契約時に将来受け取ることができる解約払戻金が確定するため、老後の備えとして、安定的な資産形成を希望されるお客様のニーズに応える商品となっており、想定以上の手応えがあります。
がん保険や医療保険に次ぐ、新たなコアビジネスにしていく上で自信を持つことができました。
─ 資産運用能力にも自信があると。
古出 はい。生命保険会社として長期運用に強みを持っています。お客様の保険料は円建てですから、円建ての負債に対するALM(Asset Liability Management=資産・負債の総合管理)のノウハウも持っており、競争力の高い長期の運用商品を提供できます。
例えばNISA(少額投資非課税制度)の運用対象は多くが株式や投資信託だと思います。リターンが大きい可能性もありますが、元本の変動はあります。その中で、ご加入時に利回りが確定する、変動のない、長期運用で、お客様に提供できる独自の価値があると考えています。
「アジャイル組織」で経営のスピードを上げる
─ 今後、さらに他の企業との連携が出てきそうですか。
古出 私達が中期経営戦略で掲げている目指す姿が「『生きる』を創るエコシステム」です。お客様の「『生きる』を創る。」をトータルでサポートしていく。
保険商品、相談サービスだけでなく、お客様をトータルに支えていくために、保険の枠を超えていろいろなプレーヤーと連携、協業することで価値提供をしていきます。
また、我々の事業展開において「アジャイル」(機敏)は1つのキーワードです。元々はITの世界の用語ですが、我々は会社の働き方全体に取り入れています。15年頃には他社を視察し、19年からアジャイル組織を正式に立ち上げています。
─ どういった組織体になっているんですか。
古出 従来はいろいろな部があり、会議をして持ち帰って、各部で上まで上げて承認を取ってというのを繰り返していましたが、アジャイル組織には大胆に権限委譲しており、各部から人を出してもらって、そこで決められるようにしています。
専門知識を有する各部署のメンバーを集めていますから、意思決定のスピードが大きく早まりました。
しかも、事業を進めながら結論を出し、すぐにマーケットに出し、そのフィードバックを得て改善します。その改善のサイクルを非常に早めているんです。以前の3年といった計画では、サービスを提供した時には世の中が変わっています。
それをアジャイルで数カ月単位の計画とすることで、外部の環境変化や、我々が出したサービスがお客様やマーケットに響いているかを確認しながら、高速で仕事を回しています。
─ 顧客の反応を即座に掴むこともできると。
古出 そうです。19年に、がんに関するエコシステム構築に向けて全社横断的なプロジェクトから進めてきましたが、25年1月からは中核組織であるマーケティング営業部門をアジャイル組織に変えました。
これは生保業界でも、他の業界でも、あまり例がないと思います。徹底的な顧客視点で、環境変化に迅速に対応できる体制にしています。
経営のスピードに加え、社員のエンゲージメントも上がっていますし、取締役会と業務執行部門の関係を含め、経営自体がアジャイルになっています。そして私達は「計画」ではなく「戦略」という言葉を使っていますが、これはアジャイル経営の表れです。
その前提として、その戦略が「骨太」でなければいけません。骨太な戦略がないところにアジャイルを持ち込んでも、外部環境に惑わされてしまいます。25年からの中期経営戦略も1年間かけて議論をしてきました。
米陸軍元帥まで務めた第34代大統領のアイゼンハワーは、計画以上にその策定プロセスが大事だと言っています。我々も議論を通じて、経営チームが戦略の内容について深い理解とコミットメントを持っていますから、アジャイルな経営が可能なのです。