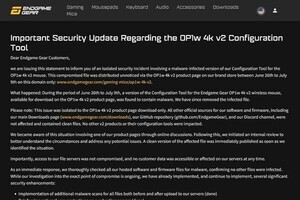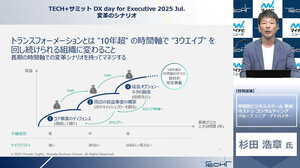マルチクラブオーナーシップ戦略に挑戦
ONODERA GROUP(オノデラグループ2025年3月期売上高1559億円)が、同社のスポーツ事業であるサッカークラブの経営で日本初の取り組みを進めている。
同社は2005年からサッカークラブ・横浜FCに資本参加し、2024年に同チームはJ1への昇格を果たした。しかし、クラブの経営の安定は大きな課題となっている。同クラブだけでなく、日本のサッカークラブの多くは親会社に頼り赤字補填をしている状況が続いている。
同グループのスポーツ事業の売上は33億円で、広告収入やチケット収入は興行収入として上がっているものの、シーズンによっては選手の強化費が増加し、経営を圧迫している。実際は、成績により賞金の有無、移籍金にも左右されるため年によって経営は不安定な状態にある。
このスポーツ事業を親会社に頼ることなくしっかりと自立させるため、同社が取り組むのがマルチクラブオーナーシップ(MCO)という手法だ。MCOはサッカーの本場・欧州では既に一般的で、1つのオーナーが国籍の異なる複数のサッカークラブを所有し、経営効率を高めるというもの。海外のクラブを持つことで、同オーナーの中で若手選手を移籍させ、海外での出場経験を積ませることができる仕組み。グループ内で選手の特徴やパーソナリティを把握した上で移籍させることができるため、移籍金等のコスト、移籍先でのミスマッチを防げ、総合的なコストパフォーマンスを高めることができる。
昨今外資系企業はこの仕組みを利用し、日本のサッカークラブを買収している。昨年はレッドブルグループ(オーストリア)が、大宮アルディージャを買収した。こうした企業は各国にクラブを複数持ち、人材の市場価値を高め移籍金で収益を得るというモデルを確立している。
同社は日本で初めてこの手法に挑戦しようと、22年11月、ポルトガルのクラブ・オリヴェイレンセの経営権を取得した。現在日本とポルトガルの2拠点でチームを運営し、その中で若手選手の育成強化することで、少しずつ実績が出始めている。
2024年の移籍金収益は、21年比の約2倍の4億円に増加した。現在も有望な選手は多く在籍し、例えば18歳で横浜FCからオリヴェイレンセに期限付き移籍した永田滉太朗選手は、海外での試合に出場し約90分の出場で4400万円の市場価値がついている。横浜FC・MCO事業部長の松本雄一氏は、「日本サッカー界では若手選手の公式戦の出場機会が圧倒的に少ないことが課題で、欧州の市場で試合経験を積ませることで、選手の急速な成長と市場価値を高めることが可能。シーズン後には永田選手には倍以上の価値がつく可能性もある」と話す。永田選手をモデルケースにし、今後も海外で活躍できる選手を継続的に輩出したい考えだ。
日本サッカー界の課題
松本氏は日本サッカーの課題を次のように語る。
「日本では経験のあるベテラン選手や即戦力の外国人選手が多く起用され、21歳以下の若手日本人選手の出場機会が不足している。日本では選手を人件費としてみる考えが未だに根付く一方で、海外では選手を資産としてみており、ベテラン選手と若手選手で実力が同じくらいであれば、若手を試合に出し市場価値を上げようとする。この考え方の違いにより、選手の経験値も、動くお金の規模も欧州と大きな差が生まれている。日本で同社がMCOの仕組みを持つことで、若手選手に出場機会を与えると同時に、選手の市場価値を高め移籍金をクラブ経営の収益の柱に加えていきたい。最終的には経営の安定化によりチームを更に強くし、日本サッカーの強化・発展に貢献したい」
日本のクラブ経営においての収益は、広告スポンサー料、入場料、物販、放映権で構成されている。昨今、FIFAワールドカップ(W杯)は放映権料の高騰で、日本の民放はテレビ中継ができなくなってきている。
これまではNHKと民放5社などで共同負担し中継する仕組みがあったが、22年大会は民放数社が撤退。一社あたりの負担が大きくなり、将来的な地上波での放映も危ぶまれる。もはやサッカーは有料動画配信のスポーツ・チャンネル「DAZN(ダゾーン)」で試合を観るのが一般的になりつつある。そうなれば、大衆的な盛り上がりは減少し、日本のサッカーへの興味は徐々に衰退していく可能性も考えられる。
放映権が収益として縮小する中で、収益アップの可能性として着目したのは移籍金と連帯貢献金。同社が取り組むこのMCO戦略により、中長期的に選手の市場価値を高め、移籍金を収益の柱にできるかが事業安定化において鍵となる。
Jリーグの2024年度売上総計(柏、湘南を除く)は過去最高1649億円。日本サッカー市場全体は成長軌道にあるが、世界と比較すればその市場規模は小さい。世界一の収益を誇る欧州のクラブ、レアル・マドリードは、23―24年シーズン1チームで10億4550万ユーロ(約1672億8000万円)を稼いでいる。ここから見れば、日本のサッカービジネスはまだ大きな伸びしろと可能性を秘めている。
MCOはコストも時間もかかり、不確実性・不透明性が高く、日本ではまだ普及していない。新たな収益の柱をつくり、クラブ経営の安定化でクラブ強化と人材育成を目指すオノデラグループ。この挑戦が実り、日本サッカーの発展につながる日が来るのか注視していきたい。