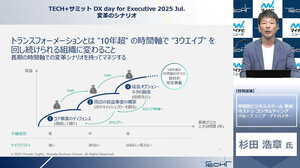戦後の国際金融秩序は、覇権国である米国のドルによる単一基軸通貨体制に支えられてきた。米国の圧倒的な経済力と軍事力、流動性と深みを備えた金融市場、さらにその政治的安定性は、ドルを貿易決済や準備資産、或いは、国際投資(国際金融)の中心に据える構造を正当化してきた。
しかし、購買力ベースでみると既に米国の経済規模は中国に劣る。軍事力でも質・量ともに中国の追い上げが著しく、核戦力においても中国は本格的な増強期に入っている。経済力や軍事力というハード・パワーでは、もはや米国の優位は不動とは言えない。
それでも従来は、故ジョセフ・ナイが説いたように、米国は圧倒的なソフト・パワーでそれを補っていた。多様性を尊び、文化的魅力に富み、世界中から学生や研究者を惹きつける大学・研究機関を擁し、法の支配と自由民主主義を基盤とする価値観など、国際政治における「共感と説得の力」の源泉を米国は保持していた。むしろソフト・パワーこそ重要と考えられていたが、その基盤をトランプ政権は破壊しているように見える。
ドルによる単一基軸通貨体制―すなわち、米国の覇権システムの一環として構築されてきた国際金融秩序―がもたらす米国の利得は今も相当に大きい。しかし、問題は、その利得がITや金融といった特定のセクター、あるいはグローバル・エリート層に集中し、再分配を通じた国内における覇権の正統性の維持が困難になっている点だ。関税で海外にコストを課すことで、解決し得る問題ではない。
覇権維持には海外との関係だけでなく、それを支える国内の正統性が不可欠なのだ。筆者は、国内分断の修復は困難であり、米国の覇権と共に、ドルの単一基軸通貨体制は、終わりの始まりに差し掛かったと懸念している。それでは、今後どのような国際通貨制度に向かうのか。
理屈上、三つの代案が考えられる。一つ目は、覇権も制度も欠如した無秩序なGゼロ的世界だ。1930年代のような世界的混乱が繰り返す可能性がある。二つ目は複数基軸通貨制で、ドルやユーロ、人民元、などが並立し、現実的な制度移行の中間案としても有望だろう。三つ目は、44年に戦後の国際金融制度を設計したブレトンウッズ会議で、イギリス代表の経済学者ケインズが提案した仮想決済通貨のバンコール型だ。基軸通貨国の特権を許さない民主的制度だが、ハードルは高い。
なお、通貨制度の移行には長い時間を要する。皆が使うから自分も使うというネットワーク外部性は大きく、また米国の金融市場の利便性は突出しており、制度的補完性もあって移行コストが大きいため、数年単位の慣性が働く。
ただ、現在のドル体制の制度的信認は、多分に「市場の期待」というソフト・パワーが支えているため、新制度への移行は、ポンドからドルに移行した30、40年という時間より短くなる可能性がある。