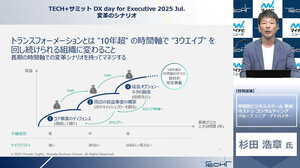新需要を創造する 商品開発
─ 物価高が続いている中で実質賃金はマイナスの状況です。その中でどう需要を掘り起こした商品開発を行っていますか。
勝木 世の中、食品を中心にほとんどのものが値上がりしている状況の中で、消費者の可処分所得については、賃上げが活発化しているとはいえ、まだまだやインフレに実質的に追いついてないというのが現状です。消費者の財布のヒモは依然として引き締まっていると思いますが、そこに対してわれわれは、商品およびサービスの質を高めていくことでご理解をいただきたいと考えています。
日本でいえば、4月に『ザ・ビタリスト』という、レギュラーのビールとしては7年振りの新商品発売をしました。酒税の一本化の中で、消費者の方はいろいろなものを併飲する方が増えて来ています。新ジャンル、発泡酒からビールに移る過程で、ビールもいろいろな商品を試してみたいという声が多いです。
どうしてもスーパードライ、あるいはアサヒ生ビールだけでは、取り込み切れないお客様に、当社の商品を楽しんでいただきたいということで新たに出すのが『ザ・ビタリスト』という商品です。適度な苦味と爽やかな香りが特徴です。こういった商品をこれからも出していきたいと思っています。
─ 定番商品のスーパードライについてはどう販促していきますか。
勝木 スーパードライについては、今年は〝冷え〟というのをキーワードにして価値を高めていこうと思っています。
飲食店さんでも、当社のビールの温度を4度未満で提供していただいている店には、「スーパーコールド認定店」を付与し、冷えたビールをお客様に楽しんでいただく取り組みを進めていきたいと思っています。
「スーパードライは冷えているほうが美味しい」という声も多く、調査をしてみると生ビールの美味しさの価値として、〝冷たい〟というのが非常に支持されていることがわかりました。この〝冷え〟の価値を高めて展開すると。缶タイプにおいても、最適な温度に冷えていることが色でわかるような仕掛けであったり、それを注ぐ用の専用タンブラーも展開しています。
─ それから、総合飲料の業種であることが、多様なニーズに応えられるということにもつながりますか。
勝木 そうですね。お客様を見ていく時に、健康志向と消費志向の多様化というのが確実に見て取れるようになってきています。消費者の方々に対して、様々な美味しさや価値を提供することは、今後大事なことであると思っています。
─ 売上は国内と海外では現在半々の割合ですが、国内市場は人口減、少子高齢化となりますがこの中でどう需要を掘り起こしていきますか。
勝木 当社のような大衆消費財企業である限り、人口の減少には抗えない部分はあると思います。その中ですべきことというのは、価値を高める、これに尽きると思います。
アサヒビールで取り組んでいるのは、スマートドリンキングという戦略で、これは2020年から進めている戦略です。現在日本の20歳以上の人口は9000万人、そのうち2000万人が、ほぼ毎日のようにお酒を飲まれると。さらに2000万人の方が月1回2回程度飲まれると。残りの5000万人の方は、ほとんど飲まないか、飲めないという方です。
ただ、そうした方々も、お酒のある場が好きだったり、人とのいろいろな触れあいやコミュニケーション、つながりというのは好きだという方々で、決してお酒のある雰囲気が嫌いなわけではないということがわかっています。
そういう方たちが、気持ちを上げたいとか、逆に落ち着きたいというときもあるわけですね。そのときに、われわれがそこに対する提供価値が今までありませんでした。
─ 酒を飲まない、あるいは飲めない方への配慮ですね。
勝木 ええ。例えばそういう方々が宴会やご自宅で飲まれるものは従来、ウーロン茶やコーラといった選択しかなかったんですね。何かこう特別なものを飲みたいと思っても、われわれは提供できていませんでした。そういうニーズに対し提供する商品として、われわれはスマドリという概念を持ち出しました。グローバルには Beer Adjacent Categories (ビール隣接)という形で、ノンアルコールのビールや、低アルコール飲料、あるいは大人向け清涼飲料(アダルトソフトドリンクス)といった、美味しくて贅沢な気分を味わえて、しかも健康にいいといった、こうした商品を展開してきて、着実に裾野が広がってきました。
─ 性別、国問わず、そういった需要はあるんですか。
勝木 ええ。世界的にそういう需要は間違いなくあります。われわれは海外の競合と比べて、酒類と飲料という両方の知見、ケイパビリティを持っています。競合の世界大手ビール会社で、飲料のケイパビリティを持っている会社はありません。
飲料はわれわれのトータルのビジネスの中で、約4分の1を占めます。日本とオーストラリアでいえば、だいたい売り上げの3割が飲料ですが、ボリュームは酒類と同じぐらいです。このケイパビリティを生かしていきたいと考えています。
飲料分野は絶対これから伸びるマーケットです。ここは非常に期待を懸けています。事業ポートフォリオ戦略の中でも、Beer Adjacent Categories (ビール隣接領域)をドンと構えて置いています。
─ ビールだけでなく、より広範囲で攻めていくと。
勝木 そうしていきたいと考えています。グローバルの執行体制の中で、エグゼクティブコミッティ(=ExCom)という従来の経営戦略会議と呼んでいたものに、グローバルの各地域統括会社のCEOも連れてきて、全体最適を話し合うという体制にしました。
各地域の単純な合計を超えた企業価値を生み出していこうという趣旨でやっています。そこでも主要な議題として Beer Adjacent Categories を推進していこうという話をしています。アサヒグループジャパンにも、酒類と飲料をまたいだマーケティングや商品開発を行うという部署を新設しました。
─ まだまだ市場は掘り起こせるということですね。
勝木 ええ。いま現段階では、そうした商品やサービスは、そんなにメジャーではありません。ですからブルーオーシャンといいますか、これからこの市場を創造していけると思っています。
加えて、南アジア、インド、パキスタンなども、これからの市場に成り得ると思っています。それを含めると人口20億人以上、27億人ぐらいですかね。ここにまだ着手できていませんでしたので、これから本格的に力を入れて行こうと。
─ アメリカはどう考えていますか。
勝木 アメリカはわれわれにとっては、ずっとミッシングピースになっています。アメリカはビールでも大規模な展開ということがなかなか難しいのです。大手のビール会社もいらっしゃるので、なかなかスピーディーには進められないというところではあります。
ただ、オーガニックにスーパードライを伸ばしていこうということで引き続きコツコツと積み上げていきたいと考えています。ちょうど去年、アメリカの飲料製造受託のオクトパイ・ブルーイング(ウィスコンシン州)を買収したんです。この3月末からスーパードライの製造を開始しています。ですからトランプ関税の問題に対しては、タイミングが良かったんです。
─ 中国市場についてはどう考えていますか。
勝木 中国については増やしていきたいと思っています。いま現在では、大都市の北京、上海、深圳、広州。この辺りを中心にスーパードライは伸びてきています。
実際、スーパードライの販売量でいうと、一番多いのは韓国ですね。韓国、中国、オーストラリア、UKと。この順番です。
各国の従業員との対話に手応え
─ 4年間社長をつとめられ嬉しかったことはありますか。
勝木 就任後コロナ禍の影響ですぐには各事業所をまわれなかったんです。2022年の6月から出張ができるようになってまずやろうと思ったのが、日本全国、世界各国の事業所をまわることです。従業員に対して、私が何者であって、何がしたくて、どんな未来に従業員と一緒に行きたいのかということをテーマに、タウンホールミーティングを70回ほどやってきました。
そこで従業員の意識が高まっている、いわゆるエンゲージメントが高まっている手応えを感じることができたのが嬉しかったことですね。会社とのつながりであるとか、会社の戦略、会社に対する共感、そういうのが高まってきていると感じております。
─ 具体的にはどういったところでそう感じましたか。
勝木 やはり、一つには、事業ポートフォリオ戦略の中で、Beer Adjacent Categories の、低アルコール、ノンアルコール、健康志向というところを狙っていくべきという、われわれの本質的な提供価値について若い人が真剣に考えてくれています。
彼らがいうのは、われわれは、お酒に関する楽しさ、豊かさとかうるおいを知り尽くしていると。これを、もっともっと広く消費者にお届けしたいんだと。
それこそ、若い人と対話するときには、ある種カマをかけるときがあります。例えば、アメリカの経済学者ミルトン・フリードマンは「企業の唯一の社会的責任(only one social responsibility)は利益の創出である」ということがあるけど、最近どうもそうではないよね。それに対してどう思う? と問うと、彼らは、われわれのパーパスは顧客価値を高めることだと。そして顧客価値はもちろんサスティナビリティと連動したものでなければいけないと。
地球は1つなので、われわれの活動はそうした世の中の持続性を高めるために事業活動を行わなければいけないと。そういうようなことが若い人の言葉として出てくる。若い人に限りませんが、従業員にそういう意識が高まってきている。この会社は、あと30年や50年は絶対大丈夫だなと思っています。
先輩たちの背中を見て…
─ 先輩経営者から学んだことはどういったことですか。
勝木 歴代の社長の方々のことを振り返ると、ある問題が起きて八方塞がりになったときに、池田弘一さんに報告に言った際「俺はなんとかなると思う。こういうときはなんとかなるんだ」と言っていたのがすごく印象深いです。軸が決まってさえいれば、要は努力すればいいだけだと。そう言われたらこちらもやり抜かねばという気になりますしね。
やはり修羅場の経験をいかにしてきているかで、人は強くなるんだと思います。瀬戸雄三さんもその最たるもので。もうどうしようもない、絶体絶命だというピンチを、何度も乗り越えた。そういう人たちの信念や嗅覚は凄いなと。
─ 修羅場は、ある意味で人を磨きますね。勝木さん自身もニッカから来られて、修羅場を経験されたのでは。
勝木 わたしは救ってもらいましたので、当社の包容力がある社風があったからこそやってこれたと思います。
─ 社長からご覧になって、伸びる人はどういう人ですか。
勝木 当事者意識を持って逃げない人ですね。自分で考え行動すると。会議なんかでも、結論が出そうにないようなときに、黙っている人と、そうではなくて、なんとかまとめて結論を導こうとするような人がいると思います。それこそさっき申し上げた先人の経営者たちのように、自分がなんとかしなければと思うような人は伸びると思います。