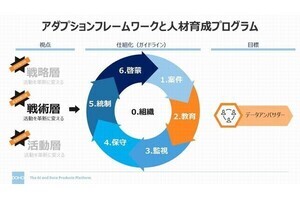4月23日~25日の期間で実施されている「第16回 EDIX(教育総合展) 東京」。同展示会は、学校・教育機関、企業の人事・研修部門など教育に関わる人に向けたもので、教育DX(デジタルトランスフォーメーション)につながる機器や授業で使える製品を持った、さまざまな企業の出展が行われている。
同展示会において、Amazonは4月24日、楽しみながら学ぶ教育手法「エデュテインメントで切り開く子どものモチベーション」をテーマに、「エデュテインメント」の最新動向や実践例、サブスクコンテンツ『Amazon Kids+』を中心としたAmazonの取り組みについて説明するセミナーを実施した。
同セミナーには、立命館小学校 教諭 正頭英和氏、アマゾンジャパン Amazon デバイス事業本部 Kindle・Fire タブレット・アクセサリー事業部 事業部長の丸山舞氏、ケシオン 企画部 マネージャーの岡本治樹氏が登壇した。
「桃鉄 教育版」が具現化する「エデュテイメント」とは
今回のセミナーのメインテーマである「エデュテイメント」は、教育を意味する「エデュケーション」と娯楽を意味する「エンターテインメント」からなる造語。学習要素と遊びが組み合わさったコンテンツを指した言葉で、楽しい体験を通じて自然と知識を身に付けていけるという特徴を持ち合わせている。
最初に登壇した正頭氏は、この「エデュテイメント」について、「とりあえずやってみるのハードルを下げることが重要」と説明した。その例として正頭氏が挙げたのが、自身がエデュテイメントプロデューサーを務めている「桃鉄 教育版」だ。
「桃鉄 教育版」は、2023年初頭から学校教育機関への無償提供が開始されたエデュテイメント教材。「日本全国を巡って物件を買い集め、資産額日本一を目指す」という「桃太郎電鉄」のゲーム性を生かして、全国各地の名産・名所などを遊びながら身につけられるだけでなく、難読地名の書き取りや収益率の計算など、さまざまなことが学べる。
通常のゲーム版と比べて、学びたい地方を限定してプレイしたり、情報表示機能の搭載、生徒同士のトラブルにつながる可能性のある「貧乏神(誰かが目的地に着いたタイミングで最も遠い場所にいたプレイヤーに取りつき嫌がらせをするキャラクター)」の仕様を廃止したりするなど、教育版ならではの特徴を備えている。
さらに「桃太郎電鉄 教育版」を通して得られた学びをより深めることができる機能として、任意のマスを物件駅として自由に編集できる「マイ桃鉄」機能が追加された。
自分たちで調べた町の魅力を、観光名所や会社、工場、農産・水産などを、さまざまな物件として、桃太郎電鉄 教育版の中で表現することで、学びの結果をクラスメイトたちと共有することが可能になり、授業を通じて、楽しみながら地元やその他の地域を知ることができるようになったという。
また桃鉄 教育版は、これまで学校教育機関・自治体のみの申し込みを受け付けていたが、5月から全国のフリースクールなどの教育機関からの申し込みが可能となるという。
Amazonが考える「エデュテイメント」
続いて登壇した丸山氏は、「Amazonデバイスが考えるエデュテイメント」という内容で、「Amazon Kids+」について説明した。
「Amazon Kids+」は、3歳~12歳を対象とした、子ども向けデジタルコンテンツのサブスクリプションサービス。「遊んで、考えて、学ぼう」をテーマに、アプリ・本・ビデオ・音楽などのコンテンツが用意されている。
Amazon Kids+は、2012年に米国でローンチされたことを皮切りに、2014年には「Fire Kids Eduition」がリリースされ、日本では2019年から「Fireキッズ・Kindleキッズ」がリリースされた。
さらに、小学生向けプログラミング学習アプリ「プログラミングゼミ×鬼滅の刃」の独占提供や、朝日小学生新聞との提携、2024年にはFire HD 8 キッズモデルとFire HD 8 キッズプロがリリースされるなど、サービスの展開を広げている。
丸山氏はAmazonが大切にしていることとして以下のように語った。
「Amazon Fire キッズタブレット・Amazon Kids+を通して、1人ひとりのお子さまの成長や可能性の芽を伸ばしていきたいと思っています。そのために『自発的な活動を通しての学び』の機会を増やし、お子さまの『好き』や『得意』という秘めた可能性を容易に見出せるような機能や、保護者の方が安心して見守れる機能を提供し続けていきます」(丸山氏)