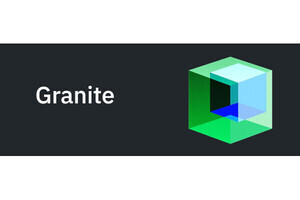日本IBMは3月26日、オンラインとオフラインのハイブリッドにより、報道関係・ITアナリスト向けにAI&データプラットフォーム「IBM watsonx」などAI製品に関する説明会を開催した。
2025年は生成AIの活用が本番展開
はじめに、日本IBM テクノロジー事業本部 Data and AI エバンジェリストの田中孝氏はIBMが捉えるAIの現在地について説明した。同氏によると、多くの企業が過去1~2年かけて生成AIの活用に取り組んできたが、その取り組みのまま本番業務で使うことが本番展開ではないと指摘。
そのうえで田中氏は「2025年は生成AIの活用が本番展開の時代を迎える。過去、初期検証やRAG(検索拡張生成)など生成AIの活用に取り組んできたが、今後はより業務に密接にかかわる領域、例えばIT運用の自動化やAIエージェントに代表されるようなタスクの自動化まで進む」との見立てだ。
同社では、従来から提供している複数サービスとの連携を可能とした業務マイクロサービス基盤「DSP(デジタルサービスプラットフォーム)」にAIの組み込みを進めている。これは、ハイブリッドクラウド基盤にコンテナ基盤「Red Hat OpenShfit」とIaC自動化基盤であるHashicorpの「Terraform」上に構築されているDSPを拡張し、「AIプラットフォームサービス」の提供を予定。
同サービスはAIアプリケーション基盤やAIエージェント共通基盤、AIゲートウェイ、AIモデル管理(LLM)基盤、AIセキュリティ/ガバナンスで構成している。同氏は「AIの活用は単独で存在するものではない。さまざまな業務の中にAIを組み込んでいくことを考え時にIBMとしては、それをしっかり支えるAIのプラットフォームの構築を支援していく。このプラットフォームに則ってAIの提供を広げていくことが当社の大きな狙い」と話す。
IBMが重視するAIエージェント、アシスタント
こうした動きを踏まえ、watsonxと「IBM watsonx AI Assistant」について話は移った。watsonxは、AIモデルのトレーニング、検証、チューニング、導入を行う「watsonx.ai」、あらゆる場所のさまざまなデータに対応してAIワークロードを拡大するwatsonx.data、責任と透明性があり、説明可能なデータとAIのワークロードを実現する「watsonx.governance」の3つのコンポーネントで構成し、Red Hat OpenShiftによりクラウド、オンプレミス、エッジ環境でも動かせる。
また、watsonx AI Assistantは、AIでデジタルレイバー(自動化ツールやAIを利用して作成されたソフトウェアロボット)をオーケストレーションする「watsonx Orchestrate」、バーチャルエージェントの「同 Assistant」、「同 Code Assistant」、メインフレーム「IBM Z」のCOBOLをJavaに変換する「同Assistant for Z」、「同BI Assistant」で構成。
このように、同社は生成AIの本番展開を見据えたソリューション群を提供している。田中氏は「お客さまの個々の課題やユースケースに合わせて、AIをカスタマイズして業務をフィットさせることが重要。昨今、トレンドにもなっているが、現在IBMとして重視しているものがAIソリューションを構築する際のUI/UX、つまりエージェント、アシスタントと呼ばれるような領域だ」と説く。
ユーザーとの接点となるフロントエンドのみならず、LLM(大規模言語モデル)やLLMの開発やカスタマイズするために必要となるデータ、運用時のガバナンスなどをIBMでは本番展開を支援していくうえで重視しているという。
IBMではwatsonx.aiにおいて、さまざまなLLMを提供している。そのうちの1つに同社が独自開発し、2023年9月に提供開始したオープンソース化された独自の基盤モデル「Granite」がある。
同氏はGraniteについて「やみくもに大規模なモデルを目指すのではなく、ビジネスの現場で使う最適なモデルであるか否かがポイントになる。軽量かつ高精度なモデルとして提供し、レスポンスの速さやオンプレミス、エッジでも動かせるという特性を享受できる」と強調する。Graniteは昨年10月に最新版「Granite 3.0」を発表し、直近では同12月に「同3.1」、2025年2月に「同3.2」とアップデートを続けている。
強化学習とLLM実行時のコストがカギとなる推論機能
そして、Graniteの詳細に関しては、日本IBM 東京基礎研究所 技術理事の倉田岳人氏が紹介した。同氏は「エンタープライズAIのためのLLMとしてスタートし、3.1でコンテキストサイズを128kまで拡張したほか、マルチリンガル性能を向上し、3.2では推論機能を導入した。LLMに加え、LLMの入出力に対するガードレール機能などの『Granite Guardian』、画像の入力に対応した『Granite 3.2 Vison Models』を提供している」と説明。
倉田氏は3.2に実装され、最近注目を集めている推論機能について「推論を行うことで複雑な問題をステップごとに分解し、解決できるようになり、エージェントの機能強化につながる」という。
そして、推論機能が注目されている理由ついて同氏は「一時は下火になった強化学習を事後学習として行うことでAIモデルの動作が改善するほか、LLMの実行時に計算コストをかけると性能が向上することが分かってきたからだ。強化学習でモデルを改良し、実行時にコストをかけることで推論機能が実現されている」と話す。
実際、3.2は3.1に追加の強化学習ステップを導入することで推論の能力が強化され、DeepSeek R1を蒸留することで推論機能を強化している軽量モデルとは異なり、Graniteが持つ信頼性、安全性を担保しているという。また、日本語性能も向上している。
将来を見据えたwatson.aiとwatsonx Orchestrateの機能
再び田中氏に変わり、エージェント領域の中核となるソリューションとしてwatsonx Orchestrateを解説した。
同氏は「AIを問い合わせの用途で使うだけでなく、人が行うタスクをAIが自律的に実行して、結果を返してくれる仕組みがAIエージェントの考え方。watsonx Orchestrateはユーザーとのやり取りをチャットインタフェースで支援し、質問に回答するとともに裏側で抱えているタスクを実行するためのスキルを経由して、さまざまな業務システムや基幹システム、SaaS(Software as a Service)と連携する」と述べている。
IBMでは現在のAIエージェントは、シングルエージェントの世界一歩手前の状態ではあるが、将来的には複数のエージェントが連携し合うマルチエージェントの世界になると予測。同社では、このような世界に向けて「カスタム構築のエージェント」「複数エージェントのオーケストレーション」「事前構築済みのエージェント」の3つの革新を想定し、watson.aiとwatsonx Orchestrateの機能拡充を進めている。
watson.aiでは「Agent Lab」をβ版で提供。自律的なエージェントを構築する場合、プログラミングベースのフレームワークで実装する流れになるが、一気にスキルレベル、ハードルが高くなる。そのため、エージェント実装のためのツール「LangGraph」を同機能に組み込み、GUIで支援しつつ自由度の高いフレームワークベースのエージェントを構築できる機能となる。
ユーザーが定義するエージェントとして計画・実行し、反映や見直しなどの振る舞いを定義する指示文に加え、エージェント内でどのようなツールを呼び出すべきかなどをGUIベースの操作で組み上げてエージェントに実装できるという。
watsonx Orchestrateでは新機能として「Agent Chat」を追加。これまでエージェントは単一のものを各業務領域でユーザーのリクエストに回答するなど、狭い領域での活用がメインになっていた。そのため、新機能はユーザーが明示的にどのエージェントとやり取りするのかを指定しなくても、Agent Chatが最適なエージェントを探してルーティングするものとなる。
現状でAIエージェントの代表的なユースケースは、顧客・社員からの問合せ対応やERP(Enterprise Resource Planning)/CRM(Customer Relationship Management)など複数システムにまたがった周辺業務の効率化、複数モデルやプロンプトの使い分け、システムとの連携といった生成AIの業務への活用などを挙げている。
IBMが取り組むAI活用の社内事例
次に、日本IBM テクノロジー事業本部 データ・プラットフォーム事業部 製品統括営業部部長の四元菜つみ氏がグローバルにおけるIBM社内のAI活用に関する事例を紹介した。
同社が社内システムの変革を行うきっかけは2020年にさかのぼる。同氏は「2020年以前の社内システムは、ウォーターフォール型で自社でスクラッチ開発したものが多くあり、ヘルプデスクは電話やメール、対面でのサポートが主だった」と振り返る。
2020年以降、グローバルで新しいテクノジーや複数の業務アプリケーションを採用しつつ、全体最適化されたITインフラの整備とアジャイル型開発を推進する変革に取り組むこととした。その反面、利用するアプリケーションの増加や仕様の頻繁な変更、これらに伴うヘルプデスクの負荷が増大するなどの課題が発生していた。
四元氏は「コロナ禍で対面のサポートが難しく、多くのSaaSベンダーがさまざまなパッケージをリリースし、IBM自身も活用して社内システムを整備していこうという動きが活発化したのが2022年。ただ、従業員からすると利用アプリが膨大かつ加速度的に増加したことから、いつ、どのような時にどのようなツールを使えばいいのか、判然となしない状況があったほか、手順書の準備やSaaSパッケージはインタフェースの変更が多いため、すぐに使いづらくなってしまう側面があった」という。
こうした課題を解決するため、同社では“的確なガイダンスの提供”や“処理の自動実行”をサポートするAIチャットボット「Askシリーズ」を展開することにした。その中で同氏は人事業務、営業、調達・購買業務のユースケースを示した。
人事、営業、調達・購買業務でAIを活用
人事業務は「AskHR」として100超の人事関連業務の問合せ回答や、61の業務処理の自動化に対応(2024年12月時点)。期限までに必要となる従業な業務処理が遅延している対象者や、緊急事態時の全社員への一斉アラートなどをSlackと連携し、プッシュ型で自動的にアテンションする機能を提供している。
社員の業務自動化では出生・経費精算や休暇申請、給与明細の取得など、40の処理を自動化し、マネージャーの業務自動化では人事異動、経費管理、個人・部門の業績管理をはじめ21の処理を自動化している。
これにより、人事部門ではAIエージェントに任せられる作業は任せ、HR視点でコーチングや指導に注力することができるという。年間のSlack上などでのやり取りとは1000万以上、人事部の予算を40%削減し、AskHRで問い合わせる従業員の割合は94%、マネージャーや役員の利用率はいずれも90%超となっている。
営業では、IBMのハードウェアやソフトウェア、クラウド、コンサルティングなどさまざまなサービスの膨大な営業関連資料が存在しているため、適切な情報が見つけづらくなっている。そのような状況に対し「Ask Sales」は営業がソリューションを学び、販売できるように、いつでも情報にアクセスを可能としており、ローンチ後に1週間で4700件超の質問を受け付けた。
また「Digital Sales Asistant」はスプレッドシートで煩雑な管理や顧客に最適化されたコンテンツ作成が難しいことから、デジタルセールスにおける日々の業務の生産性向上と自動化を支援し、対応品質が25~35%改善するとともに、50~70%の時間節約につなげている。
調達・購買業務については「Ask Procurement」を提供。サプライヤーと調達に関する洞察を労力をかけずに得ることを可能としている。適用領域は支出や契約、PO(Purchase Order)・インボイス、調達パイプライン、社内ポリシー、プロセス、コンプライアンスチェックなど、従来は数十カ所に点在していた情報を1カ所に統合し、年間2万6000時間の時間短縮を実現している。
さらに、請求書処理でもAIを活用し、価格と数量の不一致などでブロックされた請求書を自動的に識別して、請求者に解決策を提案。手作業による調査が不要となり、支払い遅延金の削減のほか90%以上の時間短縮を可能としている。結果として、全体で前年比20%の人件費削減と、ベンダーに対する支出を20億米ドルの削減効果があったとのことだ。
最後に田中氏は「当社ではデータやガバナンス、アシスタント、業務にインパクトのある領域でのAI活用を支援していく。これがIBMとしての狙い、方針となる」と述べ、説明を結んだ。