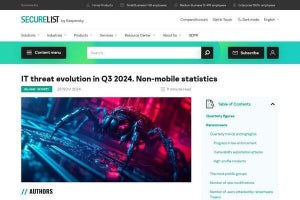Zscalerは2月25日、同社が実施したサイバーレジリエンスに関する調査結果、2025年の事業戦略に関する説明会を開催した。
同社は2024年12月に同調査を実施、世界12カ国(オーストラリア、インド、日本、シンガポール、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、スウェーデン、オランダ、英国・アイルランド、米国)の1,700人から回答を得た。うち、日本の回答者は150人。
同調査では、サイバーレジリエンスを「システムやネットワーク内でサイバーインシデントに対応し封じ込めなければならない状況下で、組織が運用の継続性を維持する能力」と定義した。
Resilient by Designが求められる背景
代表取締役の金田博之氏は、2024年に日本企業に対して行われた暗号化攻撃の件数が2.2億件、フィッシング攻撃の件数が2,700万件だったことを引き合いに出し、サイバー攻撃対策の必要性を訴えた。
加えて、金田氏はAIが介入することでサイバー攻撃に容易に行えるようになっているほか、攻撃対象が拡大していると指摘した。
こうした状況で求められる次世代のサイバー攻撃対策として、「Resilient by Design」が必須になると金田氏は述べた。Resilient by Designとは、セキュリティ対策を設計する段階からプロアクティブに保護の仕組みを組み込んでおくという考え方を指す。
同社は、「Resilient by Design」を実現するにあたって、3つのステップを踏むことを提唱している。3つのステップとは、「現在のインフラの複雑性を軽減」「:レジリエンスのためのアーキテクチャを(再)構築」「リアクティブからプロアクティブへ」だ。
金田氏は「サイバー攻撃対策は事後では手遅れ。サイバー攻撃に対し、日本は『もし』と考えているが、世界は『いつ』と考えている。いつサイバー攻撃が起きるかという時代ではなくなった」と、「Resilient by Design」の重要性を訴えた。
各国におけるサイバーレジリエンスの実態
サイバーレジリエンスに関する調査結果は、「Resilient by Design」の必要性を明らかにしているといえる。
同調査により、日本のITリーダーの33%が自組織のITインフラはレジリエンスが高いと考えており、58%が自社のサイバーレジリエンスへのアプローチは成熟していると評価していることが明らかになった。グローバルの結果を見ると、前者の回答率は49%、後者の回答率は78%と、いずれも日本のほうが自信がない結果が出ている。
一方、91%が現行のサイバーレジリエンス対策が有効であると認識していることが明らかになっている。
加えて、自組織の戦略がAIの台頭に伴う新たな攻撃に対応できる最新のものであると答えた日本の回答者は37%となっており、自信と実際の行動との間に乖離があることがわかった。
金田氏は「日本企業は危機感が薄い」と指摘した。
こうした状況を引き起こしている主な要因としては、組織の経営陣による投資不足が考えられるという。
回答者によると、大半のリーダーはサイバーレジリエンスの重要性が高まっていることを理解しているが、日本ではそれを優先事項の一つと考えるリーダーは40%にとどまっているという。
この優先順位付けは、サイバーレジリエンスに割り当てられる予算額にも反映されており、回答者の43%が現在の投資規模では日本のニーズを満たせないと回答している。
2025年に注力する地域、セグメント、業種
説明会では、2025年の事業戦略の紹介も行われた。金田氏は、日本における事業拡大のポイントとして、3点挙げた。
1点目は「新たな地域の注力」だ。具体的には、大阪オフィスを今春に新設する。
2点目は「新たなセグメントへの注力」だ。具体的には、中堅中小企業向けビジネスの拡大を狙う。金田氏によると、中堅中小企業ビジネスにおいてはパートナーにかなり投資しているほか、半年前に開発した専用パッケージが奏功しているとのことだ。今後は、さらにパートナーに投資して、共同セミナーや人材育成に取り組む構えだ。
3点目は「新たな業種への注力」だ。具体的には、公共部門のビジネスの拡大に取り組む。金田氏は公共ビジネスについて、「一昨年前からニーズが顕在化しており、ゼロトラスト構築にあたり、設計や企画段階から支援している。政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(Information system Security Management and Assessment Program:ISMAP)も受けた。4つ目の事業になるまで成長しつつある」と説明した。