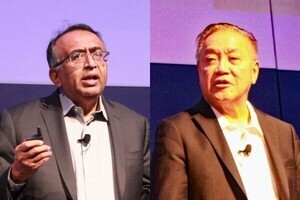BroadcomはVMwareを買収した後、クラウドプラットフォーム「VMware Cloud Foundation」(VCF)を中心にVMwareの事業を展開している。VCFと並ぶVMwareの主力事業に、エンドユーザーコンピューティング(EUC)があった。
今年2月、EUC部門がBroadcomから独立し、グローバル投資会社である KKR 傘下で独立事業会社「Omnissa」となることが発表された。独立が発表された後は、事業の方向性が明らかにされていなかった。
そうした中、Omnissaは9月26日、フラッグシップイベント「Omnissa ONE」を東京で開催し、CEOら幹部が日本における事業展開について説明した。同イベントは東京を皮切りに、米国ダラス、オランダのアムステルダムで開催される。東京が初のイベントの開催地に選ばれたことから、同社にとって、日本市場が重要であることがうかがえる。
基調講演では、CEO(最高経営責任者) シャンカー・アイヤー氏をはじめとした経営層が、同社の事業の展開、製品開発について説明を行った。VMwareの一部門として展開されてきたEUC事業が、会社として展開されることでどう変わるのだろうか。
将来は、Workspace ONEやHorizonの料金体系も変更
アイヤー氏は冒頭、「OmnissaはVMwareから独立した新しいソフトウェアの会社であり、7月1日に事業を開始した。新しい会社の形をとることで、 俊敏にプラットフォームを提供し、デジタルワークを推進できる。将来に対し、ワクワクしている」と語った。
アイヤー氏は、同社の年間経常収益が15億ドル、都度取引による売り上げが40億ドル、顧客が2万6000社以上であると述べ、同社のビジネスが盤石であることをアピールした。
Omnissaは以下のミッションを掲げており、旧VMwareの事業と方向性は変わらない。
アイヤー氏は、投資の柱として「ビジネスのしやすさ」「テクノロジーイノベーション」「エコシステムの拡大」の3点を挙げた。
「ビジネスのしやすさ」を実現する施策としては、価格モデルの変更、取引形態の簡便化、カスタマーサービス部門の増強がある。既存のユーザーにとっては、ここが最も影響を受けるかもしれない。
アイヤー氏は「柔軟なプライシングモデルを提供することを視野に入れている。このモデルでは、ソフトウェアスイートを売らずに、ユーザーが不要なソフトの代金をいただかない。これまで以上に価値を提供できる」と述べた。
VMware vSphereやVCFをはじめとする製品の料金体系がサブスクリプションモデルに移行したことで、既存のユーザーに影響を与えているが、EUC製品も同様になりそうだ。
「テクノロジーイノベーション」としては、VDI(Virtual Desktop Infrastructure)とUEM(Unified Endpoint Management)に投資するとともに、DEX(Digital Employee Experience:)やMTD(Mobile Threat Defense)といった新領域への展開も目指す。
独立した企業としてのメリット、ブランド構築など、世間の疑問に回答
続いて、シニアバイスプレジデント マーケティング担当レヌ・ウパディヤイ氏、シニアバイスプレジデント レベニュー担当ロバート・ルーラス氏が登場し、「お客様の疑問に答える」という形で、同社の現状を説明した。
初めに、ウパディヤイ氏は「完全に独立した企業となったが、これにより何が変わるのか」という質問を投げかけた。
この問いに対し、アイヤー氏は次のように答えた。
「まず、強い企業基盤の下で、ビジネスをスタートしており、プロダクトとしてワークスペース、プラットフォームと強力な基盤を持っている。今後、独立したソフトウェア企業として投資をしていく予定であり、プロダクトの大胆な展開が可能となる」
アイヤー氏の言葉に付け加えるとして、ルーラス氏は「EUCをサイドビジネスと見ている企業も多いが、われわれは主要なビジネスとしている。また、良質なサポートを提供するため、日本ではパートナーセールスの人員を2倍に増やした」と述べた。
さらに、レヌ氏は「では、会社として立ち上がったことで、ビジネスはしやすくなるのか」と畳みかけた。すると、アイヤー氏は「その通り。われわれは2つの分野で投資を行っている」と語った。
投資を行っている1つ目の分野は先に挙げたテクノロジーで、統合したプラットフォームを提供することにより、シームレスなカスタマーエクスペリエンスを実現するという。2つ目の分野は先に挙げたプライシングで、「ライシングを柔軟にする。これにより、ユーザーが本当の意味で価値に見合った料金を支払うようにする。われわれはバリューベースのプライシングを提供する。テクノロジー企業として、こういう哲学が期待されている」とアイヤー氏は説明した。
ルーラス氏は、「当社の製品は100%パートナーが提供する。したがって、われわれはパートナー支援の人材を大幅に増やしており、新しいパートナープログラムを提供する」と述べた。
そして、レヌ氏は「VMwareというブランドがなくなるがどうするか」と問いかけた。
アイヤー氏は「ブランドがなくなることの影響は当然、予測している。しかし、デジタルワークスペースは幅広く、これまで十分なサービスを提供してきたわけではない。投資を続けて、ブランド構築を進めていく。将来的には、VMwareの規模に成長すると考えている」と語った。
Omnissaプラットフォーム全体にAIベースのサービスを組み込む
製品のロードマップについては、シニアバイスプレジデント 製品担当バラス・ランガラジャン氏が説明した。同氏は、企業が抱える課題を解決するため、自律型ワークスペースを提供すると述べた。
自律型ワークスペースは、自律型の構成、修復、セキュリティから構成されている。例えば、インシデントを検知したら自動で修復を行い、また、脆弱性やコンプライアンス違反を検知したら指導で修復する。
こうした自律型ワークスペースは、4つのソリューションから構成されているOmnissaプラットフォームによって実現される。4つのソリュ-ションとは「仮想デスクトップとアプリ」「UEM」「セキュリティとコンプライアンス」「DEX」だ。ランガラジャン氏は、統合プラットフォームのメリットについて、「あらゆるデバイス、OS、クラウドを利用できるという選択肢がある。また、サイバーレジリエンスが担保され、インシデントがあった場合自動でリカバリでき、コストも最適化される」と述べた。
ランガラジャン氏は今後、新たなソリューションを開発するのではなく、AIにおって既存の製品を進化させると説明した。Omnissaプラットフォーム全体にAIベースのサービスを組み込み、自律型ワークスペースを実現するという。
「生成AIには可能性がある。われわれは顧客の課題解決に関連した形で活用することを考えている。ChatGPTが出る前から、生成AIを活用したインサイトを提供している」(ランガラジャン氏)
インサイトでは、ガイド付きで原因を分析する。そのほか、対話型アシスタント、ガイド付きレコメンデーション、自律型ワークスペースの開発が進められている。